令和6年度 社会福祉法人恩賜財団 済生会支部 栃木県済生会宇都宮 病院情報の公表
病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
- リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
- 血液培養2セット実施率
- 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
- 転倒・転落発生率
- 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
- 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
- d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
- 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
- 身体的拘束の実施率
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 1597 | 363 | 468 | 762 | 1066 | 1629 | 2307 | 4614 | 2752 | 409 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし | 37 | 19.24 | 20.78 | 45.95% | 83.08 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 27 | 13.07 | 13.66 | ー | 76.78 | |
| 180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 なし | 13 | 13.92 | 20.06 | ー | 81.38 | |
| 030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 終夜睡眠ポリグラフィーあり | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 080010xxxx0xxx | 蜂窩織炎(蜂巣炎) 手術・処置等1 なし | ー | ー | ー | ー | ー |
【集計方法と定義】
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇各診療科別に患者数の多いDPC14桁分類についてDPCコード、名称、患者数、自院の平均在院日数、全国の平均在院日数、転院率、平均年齢を集計しています。
◇4位以下のDPCコードについては、患者数10症例未満のため、各項目を非公開としています。
◇転院数10症例未満の症例は、転院率を非公開としています。
【解説】
内科では、さまざまな専門診療科と緊密な連携を取りながら診療にあたっています。
当科で最も多かったのは、誤嚥性肺炎です。肺炎の治療には、呼吸器内科とも連携しながら治療にあたっておりますが、敗血症性のショックや他の重複疾患など全身管理が必要になる場合など、救急・集中治療科と協力して診療にあたっています。特に高齢者は、単一疾患だけではなく、免疫機能が低下している場合などは、急速に重症化することもあり、いわゆる全身管理が必要になる場合も多く見られます。高齢者が多く、基礎疾患も多岐にわたっているため、当科で担当させていただき、各専門家の意見を集約して対応しています。
2番目に多いのは、尿路感染症です。平均年齢が70歳を超えている事からも分かるように、高齢化が進んでいることが背景としてあります。男性であれば、前立腺による排尿障害が顕著になったり、女性でも日常活動が低下し、腹圧がかかりにくくなることなどで誘発されやすい状態になっていると思われます。また、基礎疾患に糖尿病などがあれば、さらに”易感染性”といって、バイ菌に負けやすい傾向も顕著になります。男女ともに、活動性の低下がきっかけとなり発症することが多いため、環境面での配慮も必要になる事が多く、メディカルソーシャルワーカーと連携して対応しています。
3番目に多いのは、敗血症です。細菌の侵入門戸は、尿路、腸管など多岐にわたります。ショック症状をきたすこともあり、3階西病棟(救急病棟)のハイケアユニットをベースに、循環管理も行っています。
4番目に多いのは、睡眠時無呼吸症候群に対して実施した終夜睡眠ポリグラフィー検査を実施です。終夜睡眠ポリグラフィー検査は、睡眠中の脳波や呼吸状態などを調べます。入院は1泊2日となっています。
5番目に多いのは、蜂窩織炎(蜂巣炎)です。下肢などの皮膚及び皮下脂肪の細菌感染であり、これまでの手術などで、浮腫が残っていて起こしやすい方もいます。また、糖尿病による神経障害で、痛みという症状が出ないままに、ショック状態で救急搬送される方も少なくありません。蜂窩織炎の範疇を超えて、壊死を起こしたり、筋膜への波及も疑われる症例もあり、整形外科や救急・集中治療科と一緒に取り組むこともあります。
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇各診療科別に患者数の多いDPC14桁分類についてDPCコード、名称、患者数、自院の平均在院日数、全国の平均在院日数、転院率、平均年齢を集計しています。
◇4位以下のDPCコードについては、患者数10症例未満のため、各項目を非公開としています。
◇転院数10症例未満の症例は、転院率を非公開としています。
【解説】
内科では、さまざまな専門診療科と緊密な連携を取りながら診療にあたっています。
当科で最も多かったのは、誤嚥性肺炎です。肺炎の治療には、呼吸器内科とも連携しながら治療にあたっておりますが、敗血症性のショックや他の重複疾患など全身管理が必要になる場合など、救急・集中治療科と協力して診療にあたっています。特に高齢者は、単一疾患だけではなく、免疫機能が低下している場合などは、急速に重症化することもあり、いわゆる全身管理が必要になる場合も多く見られます。高齢者が多く、基礎疾患も多岐にわたっているため、当科で担当させていただき、各専門家の意見を集約して対応しています。
2番目に多いのは、尿路感染症です。平均年齢が70歳を超えている事からも分かるように、高齢化が進んでいることが背景としてあります。男性であれば、前立腺による排尿障害が顕著になったり、女性でも日常活動が低下し、腹圧がかかりにくくなることなどで誘発されやすい状態になっていると思われます。また、基礎疾患に糖尿病などがあれば、さらに”易感染性”といって、バイ菌に負けやすい傾向も顕著になります。男女ともに、活動性の低下がきっかけとなり発症することが多いため、環境面での配慮も必要になる事が多く、メディカルソーシャルワーカーと連携して対応しています。
3番目に多いのは、敗血症です。細菌の侵入門戸は、尿路、腸管など多岐にわたります。ショック症状をきたすこともあり、3階西病棟(救急病棟)のハイケアユニットをベースに、循環管理も行っています。
4番目に多いのは、睡眠時無呼吸症候群に対して実施した終夜睡眠ポリグラフィー検査を実施です。終夜睡眠ポリグラフィー検査は、睡眠中の脳波や呼吸状態などを調べます。入院は1泊2日となっています。
5番目に多いのは、蜂窩織炎(蜂巣炎)です。下肢などの皮膚及び皮下脂肪の細菌感染であり、これまでの手術などで、浮腫が残っていて起こしやすい方もいます。また、糖尿病による神経障害で、痛みという症状が出ないままに、ショック状態で救急搬送される方も少なくありません。蜂窩織炎の範疇を超えて、壊死を起こしたり、筋膜への波及も疑われる症例もあり、整形外科や救急・集中治療科と一緒に取り組むこともあります。
循環器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050050xx0200xx | 狭心症 経皮的冠動脈形成術等あり | 553 | 3.99 | 4.18 | ー | 71.35 | |
| 050050xx9910xx | 狭心症 心臓カテーテル検査等あり | 227 | 2.95 | 3.07 | ー | 70.14 | |
| 050050xx9920xx | 狭心症 心臓カテーテル検査+血管内超音波検査等あり | 191 | 3.14 | 3.27 | ー | 71.47 | |
| 050030xx03000x | 急性心筋梗塞 経皮的冠動脈形成術等あり 手術・処置1なし or 心臓カテーテル検査あり | 141 | 10.50 | 11.37 | ー | 68.62 | |
| 050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 他院からの転院以外 | 113 | 16.41 | 17.33 | 8.85% | 79.93 |
【集計方法と定義】
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇各診療科別に患者数の多いDPC14桁分類についてDPCコード、名称、患者数、自院の平均在院日数、全国の平均在院日数、転院率、平均年齢を集計しています。
◇転院数10症例未満の症例は、転院率を非公開としています。
【解説】
循環器内科では、狭心症や心筋梗塞などの虚血性心疾患をはじめ、心不全、弁膜症、肺塞栓症、下肢動脈硬化症、不整脈、先天性心疾患など、あらゆる循環器疾患に対して質の高い医療を提供できる診療体制を整えています。とくに心臓の救急疾患に関しては、当院が宇都宮医療圏で唯一の救命救急センターであることから、常に迅速かつ高度な医療が提供できるよう、スタッフ一同が24時間体制で対応しています。
患者数別にみると、最も多いのは、狭心症に対してカテーテルを使用し、冠動脈の狭窄や閉塞部分の治療を行う患者さんです。これらの治療は予約入院による待機的なものだけでなく救急救命センターを併設していることにより、緊急のカテーテル治療にも対応しています。平均在院日数は3.99日と短く、早期の退院が可能です。
2番目に多いのは、狭心症に対して冠動脈の狭窄や閉塞部分の状態を確認するため、心臓カテーテル検査のみを行う患者さんです。
3番目に多いのは、2番目に多い狭心症の患者さんと同様ですが、心臓カテーテル検査に加えて血管内超音波検査などを併用して行うケースです。中等度の冠動脈狭窄では、薬による治療が望ましい場合もあるため、症例ごとにカテーテル治療の適応を慎重に検討しています。
4番目に多いのは、急性心筋梗塞に対し心臓カテーテルを使用し、冠動脈の狭窄や閉塞部分の治療を行う患者さんです。発症から数時間以内の「超急性期」においては、梗塞領域の縮小を目的としてカテーテル手術を行います。当院では救急外来の来院から90分以内にカテーテル手術を開始できるよう、24時間体制を整えています。
5番目に多いのは、心不全の患者さんです。平均年齢は79.93歳となっています。高齢者や心臓弁膜症などの基礎疾患を持つ重症例にも対応できるよう、集中治療室での全身管理を行っています。
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇各診療科別に患者数の多いDPC14桁分類についてDPCコード、名称、患者数、自院の平均在院日数、全国の平均在院日数、転院率、平均年齢を集計しています。
◇転院数10症例未満の症例は、転院率を非公開としています。
【解説】
循環器内科では、狭心症や心筋梗塞などの虚血性心疾患をはじめ、心不全、弁膜症、肺塞栓症、下肢動脈硬化症、不整脈、先天性心疾患など、あらゆる循環器疾患に対して質の高い医療を提供できる診療体制を整えています。とくに心臓の救急疾患に関しては、当院が宇都宮医療圏で唯一の救命救急センターであることから、常に迅速かつ高度な医療が提供できるよう、スタッフ一同が24時間体制で対応しています。
患者数別にみると、最も多いのは、狭心症に対してカテーテルを使用し、冠動脈の狭窄や閉塞部分の治療を行う患者さんです。これらの治療は予約入院による待機的なものだけでなく救急救命センターを併設していることにより、緊急のカテーテル治療にも対応しています。平均在院日数は3.99日と短く、早期の退院が可能です。
2番目に多いのは、狭心症に対して冠動脈の狭窄や閉塞部分の状態を確認するため、心臓カテーテル検査のみを行う患者さんです。
3番目に多いのは、2番目に多い狭心症の患者さんと同様ですが、心臓カテーテル検査に加えて血管内超音波検査などを併用して行うケースです。中等度の冠動脈狭窄では、薬による治療が望ましい場合もあるため、症例ごとにカテーテル治療の適応を慎重に検討しています。
4番目に多いのは、急性心筋梗塞に対し心臓カテーテルを使用し、冠動脈の狭窄や閉塞部分の治療を行う患者さんです。発症から数時間以内の「超急性期」においては、梗塞領域の縮小を目的としてカテーテル手術を行います。当院では救急外来の来院から90分以内にカテーテル手術を開始できるよう、24時間体制を整えています。
5番目に多いのは、心不全の患者さんです。平均年齢は79.93歳となっています。高齢者や心臓弁膜症などの基礎疾患を持つ重症例にも対応できるよう、集中治療室での全身管理を行っています。
血液・リウマチ科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 化学療法(リツキシマブ)あり | 40 | 10.00 | 8.65 | ー | 75.23 | |
| 130030xx99x7xx | 非ホジキンリンパ腫 化学療法(ベンダムスチン塩酸塩)あり | 21 | 11.38 | 12.54 | ー | 75.00 | |
| 130030xx99xBxx | 非ホジキンリンパ腫 化学療法(ブレンツキシマブ ベドチン)あり | 17 | 11.59 | 12.23 | ー | 77.35 | |
| 130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 化学療法(リツキシマブ+フィルグラスチム)あり | 15 | 45.07 | 19.30 | ー | 63.87 | |
| 130010xx97x2xx | 急性白血病 手術・輸血あり 化学療法あり | 14 | 51.07 | 35.63 | ー | 56.64 |
【集計方法と定義】
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇各診療科別に患者数の多いDPC14桁分類についてDPCコード、名称、患者数、自院の平均在院日数、全国の平均在院日数、転院率、平均年齢を集計しています。
◇転院数10症例未満の症例は、転院率を非公開としています。
【解説】
血液・リウマチ科は、白血病・悪性リンパ腫・多発性骨髄腫などの造血器腫瘍をはじめ、再生不良性貧血・骨髄異形成症候群・鉄欠乏性貧血・巨赤芽球性貧血・溶血性貧血などの各種貧血症、さらに特発性血小板減少性紫斑病や血友病などの出血性疾患を含む、血液疾患全般を診療対象としています。
患者数別にみると、最も多いのは、非ホジキンリンパ腫(悪性リンパ腫)に対してリツキシマブ(リツキサン)という注射薬を用いた化学療法(抗がん剤治療)を行う患者さんです。非ホジキンリンパ腫は、リンパ節、脾臓、胸腺、扁桃などを含むリンパ組織に加え、消化管、肝、甲状腺など、さまざまな臓器にも腫瘤を形成することがあります。タイプや病期により治療法は異なりますが、化学療法が治療の中心となります。
2番目に多いのは、非ホジキンリンパ腫に対して、ベンダムスチン塩酸塩(トレアキシン)による化学療法を行う患者さんです。
3番目に多いのは、非ホジキンリンパ腫に対して、ブレンツキシマブ ベドチン(アドセトリス)による化学療法を行う患者さんです。
4番目に多いのは、非ホジキンリンパ腫に対して、リツキシマブ(リツキサン)による化学療法を行い、さらにその治療に伴う好中球減少症に対してフィルグラスチムを使用する患者さんです。
5番目に多いのは、急性白血病に対して、輸血などの支持療法と化学療法を併用して治療を行う患者さんです。
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇各診療科別に患者数の多いDPC14桁分類についてDPCコード、名称、患者数、自院の平均在院日数、全国の平均在院日数、転院率、平均年齢を集計しています。
◇転院数10症例未満の症例は、転院率を非公開としています。
【解説】
血液・リウマチ科は、白血病・悪性リンパ腫・多発性骨髄腫などの造血器腫瘍をはじめ、再生不良性貧血・骨髄異形成症候群・鉄欠乏性貧血・巨赤芽球性貧血・溶血性貧血などの各種貧血症、さらに特発性血小板減少性紫斑病や血友病などの出血性疾患を含む、血液疾患全般を診療対象としています。
患者数別にみると、最も多いのは、非ホジキンリンパ腫(悪性リンパ腫)に対してリツキシマブ(リツキサン)という注射薬を用いた化学療法(抗がん剤治療)を行う患者さんです。非ホジキンリンパ腫は、リンパ節、脾臓、胸腺、扁桃などを含むリンパ組織に加え、消化管、肝、甲状腺など、さまざまな臓器にも腫瘤を形成することがあります。タイプや病期により治療法は異なりますが、化学療法が治療の中心となります。
2番目に多いのは、非ホジキンリンパ腫に対して、ベンダムスチン塩酸塩(トレアキシン)による化学療法を行う患者さんです。
3番目に多いのは、非ホジキンリンパ腫に対して、ブレンツキシマブ ベドチン(アドセトリス)による化学療法を行う患者さんです。
4番目に多いのは、非ホジキンリンパ腫に対して、リツキシマブ(リツキサン)による化学療法を行い、さらにその治療に伴う好中球減少症に対してフィルグラスチムを使用する患者さんです。
5番目に多いのは、急性白血病に対して、輸血などの支持療法と化学療法を併用して治療を行う患者さんです。
消化器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100xx01xxxx | 大腸腺腫 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 99 | 2.26 | 2.57 | ー | 69.15 | |
| 060340xx03x00x | 胆管結石、胆管炎 内視鏡的乳頭切開術等あり | 70 | 13.43 | 8.88 | ー | 76.16 | |
| 060102xx99xxxx | 大腸憩室炎、大腸憩室出血(穿孔又は膿瘍を伴わない) | 67 | 7.93 | 7.60 | ー | 69.46 | |
| 060140xx97x0xx | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) 内視鏡的消化管止血術等あり | 37 | 13.46 | 10.93 | ー | 72.05 | |
| 060102xx97xxxx | 大腸憩室炎、大腸憩室出血(穿孔又は膿瘍を伴わない)輸血等あり | 36 | 10.42 | 10.96 | ー | 73.33 |
【集計方法と定義】
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇各診療科別に患者数の多いDPC14桁分類についてDPCコード、名称、患者数、自院の平均在院日数、全国の平均在院日数、転院率、平均年齢を集計しています。
◇転院数10症例未満の症例は、転院率を非公開としています。
【解説】
消化器内科では、消化器全般にわたる診断および治療を行っており、幅広い疾患に対応しています。
患者数別にみると、最も多いのは、大腸腺腫やポリープなどの良性腫瘍に対して内視鏡で切除を行う患者さんです。これらの手術は、入院当日または入院翌日に実施されることが多く、手術翌日に退院となるケースが一般的です。平均在院日数は2.26日と短く、低侵襲で効率的な治療が可能となっています。
2番目に多いのは、総胆管結石や胆管炎、胆管狭窄などの胆道疾患に対し、内視鏡を用いて胆道の出口(乳頭部)を切開し結石を除去したり、胆管ステント留置を行う患者さんです。総胆管結石は通常無症状ですが、大きな結石が嵌頓すると閉塞性黄疸などの症状が現れます。胆管炎を伴う場合には発熱がみられ、急性閉塞性化膿性胆管炎を引き起こすと、敗血症からショックに至ることもあり、生命にかかわる重篤な状態となることがあります。
3番目に多いのは、大腸憩室炎や大腸憩室出血の患者さんです。憩室内に糞便が停滞することで急性憩室炎を発症し、腹痛や発熱などの症状が現れます。初期治療は抗生物質による内科的治療が基本ですが、穿孔や腹膜炎、大量出血などの重篤な合併症が生じた場合には、外科的な腸切除が必要となることもあります。
4番目に多いのは、出血を伴う胃潰瘍や十二指腸潰瘍に対して内視鏡的消化管止血術や血管塞栓術を行う患者さんです。これらの治療は、消化管出血の制御を目的とした緊急性の高い処置です。
5番目に多いのは、大腸憩室出血に対して輸血を行う患者さんです。出血量が多く貧血を伴う場合には、迅速な輸血対応が求められます。
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇各診療科別に患者数の多いDPC14桁分類についてDPCコード、名称、患者数、自院の平均在院日数、全国の平均在院日数、転院率、平均年齢を集計しています。
◇転院数10症例未満の症例は、転院率を非公開としています。
【解説】
消化器内科では、消化器全般にわたる診断および治療を行っており、幅広い疾患に対応しています。
患者数別にみると、最も多いのは、大腸腺腫やポリープなどの良性腫瘍に対して内視鏡で切除を行う患者さんです。これらの手術は、入院当日または入院翌日に実施されることが多く、手術翌日に退院となるケースが一般的です。平均在院日数は2.26日と短く、低侵襲で効率的な治療が可能となっています。
2番目に多いのは、総胆管結石や胆管炎、胆管狭窄などの胆道疾患に対し、内視鏡を用いて胆道の出口(乳頭部)を切開し結石を除去したり、胆管ステント留置を行う患者さんです。総胆管結石は通常無症状ですが、大きな結石が嵌頓すると閉塞性黄疸などの症状が現れます。胆管炎を伴う場合には発熱がみられ、急性閉塞性化膿性胆管炎を引き起こすと、敗血症からショックに至ることもあり、生命にかかわる重篤な状態となることがあります。
3番目に多いのは、大腸憩室炎や大腸憩室出血の患者さんです。憩室内に糞便が停滞することで急性憩室炎を発症し、腹痛や発熱などの症状が現れます。初期治療は抗生物質による内科的治療が基本ですが、穿孔や腹膜炎、大量出血などの重篤な合併症が生じた場合には、外科的な腸切除が必要となることもあります。
4番目に多いのは、出血を伴う胃潰瘍や十二指腸潰瘍に対して内視鏡的消化管止血術や血管塞栓術を行う患者さんです。これらの治療は、消化管出血の制御を目的とした緊急性の高い処置です。
5番目に多いのは、大腸憩室出血に対して輸血を行う患者さんです。出血量が多く貧血を伴う場合には、迅速な輸血対応が求められます。
呼吸器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040040xx9910xx | 肺癌 気管支生検等あり | 258 | 2.36 | 3.03 | ー | 72.07 | |
| 040040xx99040x | 肺癌 化学療法あり | 87 | 6.90 | 8.16 | ー | 72.90 | |
| 040110xxxx10xx | 間質性肺炎 気管支生検等あり | 42 | 5.98 | 10.66 | ー | 71.33 | |
| 0400800x99x0xx | 肺炎等(市中肺炎以外) 手術なし | 40 | 17.00 | 18.16 | ー | 79.40 | |
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし | 39 | 16.41 | 16.40 | ー | 81.92 |
【集計方法と定義】
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇各診療科別に患者数の多いDPC14桁分類についてDPCコード、名称、患者数、自院の平均在院日数、全国の平均在院日数、転院率、平均年齢を集計しています。
◇転院数10症例未満の症例は、転院率を非公開としています。
【解説】
呼吸器内科では、呼吸器疾患全般にわたる診療を行っており、救急救命センターを併設していることから、緊急性の高い患者さんも積極的に受け入れています。特に、入院が必要となる急性呼吸不全、重症の肺炎、気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、びまん性肺疾患、そして肺癌の診断・治療に重点を置いています。肺癌は現在、がんによる死亡原因の中で最も多く、患者数も年々増加しています。抗がん剤の種類も近年多様化しており、患者さんの病期に応じて、化学療法を中心とした治療を行っています。
患者数別にみると、最も多いのは、肺癌(疑いも含む)に対して、気管支鏡などによる生検を行う患者さんです。これらは検査入院で対応するため、平均在院日数は2.36日と短くなっています。
2番目に多いのは、肺癌に対して化学療法(抗がん剤治療)を行う患者さんです。化学療法は外来でも実施可能ですが、抗がん剤の種類や患者さんの全身状態に応じて、入院での治療が選択されることもあります。
3番目に多いのは、間質性肺炎の患者さんです。薬剤性、放射線性、膠原病性など原因が明らかな場合もあれば、原因不明の特発性の場合もあります。感染などを契機に急速に呼吸不全をきたすこともあり、慎重な管理が求められます。
4番目に多いのは、医療・介護関連肺炎に対して薬物療法を行う患者さんです。これは、医療や介護を受けている方に発症する肺炎で、「市中肺炎」(基礎疾患がない、または軽微な基礎疾患を有する人が普段の社会生活の中でかかる肺炎)とは、DPCコード上で区別されています。高齢の患者さんが多く、平均年齢は79.44歳と高くなっています。
5番目に多いのは、75歳以上の高齢者で、市中肺炎に対して薬物療法を受ける患者さんです。
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇各診療科別に患者数の多いDPC14桁分類についてDPCコード、名称、患者数、自院の平均在院日数、全国の平均在院日数、転院率、平均年齢を集計しています。
◇転院数10症例未満の症例は、転院率を非公開としています。
【解説】
呼吸器内科では、呼吸器疾患全般にわたる診療を行っており、救急救命センターを併設していることから、緊急性の高い患者さんも積極的に受け入れています。特に、入院が必要となる急性呼吸不全、重症の肺炎、気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、びまん性肺疾患、そして肺癌の診断・治療に重点を置いています。肺癌は現在、がんによる死亡原因の中で最も多く、患者数も年々増加しています。抗がん剤の種類も近年多様化しており、患者さんの病期に応じて、化学療法を中心とした治療を行っています。
患者数別にみると、最も多いのは、肺癌(疑いも含む)に対して、気管支鏡などによる生検を行う患者さんです。これらは検査入院で対応するため、平均在院日数は2.36日と短くなっています。
2番目に多いのは、肺癌に対して化学療法(抗がん剤治療)を行う患者さんです。化学療法は外来でも実施可能ですが、抗がん剤の種類や患者さんの全身状態に応じて、入院での治療が選択されることもあります。
3番目に多いのは、間質性肺炎の患者さんです。薬剤性、放射線性、膠原病性など原因が明らかな場合もあれば、原因不明の特発性の場合もあります。感染などを契機に急速に呼吸不全をきたすこともあり、慎重な管理が求められます。
4番目に多いのは、医療・介護関連肺炎に対して薬物療法を行う患者さんです。これは、医療や介護を受けている方に発症する肺炎で、「市中肺炎」(基礎疾患がない、または軽微な基礎疾患を有する人が普段の社会生活の中でかかる肺炎)とは、DPCコード上で区別されています。高齢の患者さんが多く、平均年齢は79.44歳と高くなっています。
5番目に多いのは、75歳以上の高齢者で、市中肺炎に対して薬物療法を受ける患者さんです。
脳神経内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060xx99x30x | 脳梗塞 手術なし SPECT等あり 副傷病なし | 69 | 18.67 | 18.42 | 33.33% | 73.10 | |
| 010060xx99x40x | 脳梗塞 手術なし エダラボン治療あり 副傷病なし | 37 | 15.46 | 16.89 | 45.95% | 73.05 | |
| 010060xx99x20x | 脳梗塞 手術なし リハビリテーションあり 副傷病なし | 33 | 13.70 | 16.94 | ー | 76.76 | |
| 010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし | 25 | 18.24 | 18.68 | 60.00% | 66.16 | |
| 010230xx99x00x | てんかん 手術なし 副傷病なし | 25 | 9.08 | 6.89 | ー | 56.80 |
【集計方法と定義】
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇各診療科別に患者数の多いDPC14桁分類についてDPCコード、名称、患者数、自院の平均在院日数、全国の平均在院日数、転院率、平均年齢を集計しています。
◇転院数10症例未満の症例は、転院率を非公開としています。
【解説】
脳神経内科は神経疾患全般を対象として診療を行っています。急性期の疾患としては、脳卒中・てんかん重積・神経感染症を扱っており、亜急性から慢性疾患として、重症筋無力症・多発性硬化症・神経変性疾患(パーキンソン病・脊髄小脳変性症)・認知症疾患など幅広く診療しています。栃木県では脳卒中の発症数が多いため、当院では脳卒中(脳出血、脳梗塞、一過性脳虚血発作、くも膜下出血)の診断および治療に特に力をいれています。24時間365日対応可能な血栓溶解療法(t-PAの投与)の体制を整えており、迅速な治療が可能です。
患者数別にみると、最も多いのは、脳梗塞に対してSPECT(単一光子放射線型コンピューター断層撮影)装置を使用し、適切な治療を行っている患者さんです。脳梗塞には、血栓性、塞栓性、血行力学性などのタイプがあり、発症からの時間経過により、治療法が異なります。
2番目に多いのは、脳梗塞に対して脳保護薬であるエダラボンを使用し、治療を行う患者さんです。
3番目に多いのは、脳梗塞に対してリハビリテーションなどを中心に治療を行う患者さんです。
4番目に多いのは、JCS10(注1*)未満の意識障害を伴う非外傷性の脳出血の患者さんです。
5番目に多いのは、てんかんに対して抗てんかん薬などを使用し、治療を行う患者さんです。
また、当院では筋萎縮性側索硬化症(ALS)の患者さんに対して、HAL(Hybrid Assistive Limb)という歩行支援ロボットを用いたリハビリテーションを組み合わせた治療を行っています。HAL(Hybrid Assistive Limb)による歩行リハビリテーションを導入している医療機関は全国的にもまだ少なく、当院では筋萎縮性側索硬化症(ALS)の他、筋ジストロフィー、球脊髄性筋萎縮症、シャルコー・マリー・トゥース病、封入体筋炎など、計8疾患に対して適応しています。
注1* JCS(Japan Coma Scale:意識障害のレベル) ※0:意識障害なし
■Ⅲ群:刺激しても覚醒しない
300:まったく動かない
200:手足を少し動かしたり顔をしかめたりする(除脳硬直を含む)
100:払いのける動作をする
■Ⅱ群:刺激すると覚醒する
30:かろうじて開眼する
20:痛み刺激で開眼する
10:呼びかけで容易に開眼する
■Ⅰ群:覚醒している
3:名前、生年月日が言えない
2:見当識障害あり
1:清明とはいえない
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇各診療科別に患者数の多いDPC14桁分類についてDPCコード、名称、患者数、自院の平均在院日数、全国の平均在院日数、転院率、平均年齢を集計しています。
◇転院数10症例未満の症例は、転院率を非公開としています。
【解説】
脳神経内科は神経疾患全般を対象として診療を行っています。急性期の疾患としては、脳卒中・てんかん重積・神経感染症を扱っており、亜急性から慢性疾患として、重症筋無力症・多発性硬化症・神経変性疾患(パーキンソン病・脊髄小脳変性症)・認知症疾患など幅広く診療しています。栃木県では脳卒中の発症数が多いため、当院では脳卒中(脳出血、脳梗塞、一過性脳虚血発作、くも膜下出血)の診断および治療に特に力をいれています。24時間365日対応可能な血栓溶解療法(t-PAの投与)の体制を整えており、迅速な治療が可能です。
患者数別にみると、最も多いのは、脳梗塞に対してSPECT(単一光子放射線型コンピューター断層撮影)装置を使用し、適切な治療を行っている患者さんです。脳梗塞には、血栓性、塞栓性、血行力学性などのタイプがあり、発症からの時間経過により、治療法が異なります。
2番目に多いのは、脳梗塞に対して脳保護薬であるエダラボンを使用し、治療を行う患者さんです。
3番目に多いのは、脳梗塞に対してリハビリテーションなどを中心に治療を行う患者さんです。
4番目に多いのは、JCS10(注1*)未満の意識障害を伴う非外傷性の脳出血の患者さんです。
5番目に多いのは、てんかんに対して抗てんかん薬などを使用し、治療を行う患者さんです。
また、当院では筋萎縮性側索硬化症(ALS)の患者さんに対して、HAL(Hybrid Assistive Limb)という歩行支援ロボットを用いたリハビリテーションを組み合わせた治療を行っています。HAL(Hybrid Assistive Limb)による歩行リハビリテーションを導入している医療機関は全国的にもまだ少なく、当院では筋萎縮性側索硬化症(ALS)の他、筋ジストロフィー、球脊髄性筋萎縮症、シャルコー・マリー・トゥース病、封入体筋炎など、計8疾患に対して適応しています。
注1* JCS(Japan Coma Scale:意識障害のレベル) ※0:意識障害なし
■Ⅲ群:刺激しても覚醒しない
300:まったく動かない
200:手足を少し動かしたり顔をしかめたりする(除脳硬直を含む)
100:払いのける動作をする
■Ⅱ群:刺激すると覚醒する
30:かろうじて開眼する
20:痛み刺激で開眼する
10:呼びかけで容易に開眼する
■Ⅰ群:覚醒している
3:名前、生年月日が言えない
2:見当識障害あり
1:清明とはいえない
腎臓内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110280xx9901xx | 慢性腎不全 血液透析あり | 58 | 13.78 | 13.75 | ー | 68.47 | |
| 110280xx991xxx | 慢性腎不全 腎生検あり | 31 | 8.03 | 6.01 | ー | 56.45 | |
| 110280xx9900xx | 慢性腎不全 | 26 | 8.15 | 11.35 | ー | 8.15 | |
| 110280xx02x1xx | 慢性腎不全 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)等あり 血液透析あり | 20 | 37.05 | 33.81 | ー | 62.55 | |
| 110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし | 18 | 20.28 | 19.53 | ー | 67.28 |
【集計方法と定義】
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇各診療科別に患者数の多いDPC14桁分類についてDPCコード、名称、患者数、自院の平均在院日数、全国の平均在院日数、転院率、平均年齢を集計しています。
◇転院数10症例未満の症例は、転院率を非公開としています。
【解説】
腎臓内科では、慢性腎臓疾患(CKD)や急性腎障害(AKI)、さらにさまざまな水分・電解質の異常に対する診断と治療を行っています。高齢化の進行に伴い、腎臓病を発症する方が増えており、それに伴って当科を受診する患者さんも増加しております。
患者数別にみると、最も多いのは慢性腎不全に対して血液透析導入を行う患者さんです。慢性腎不全が悪化したり、尿毒症・肺水腫・急性呼吸不全などの合併症を起こし緊急入院されるケースが多く見られます。
2番目に多いのは、腎不全や慢性腎炎に対して、経皮的腎生検を行う患者さんです。
3番目に多いのは、慢性腎不全の患者さんです。慢性腎不全に対し透析治療を行ったり、IgA腎症などに対し薬物療法などの治療を行う方が含まれます。
4番目に多いのは、慢性腎不全に対して、内シャント設置術と血液透析を行う患者さんです。
5番目に多いのは、ネフローゼ症候群に対し薬物療法などの治療を行う患者さんです。
慢性腎不全は、何らかの原因によって腎機能が障害され、体内の水分や電解質のバランスが保てなくなった状態が長期間にわたって進行したものです。腎機能の低下をできる限り抑えるためには、適切な管理が必要であり、食事療法を含めた合併症予防のための教育も重要です。症状が進行した場合には、血液浄化療法(血液透析など)が必要となります。
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇各診療科別に患者数の多いDPC14桁分類についてDPCコード、名称、患者数、自院の平均在院日数、全国の平均在院日数、転院率、平均年齢を集計しています。
◇転院数10症例未満の症例は、転院率を非公開としています。
【解説】
腎臓内科では、慢性腎臓疾患(CKD)や急性腎障害(AKI)、さらにさまざまな水分・電解質の異常に対する診断と治療を行っています。高齢化の進行に伴い、腎臓病を発症する方が増えており、それに伴って当科を受診する患者さんも増加しております。
患者数別にみると、最も多いのは慢性腎不全に対して血液透析導入を行う患者さんです。慢性腎不全が悪化したり、尿毒症・肺水腫・急性呼吸不全などの合併症を起こし緊急入院されるケースが多く見られます。
2番目に多いのは、腎不全や慢性腎炎に対して、経皮的腎生検を行う患者さんです。
3番目に多いのは、慢性腎不全の患者さんです。慢性腎不全に対し透析治療を行ったり、IgA腎症などに対し薬物療法などの治療を行う方が含まれます。
4番目に多いのは、慢性腎不全に対して、内シャント設置術と血液透析を行う患者さんです。
5番目に多いのは、ネフローゼ症候群に対し薬物療法などの治療を行う患者さんです。
慢性腎不全は、何らかの原因によって腎機能が障害され、体内の水分や電解質のバランスが保てなくなった状態が長期間にわたって進行したものです。腎機能の低下をできる限り抑えるためには、適切な管理が必要であり、食事療法を含めた合併症予防のための教育も重要です。症状が進行した場合には、血液浄化療法(血液透析など)が必要となります。
糖尿病・内分泌内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) インスリン療法あり | 25 | 11.96 | 13.77 | ー | 64.28 | |
| 100180xx99000x | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし | 23 | 3.78 | 5.35 | ー | 53.96 | |
| 100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 | 17 | 16.24 | 13.07 | ー | 51.94 | |
| 10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 なし | 16 | 10.13 | 10.46 | ー | 61.19 | |
| 100180xx991xxx | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 副腎静脈サンプリングあり | 15 | 3.07 | 3.88 | ー | 52.40 |
【集計方法と定義】
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇各診療科別に患者数の多いDPC14桁分類についてDPCコード、名称、患者数、自院の平均在院日数、全国の平均在院日数、転院率、平均年齢を集計しています。
◇転院数10症例未満の症例は、転院率を非公開としています。
【解説】
糖尿病・内分泌内科では、糖尿病・脂質異常症などの代謝疾患に加え、甲状腺疾患、脳下垂体、副腎疾患などの内分泌疾患を対象に診療を行っています。
患者数別にみると、最も多いのは、2型糖尿病に対してインスリン製剤による注射薬を用いた教育入院を行う患者さんです。この教育入院では、インスリンの自己注射手技の指導をはじめ、栄養指導や運動指導を通して糖尿病への理解を深めていただき、血糖コントロールの改善を目指しています。
2番目に多いのは、クッシング症候群や原発性アルドステロン症など、副腎皮質機能亢進症の患者さんです。これらの疾患に対しては、内分泌負荷試験などの精密検査を行い、診断とや治療を進めています。
3番目に多いのは、糖尿病性ケトアシドーシスの患者さんです。これは糖尿病の急性合併症のひとつであり、緊急性の高い治療が必要となるため、迅速な対応が求められます。
4番目に多いのは、2型糖尿病に対して教育入院を行う患者さんです。教育入院を通じて糖尿病の理解を深め、栄養指導や運動指導に関する指導を受けながら血糖コントロールの改善を図るケースです。インスリン治療を行わない場合でも、生活習慣の見直しを中心とした支援が行われています。
5番目に多いのは、クッシング症候群や原発性アルドステロン症など、副腎皮質機能亢進症の患者さんで、副腎静脈サンプリングなどの精密検査を通じて診断を確定し、適切な治療を行っています。
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇各診療科別に患者数の多いDPC14桁分類についてDPCコード、名称、患者数、自院の平均在院日数、全国の平均在院日数、転院率、平均年齢を集計しています。
◇転院数10症例未満の症例は、転院率を非公開としています。
【解説】
糖尿病・内分泌内科では、糖尿病・脂質異常症などの代謝疾患に加え、甲状腺疾患、脳下垂体、副腎疾患などの内分泌疾患を対象に診療を行っています。
患者数別にみると、最も多いのは、2型糖尿病に対してインスリン製剤による注射薬を用いた教育入院を行う患者さんです。この教育入院では、インスリンの自己注射手技の指導をはじめ、栄養指導や運動指導を通して糖尿病への理解を深めていただき、血糖コントロールの改善を目指しています。
2番目に多いのは、クッシング症候群や原発性アルドステロン症など、副腎皮質機能亢進症の患者さんです。これらの疾患に対しては、内分泌負荷試験などの精密検査を行い、診断とや治療を進めています。
3番目に多いのは、糖尿病性ケトアシドーシスの患者さんです。これは糖尿病の急性合併症のひとつであり、緊急性の高い治療が必要となるため、迅速な対応が求められます。
4番目に多いのは、2型糖尿病に対して教育入院を行う患者さんです。教育入院を通じて糖尿病の理解を深め、栄養指導や運動指導に関する指導を受けながら血糖コントロールの改善を図るケースです。インスリン治療を行わない場合でも、生活習慣の見直しを中心とした支援が行われています。
5番目に多いのは、クッシング症候群や原発性アルドステロン症など、副腎皮質機能亢進症の患者さんで、副腎静脈サンプリングなどの精密検査を通じて診断を確定し、適切な治療を行っています。
外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術あり | 198 | 4.20 | 4.54 | ー | 70.30 | |
| 060335xx0200xx | 胆のう炎・胆のうポリープ等 腹腔鏡下胆のう摘出術等あり | 105 | 5.66 | 7.05 | ー | 61.92 | |
| 090010xx010xxx | 乳癌 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩部郭清を伴うもの)等あり | 88 | 9.22 | 9.77 | ー | 66.07 | |
| 060035xx0100xx | 結腸癌・虫垂癌 悪性腫瘍切除術等あり | 78 | 11.05 | 14.81 | ー | 71.82 | |
| 090010xx02xxxx | 乳癌 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)等あり | 63 | 5.70 | 5.50 | ー | 62.84 |
【集計方法と定義】
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇各診療科別に患者数の多いDPC14桁分類についてDPCコード、名称、患者数、自院の平均在院日数、全国の平均在院日数、転院率、平均年齢を集計しています。
◇転院数10症例未満のため、転院率を非公開としています。
【解説】
一般外科では、消化器系と乳腺を含むさまざまな疾患の診療を行っています。主な対象は、食道・胃・小腸・大腸・肝臓・膵臓・胆のうなどの消化器系に関する良性および悪性疾患、さらに成人および小児のヘルニアなどです。また、当院はがん診療連携拠点病院として、多くの悪性腫瘍に対する手術や化学療法などの先進医療にも積極的に取り組んでいます。
患者数別にみると、最も多いのは、15歳以上の鼠径ヘルニアに対して手術を行う患者さんです。ヘルニア手術には、前方アプローチ法と腹腔鏡下手術の両方を導入しており、平均在院日数は4.20日と短くなっています。
2番目に多いのは、胆石性胆のう炎や胆のうポリープに対して、腹腔鏡下で胆のう摘出術を行う患者さんです。急性胆のう炎を併発して緊急入院となるケースにも多数対応しているため、平均在院日数は5.66日となっています。
3番目に多いのは、乳癌に対して乳腺切除手術を行う患者さんです。この手術では腋窩部のリンパ節を切除する腋窩郭清を伴う場合が多く、がんの進行度に応じた適切な治療を行っています。クリニカルパスを適用しているため、平均在院日数は9.22日と比較的短くなっています。
4番目に多いのは、結腸癌や虫垂癌に対して悪性腫瘍の切除手術を行う患者さんです。当院では、これらの手術のうち8割以上を腹腔鏡下で実施しています。
5番目に多いのは、乳癌に対して腋窩部の郭清を伴わない乳房部分切除を行う患者さんです。クリニカルパスを適用しているため、平均在院日数は5.70日と短縮されています。
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇各診療科別に患者数の多いDPC14桁分類についてDPCコード、名称、患者数、自院の平均在院日数、全国の平均在院日数、転院率、平均年齢を集計しています。
◇転院数10症例未満のため、転院率を非公開としています。
【解説】
一般外科では、消化器系と乳腺を含むさまざまな疾患の診療を行っています。主な対象は、食道・胃・小腸・大腸・肝臓・膵臓・胆のうなどの消化器系に関する良性および悪性疾患、さらに成人および小児のヘルニアなどです。また、当院はがん診療連携拠点病院として、多くの悪性腫瘍に対する手術や化学療法などの先進医療にも積極的に取り組んでいます。
患者数別にみると、最も多いのは、15歳以上の鼠径ヘルニアに対して手術を行う患者さんです。ヘルニア手術には、前方アプローチ法と腹腔鏡下手術の両方を導入しており、平均在院日数は4.20日と短くなっています。
2番目に多いのは、胆石性胆のう炎や胆のうポリープに対して、腹腔鏡下で胆のう摘出術を行う患者さんです。急性胆のう炎を併発して緊急入院となるケースにも多数対応しているため、平均在院日数は5.66日となっています。
3番目に多いのは、乳癌に対して乳腺切除手術を行う患者さんです。この手術では腋窩部のリンパ節を切除する腋窩郭清を伴う場合が多く、がんの進行度に応じた適切な治療を行っています。クリニカルパスを適用しているため、平均在院日数は9.22日と比較的短くなっています。
4番目に多いのは、結腸癌や虫垂癌に対して悪性腫瘍の切除手術を行う患者さんです。当院では、これらの手術のうち8割以上を腹腔鏡下で実施しています。
5番目に多いのは、乳癌に対して腋窩部の郭清を伴わない乳房部分切除を行う患者さんです。クリニカルパスを適用しているため、平均在院日数は5.70日と短縮されています。
呼吸器外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040040xx02x0xx | 肺癌 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術等あり | 95 | 8.94 | 9.82 | ー | 68.86 | |
| 040040xx9910xx | 肺癌 気管支生検等あり | 22 | 2.00 | 3.03 | ー | 70.27 | |
| 040010xx01x0xx | 縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等あり | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 040200xx01x00x | 自然気胸・続発性気胸 胸腔鏡下肺切除術等あり | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 040010xx99x0xx | 縦隔・胸膜の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし | ー | ー | ー | ー | ー |
【集計方法と定義】
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇各診療科別に患者数の多いDPC14桁分類についてDPCコード、名称、患者数、自院の平均在院日数、全国の平均在院日数、転院率、平均年齢を集計しています。
◇3位以下のDPCコードについては、患者数10症例未満のため、各項目を非公開としています。
◇転院数10症例未満の症例は、転院率を非公開としています。
【解説】
呼吸器外科では、呼吸器内科と連携しながら、肺・気管・気管支の疾患をはじめ、気胸、縦隔の疾患、胸壁や横隔膜の疾患、さらに胸部外傷など、呼吸器全般にわたる診療を行っています。
患者数別にみると、1番目に多いのは、肺癌に対して悪性腫瘍切除術を行う患者さんです。肺癌手術の約9割は、ロボット支援によるダヴィンチ手術、胸腔鏡下手術または胸腔鏡補助下手術(VATS)といった、小さな傷で行う低侵襲手術によって実施されています。クリニカルパスを適用しているため、平均在院日数は8.94日と短く、効率的な治療が可能となっています。
2番目に多いのは、肺癌(疑いも含む)の確定診断を目的として、気管支鏡などによる生検を行う患者さんです。これらは検査入院で対応されるため、平均在院日数は2.00日と短くなっています。
3番目に多いのは、縦隔・胸膜・胸腺に発生した悪性腫瘍手術を行う患者さんです。主に、ロボット支援によるダヴィンチ手術を行っています。低侵襲で精度の高い治療が可能となっているのが特徴です。
4番目に多いのは、自然気胸や続発性気胸に対して胸腔鏡下肺切除術等の手術を行う患者さんです。再発を繰り返す症例や、肺からの空気漏れが持続する難治性の症例に対して、胸腔鏡下で肺切除術を行います。
5番目に多いには、縦隔・胸膜・胸腺の悪性腫瘍に対して超音波気管支鏡下穿刺吸引生検法(EBUS-TBNA)を行う患者さんです。この検査は、腫瘍の性質や広がりを詳しく調べるために行われ、診断精度の向上に貢献しています。
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇各診療科別に患者数の多いDPC14桁分類についてDPCコード、名称、患者数、自院の平均在院日数、全国の平均在院日数、転院率、平均年齢を集計しています。
◇3位以下のDPCコードについては、患者数10症例未満のため、各項目を非公開としています。
◇転院数10症例未満の症例は、転院率を非公開としています。
【解説】
呼吸器外科では、呼吸器内科と連携しながら、肺・気管・気管支の疾患をはじめ、気胸、縦隔の疾患、胸壁や横隔膜の疾患、さらに胸部外傷など、呼吸器全般にわたる診療を行っています。
患者数別にみると、1番目に多いのは、肺癌に対して悪性腫瘍切除術を行う患者さんです。肺癌手術の約9割は、ロボット支援によるダヴィンチ手術、胸腔鏡下手術または胸腔鏡補助下手術(VATS)といった、小さな傷で行う低侵襲手術によって実施されています。クリニカルパスを適用しているため、平均在院日数は8.94日と短く、効率的な治療が可能となっています。
2番目に多いのは、肺癌(疑いも含む)の確定診断を目的として、気管支鏡などによる生検を行う患者さんです。これらは検査入院で対応されるため、平均在院日数は2.00日と短くなっています。
3番目に多いのは、縦隔・胸膜・胸腺に発生した悪性腫瘍手術を行う患者さんです。主に、ロボット支援によるダヴィンチ手術を行っています。低侵襲で精度の高い治療が可能となっているのが特徴です。
4番目に多いのは、自然気胸や続発性気胸に対して胸腔鏡下肺切除術等の手術を行う患者さんです。再発を繰り返す症例や、肺からの空気漏れが持続する難治性の症例に対して、胸腔鏡下で肺切除術を行います。
5番目に多いには、縦隔・胸膜・胸腺の悪性腫瘍に対して超音波気管支鏡下穿刺吸引生検法(EBUS-TBNA)を行う患者さんです。この検査は、腫瘍の性質や広がりを詳しく調べるために行われ、診断精度の向上に貢献しています。
整形外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07040xxx01xxxx | 股関節症(変形性を含む。) 人工関節置換術等あり | 129 | 15.63 | 18.76 | 48.06% | 66.40 | |
| 160800xx02xxxx | 大腿骨近位端骨折 人工骨頭挿入術等あり | 72 | 21.63 | 25.29 | 68.06% | 77.94 | |
| 070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節置換術等あり | 54 | 17.81 | 21.38 | 55.56% | 75.80 | |
| 070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 52 | 16.46 | 15.41 | ー | 70.83 | |
| 160760xx01xxxx | 前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等 | 38 | 3.97 | 5.95 | ー | 49.87 |
【集計方法と定義】
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇各診療科別に患者数の多いDPC14桁分類についてDPCコード、名称、患者数、自院の平均在院日数、全国の平均在院日数、転院率、平均年齢を集計しています。
◇交通事故や労災などによる保険外診療については、集計から除外しています。
◇転院数10症例未満の症例は、転院率を非公開としています。
【解説】
整形外科は、骨・関節・筋肉・脊椎脊髄・神経など、体を動かすために必要な「運動器」に関する病気やけがを幅広く診療しています。安全で確実な治療を行うことを基本方針としており、その中で最新の医学的知識や技術を積極的に導入しています。診療の対象となる分野は多岐にわたっており、脊椎や脊の疾患に対する外科的治療、人工関節手術を中心とした関節外科、肩や肘などの上肢の外科、骨折・脱臼などの外傷外科が含まれます。これらの分野については、それぞれ専門医が診療を担当しています。
患者数別にみると、最も多いのは、変形性股関節症に対して人工関節置換術などを行う患者さんです。変形性股関節症は、股関節の軟骨がすり減ることで痛みや動きにくさが生じる病気であり、人工関節置換術などの手術が多く行われています。手術後には継続的なリハビリが必要となるため、他の病院へ転院される方が多く、転院率は48.06%となっています。
2番目に多いのは、大腿骨近位部骨折に対して手術を行う患者さんです。大腿骨近位部の骨折(太ももの付け根に近い部分の骨折)は転倒によって起こることが多く、高齢者に多く見られます。治療には、人工骨頭挿入術や人工関節置換術、髄内釘を用いた骨折手術などが行われます。平均年齢は77.94歳と高く、術後のリハビリを目的として他の病院へ転院される方が多く、転院率は68.06%です。
3番目に多いのは、変形性膝関節症に対して人工関節置換術を行う患者さんです。変形性膝関節症は、膝関節の軟骨がすり減ることで痛みや歩行障害が生じる病気であり、人工関節置換術などの手術が行われています。
4番目に多いのは、腰部脊柱管狭窄症や腰椎すべり症に対して脊椎固定術や脊椎切除術を行う患者さんです。脊柱管狭窄症は、背骨の中を通る神経の通り道である脊柱管が狭くなり、神経が圧迫されることで症状が現れる病気です。特に腰部の狭窄では、足の痛みやしびれなどの症状が出ることが多く、治療には脊椎固定術や脊椎切除術などの外科的手術を行われます。
5番目に多いのは、前腕(橈骨や尺骨)または手関節周辺の骨折に対して骨折観血的手術などを行う患者さんです。手関節周辺の骨折は、運動時の転倒や転落によって起こることが多く、壮年期から初老期の患者さんが多いため、平均年齢は比較的低くなっています。
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇各診療科別に患者数の多いDPC14桁分類についてDPCコード、名称、患者数、自院の平均在院日数、全国の平均在院日数、転院率、平均年齢を集計しています。
◇交通事故や労災などによる保険外診療については、集計から除外しています。
◇転院数10症例未満の症例は、転院率を非公開としています。
【解説】
整形外科は、骨・関節・筋肉・脊椎脊髄・神経など、体を動かすために必要な「運動器」に関する病気やけがを幅広く診療しています。安全で確実な治療を行うことを基本方針としており、その中で最新の医学的知識や技術を積極的に導入しています。診療の対象となる分野は多岐にわたっており、脊椎や脊の疾患に対する外科的治療、人工関節手術を中心とした関節外科、肩や肘などの上肢の外科、骨折・脱臼などの外傷外科が含まれます。これらの分野については、それぞれ専門医が診療を担当しています。
患者数別にみると、最も多いのは、変形性股関節症に対して人工関節置換術などを行う患者さんです。変形性股関節症は、股関節の軟骨がすり減ることで痛みや動きにくさが生じる病気であり、人工関節置換術などの手術が多く行われています。手術後には継続的なリハビリが必要となるため、他の病院へ転院される方が多く、転院率は48.06%となっています。
2番目に多いのは、大腿骨近位部骨折に対して手術を行う患者さんです。大腿骨近位部の骨折(太ももの付け根に近い部分の骨折)は転倒によって起こることが多く、高齢者に多く見られます。治療には、人工骨頭挿入術や人工関節置換術、髄内釘を用いた骨折手術などが行われます。平均年齢は77.94歳と高く、術後のリハビリを目的として他の病院へ転院される方が多く、転院率は68.06%です。
3番目に多いのは、変形性膝関節症に対して人工関節置換術を行う患者さんです。変形性膝関節症は、膝関節の軟骨がすり減ることで痛みや歩行障害が生じる病気であり、人工関節置換術などの手術が行われています。
4番目に多いのは、腰部脊柱管狭窄症や腰椎すべり症に対して脊椎固定術や脊椎切除術を行う患者さんです。脊柱管狭窄症は、背骨の中を通る神経の通り道である脊柱管が狭くなり、神経が圧迫されることで症状が現れる病気です。特に腰部の狭窄では、足の痛みやしびれなどの症状が出ることが多く、治療には脊椎固定術や脊椎切除術などの外科的手術を行われます。
5番目に多いのは、前腕(橈骨や尺骨)または手関節周辺の骨折に対して骨折観血的手術などを行う患者さんです。手関節周辺の骨折は、運動時の転倒や転落によって起こることが多く、壮年期から初老期の患者さんが多いため、平均年齢は比較的低くなっています。
脳神経外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160100xx97x00x | 急性硬膜下血腫、脳挫傷、外傷性くも膜下出血 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄等あり | 38 | 15.63 | 9.83 | ー | 78.89 | |
| 010030xx991xxx | 未破裂脳動脈瘤 血管造影検査あり | 31 | 2.13 | 2.86 | ー | 59.97 | |
| 010070xx9910xx | 内頚動脈狭窄症、中大脳動脈狭窄症 造影剤注入(動脈造影カテーテル法)(選択的血管造影) | 16 | 2.13 | 3.23 | ー | 65.06 | |
| 160100xx0111xx | 外傷性急性硬膜下血腫、脳挫傷、外傷性くも膜下出血 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)あり | 15 | 69.00 | 63.24 | 93.33% | 69.33 | |
| 010040x101x1xx | 脳出血(JCS10以上) 脳血管内手術+脳動静脈奇形摘出術等 手術・処置等2 あり | 15 | 55.13 | 39.52 | 73.33% | 62.93 |
【集計方法と定義】
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇各診療科別に患者数の多いDPC14桁分類についてDPCコード、名称、患者数、自院の平均在院日数、全国の平均在院日数、転院率、平均年齢を集計しています。
◇交通事故や労災などによる保険外診療については、集計から除外しています。
◇転院数10症例未満の症例は、転院率を非公開としています。
【解説】
脳神経外科は、県内外の大学と積極的に交流を図り、より質の高い医療の提供を目指して、先進的な治療も積極的に取り入れています。対象となる疾患は、脳腫瘍(髄膜腫、頭蓋底腫瘍、下垂体腫瘍、聴神経腫瘍、神経膠腫など)、脳動脈瘤(くも膜下出血、未破裂動脈瘤)、脳動静脈奇形、頭部外傷、脳梗塞(バイパス手術、頚動脈血栓内膜剥離術など)、機能的疾患(三叉神経痛、顔面けいれん)など、脳神経外科領域全般にわたります。また、脳動脈瘤、脳虚血性疾患に対する血管内治療、神経内視鏡を用いた低侵襲治療に力を入れています。
患者数別にみると、最も多いのは、外傷性硬膜下血腫(急性または慢性)に対して慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術(注1*)を行う患者さんです。慢性硬膜下血腫は、軽度の頭部外傷から3週間以上経過した後、硬膜下に徐々に血液がたまっていく病気で、血腫が大きくなるにつれて圧迫症状が現れます。高齢者が転倒した際に発症することが多く、歩行障害や片麻痺、認知症のような症状で受診し、診断されるケースが多く見られます。平均年齢は78.89歳と高齢です。
2番目に多いのは、未破裂脳動脈瘤に対して血管造影検査を行う患者さんです。クリニカルパスを適用しているため、平均在院日数が2.13日と短くなっています。
3番目に多いのは、内頚動脈狭窄症、中大脳動脈狭窄症に対して血管造影検査を行う患者さんです。クリニカルパスを適用しているため、平均在院日数が2.13日です。
4番目に多いのは、外傷性の急性硬膜下血腫に対して、開頭による頭蓋内血腫除去術(硬膜下のもの)を行う患者さんです。
5番目に多いのは、JCS(注2*)10以上の被殻出血などに対して、頭蓋内血腫除去術などの処置を行う患者さんです。退院後も継続的なリハビリが必要となるため、転院される方も多くいます。
注1* 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 硬膜下血腫に対して頭蓋骨に穴をあけ、血腫を抽出・洗浄し、ドレナージを行う手術
注2* JCS(Japan Coma Scale:意識障害のレベル) ※0:意識障害なし
■Ⅲ群:刺激しても覚醒しない
300:まったく動かない
200:手足を少し動かしたり顔をしかめたりする(除脳硬直を含む)
100:払いのける動作をする
■Ⅱ群:刺激すると覚醒する
30:かろうじて開眼する
20:痛み刺激で開眼する
10:呼びかけで容易に開眼する
■Ⅰ群:覚醒している
3:名前、生年月日が言えない
2:見当識障害あり
1:清明とはいえない
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇各診療科別に患者数の多いDPC14桁分類についてDPCコード、名称、患者数、自院の平均在院日数、全国の平均在院日数、転院率、平均年齢を集計しています。
◇交通事故や労災などによる保険外診療については、集計から除外しています。
◇転院数10症例未満の症例は、転院率を非公開としています。
【解説】
脳神経外科は、県内外の大学と積極的に交流を図り、より質の高い医療の提供を目指して、先進的な治療も積極的に取り入れています。対象となる疾患は、脳腫瘍(髄膜腫、頭蓋底腫瘍、下垂体腫瘍、聴神経腫瘍、神経膠腫など)、脳動脈瘤(くも膜下出血、未破裂動脈瘤)、脳動静脈奇形、頭部外傷、脳梗塞(バイパス手術、頚動脈血栓内膜剥離術など)、機能的疾患(三叉神経痛、顔面けいれん)など、脳神経外科領域全般にわたります。また、脳動脈瘤、脳虚血性疾患に対する血管内治療、神経内視鏡を用いた低侵襲治療に力を入れています。
患者数別にみると、最も多いのは、外傷性硬膜下血腫(急性または慢性)に対して慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術(注1*)を行う患者さんです。慢性硬膜下血腫は、軽度の頭部外傷から3週間以上経過した後、硬膜下に徐々に血液がたまっていく病気で、血腫が大きくなるにつれて圧迫症状が現れます。高齢者が転倒した際に発症することが多く、歩行障害や片麻痺、認知症のような症状で受診し、診断されるケースが多く見られます。平均年齢は78.89歳と高齢です。
2番目に多いのは、未破裂脳動脈瘤に対して血管造影検査を行う患者さんです。クリニカルパスを適用しているため、平均在院日数が2.13日と短くなっています。
3番目に多いのは、内頚動脈狭窄症、中大脳動脈狭窄症に対して血管造影検査を行う患者さんです。クリニカルパスを適用しているため、平均在院日数が2.13日です。
4番目に多いのは、外傷性の急性硬膜下血腫に対して、開頭による頭蓋内血腫除去術(硬膜下のもの)を行う患者さんです。
5番目に多いのは、JCS(注2*)10以上の被殻出血などに対して、頭蓋内血腫除去術などの処置を行う患者さんです。退院後も継続的なリハビリが必要となるため、転院される方も多くいます。
注1* 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 硬膜下血腫に対して頭蓋骨に穴をあけ、血腫を抽出・洗浄し、ドレナージを行う手術
注2* JCS(Japan Coma Scale:意識障害のレベル) ※0:意識障害なし
■Ⅲ群:刺激しても覚醒しない
300:まったく動かない
200:手足を少し動かしたり顔をしかめたりする(除脳硬直を含む)
100:払いのける動作をする
■Ⅱ群:刺激すると覚醒する
30:かろうじて開眼する
20:痛み刺激で開眼する
10:呼びかけで容易に開眼する
■Ⅰ群:覚醒している
3:名前、生年月日が言えない
2:見当識障害あり
1:清明とはいえない
形成外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等あり | 32 | 3.75 | 4.65 | ー | 58.84 | |
| 080007xx010xxx | 皮膚の良性腫瘍 皮膚、皮下腫瘍摘出術等あり | 28 | 2.96 | 3.77 | ー | 39.86 | |
| 160200xx020xxx | 顔面骨骨折(眼窩、胸骨、鼻骨等) 眼窩骨折観血的手術等あり | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 070520xx97xxxx | リンパ節、リンパ管の疾患 手術あり | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 070590xx97x0xx | 血管腫、リンパ管腫 手術あり 手術・処置等2 なし | ー | ー | ー | ー | ー |
【集計方法と定義】
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇各診療科別に患者数の多いDPC14桁分類についてDPCコード、名称、患者数、自院の平均在院日数、全国の平均在院日数、転院率、平均年齢を集計しています。
◇3位以下のDPCコードについては、患者数10症例未満のため、各項目を非公開としています。
◇転院数10症例未満の症例は、転院率を非公開としています。
【解説】
形成外科では、外傷(軟部組織損傷、顔面骨骨折、熱傷)をはじめ、体表に現れるの先天的な形態異常(口唇裂、耳介変形、多指症、合指症など)、皮膚や皮下にできる腫瘍などに対しての診療を行っています。手術の約8割は外来で局所麻酔による手術を行っておりますが、患者さんの状態や手術の内容によっては入院による手術も行っています。
患者数別にみると、最も多いのは、肩や背部などにできた良性の軟部腫瘍に対して摘出を行う患者さんです。
2番目に多いのは、良性皮膚腫瘍や良性皮下腫瘍(脂肪腫など)に対して切除術を行う患者さんです。平均在院日数は2.96日と短く、患者さんの負担も比較的軽いものとなっています。
3番目に多いのは、眼窩底骨折や頬骨骨折など、顔面の骨折に対して観血的手術(出血を伴う外科的処置)を行う患者さんです。これらの手術は、外見や機能の回復を目的として慎重に行われます。
4番目に多いのは、リンパ浮腫に対して、リンパ管吻合術を行う患者さんです。リンパの流れを改善するためにリンパ管同士をつなぎ合わせるもので、むくみの軽減や生活の質の向上を目指します。
5番目に多いのは、血管腫や巨大動静脈奇形に対して、血管摘出術を行う患者さんです。これらの疾患は見た目だけでなく、血流や周囲の組織に影響を及ぼすことがあるため、専門的な判断のもとで手術が行われます。
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇各診療科別に患者数の多いDPC14桁分類についてDPCコード、名称、患者数、自院の平均在院日数、全国の平均在院日数、転院率、平均年齢を集計しています。
◇3位以下のDPCコードについては、患者数10症例未満のため、各項目を非公開としています。
◇転院数10症例未満の症例は、転院率を非公開としています。
【解説】
形成外科では、外傷(軟部組織損傷、顔面骨骨折、熱傷)をはじめ、体表に現れるの先天的な形態異常(口唇裂、耳介変形、多指症、合指症など)、皮膚や皮下にできる腫瘍などに対しての診療を行っています。手術の約8割は外来で局所麻酔による手術を行っておりますが、患者さんの状態や手術の内容によっては入院による手術も行っています。
患者数別にみると、最も多いのは、肩や背部などにできた良性の軟部腫瘍に対して摘出を行う患者さんです。
2番目に多いのは、良性皮膚腫瘍や良性皮下腫瘍(脂肪腫など)に対して切除術を行う患者さんです。平均在院日数は2.96日と短く、患者さんの負担も比較的軽いものとなっています。
3番目に多いのは、眼窩底骨折や頬骨骨折など、顔面の骨折に対して観血的手術(出血を伴う外科的処置)を行う患者さんです。これらの手術は、外見や機能の回復を目的として慎重に行われます。
4番目に多いのは、リンパ浮腫に対して、リンパ管吻合術を行う患者さんです。リンパの流れを改善するためにリンパ管同士をつなぎ合わせるもので、むくみの軽減や生活の質の向上を目指します。
5番目に多いのは、血管腫や巨大動静脈奇形に対して、血管摘出術を行う患者さんです。これらの疾患は見た目だけでなく、血流や周囲の組織に影響を及ぼすことがあるため、専門的な判断のもとで手術が行われます。
心臓血管外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050163xx03x0xx | 胸部・腹部大動脈瘤 ステントグラフト内挿術等あり | 102 | 8.98 | 10.18 | ー | 77.04 | |
| 050210xx97000x | 房室ブロック、洞不全症候群、ペースメーカ電池消耗 ペースメーカー移植術等あり | 57 | 3.56 | 9.59 | ー | 78.00 | |
| 050080xx0101xx | 弁膜症 弁置換術(胸腔鏡下含む)等 中心静脈・人工呼吸あり | 43 | 16.67 | 20.84 | ー | 62.63 | |
| 050161xx01x1xx | 急性大動脈解離 オープンステントグラフト内挿術等 中心静脈・人工呼吸あり | 31 | 30.84 | 29.35 | 38.71% | 68.00 | |
| 050163xx01x1xx | 非破裂性大動脈瘤 オープンステントグラフト内挿術等 中心静脈・人工呼吸あり | 29 | 28.10 | 27.01 | ー | 74.38 |
【集計方法と定義】
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇各診療科別に患者数の多いDPC14桁分類についてDPCコード、名称、患者数、自院の平均在院日数、全国の平均在院日数、転院率、平均年齢を集計しています。
◇転院数10症例未満の症例は、転院率を非公開としています。
【解説】
心臓血管外科では、循環器内科・小児科・放射線科との綿密な連携しながら、さまざまな循環器疾患に対する治療を行っています。近年では、命を救うことはもちろん、患者さんの身体的負担をできるだけ軽減し、手術後の日常生活の質を高めることを目指した治療にも力を入れています。対象となる疾患は、心臓弁膜症や冠動脈疾患、心房中隔欠損症などの先天性心疾患、急性大動脈解離や胸部大動脈瘤などの大動脈疾患、閉塞性動脈硬化症などの末梢血管疾患、不整脈などの、多岐にわたります。
患者数別にみると、最も多いのは、胸部や腹部大動脈瘤に対してステントグラフト内挿術(注1* )を行う患者さんです。この手術は身体への負担が少ないため、高齢者や合併症を持つ患者さんにも適しており、平均年齢が77.04歳と高くなっています。
2番目に多いのは、房室ブロックや洞不全症候群などの不整脈に対して、新たにペースメーカーの植え込みむ、または既存の機器を交換する患者さんです。クリニカルパスを適用しているため、平均在院日数は3.56日と短く、効率的な治療が可能です。
3番目に多いのは、心臓弁膜症に対して弁置換術や弁形成術を行う患者さんです。これらの手術では、中心静脈注射や人工呼吸器を使用しながら、心機能の改善を図ります。
4番目に多いのは、急性大動解離に対して、オープンステントグラフト内挿術を行う患者さんです。緊急性の高い疾患であり、迅速かつ高度な外科的対応が求められます。
5番目に多いのは、非破裂性大動脈瘤に対して、大動脈瘤切除術やオープンステントグラフト内挿術を行う患者さんです。破裂のリスクを未然に防ぐため、計画的に手術を行うケースが多く見られます。
注1* ステントグラフト内挿術 大きく皮膚を切開することなく、ステントグラフトを用いた経カテーテル的血管内治療。大腿動脈切開部からガイドワイヤーを使用し、目標の動脈瘤の中枢と末梢側の健常部分にステントグラフトを拡張し留置する治療法。
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇各診療科別に患者数の多いDPC14桁分類についてDPCコード、名称、患者数、自院の平均在院日数、全国の平均在院日数、転院率、平均年齢を集計しています。
◇転院数10症例未満の症例は、転院率を非公開としています。
【解説】
心臓血管外科では、循環器内科・小児科・放射線科との綿密な連携しながら、さまざまな循環器疾患に対する治療を行っています。近年では、命を救うことはもちろん、患者さんの身体的負担をできるだけ軽減し、手術後の日常生活の質を高めることを目指した治療にも力を入れています。対象となる疾患は、心臓弁膜症や冠動脈疾患、心房中隔欠損症などの先天性心疾患、急性大動脈解離や胸部大動脈瘤などの大動脈疾患、閉塞性動脈硬化症などの末梢血管疾患、不整脈などの、多岐にわたります。
患者数別にみると、最も多いのは、胸部や腹部大動脈瘤に対してステントグラフト内挿術(注1* )を行う患者さんです。この手術は身体への負担が少ないため、高齢者や合併症を持つ患者さんにも適しており、平均年齢が77.04歳と高くなっています。
2番目に多いのは、房室ブロックや洞不全症候群などの不整脈に対して、新たにペースメーカーの植え込みむ、または既存の機器を交換する患者さんです。クリニカルパスを適用しているため、平均在院日数は3.56日と短く、効率的な治療が可能です。
3番目に多いのは、心臓弁膜症に対して弁置換術や弁形成術を行う患者さんです。これらの手術では、中心静脈注射や人工呼吸器を使用しながら、心機能の改善を図ります。
4番目に多いのは、急性大動解離に対して、オープンステントグラフト内挿術を行う患者さんです。緊急性の高い疾患であり、迅速かつ高度な外科的対応が求められます。
5番目に多いのは、非破裂性大動脈瘤に対して、大動脈瘤切除術やオープンステントグラフト内挿術を行う患者さんです。破裂のリスクを未然に防ぐため、計画的に手術を行うケースが多く見られます。
注1* ステントグラフト内挿術 大きく皮膚を切開することなく、ステントグラフトを用いた経カテーテル的血管内治療。大腿動脈切開部からガイドワイヤーを使用し、目標の動脈瘤の中枢と末梢側の健常部分にステントグラフトを拡張し留置する治療法。
小児科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、RSウイルス気管支炎 | 210 | 6.40 | 6.22 | ー | 1.04 | |
| 140010x199x1xx | 新生児疾患(出生時体重2500g以上) 中心静脈注射等あり | 157 | 7.15 | 10.60 | ー | 0.00 | |
| 150040xxxxx0xx | 熱性けいれん | 106 | 3.81 | 3.51 | ー | 2.08 | |
| 010230xx99x00x | てんかん | 103 | 4.63 | 6.89 | ー | 7.98 | |
| 040100xxxxx00x | 気管支喘息発作、小児喘息用気管支炎 | 102 | 6.75 | 6.38 | ー | 2.76 |
【集計方法と定義】
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇各診療科別に患者数の多いDPC14桁分類についてDPCコード、名称、患者数、自院の平均在院日数、全国の平均在院日数、転院率、平均年齢を集計しています。
◇転院数10症例未満の症例は、転院率を非公開としています。
【解説】
小児科では、先天性心疾患をはじめとして、急性期・慢性期を問わず、あらゆる疾患の患者ワンを受け入れています。新生児集中治療室(NICU)、小児循環器部、産科を統合し、特色のある二次周産期施設として「母子医療センター」を運営しており、周産期の段階から小児科医が積極的に診療に関与しています。
患者数別にみると、最も多いのは、急性気管支炎の患者さんです。その中でも、RSウイルスによる気管支炎んが約6割を占めており、乳幼児期に多く見られる疾患です。
2番目に多いのは、出生時体重2500g以上の新生児で、中心静脈注射などの処置を必要とする患者さんです。これらの新生児には、新生児黄疸、呼吸障害、哺乳不全などの症状がみられ、適切な管理と治療が行われています。
3番目に多いのは、熱性けいれんの患者さんです。熱性けいれんは、38度以上の発熱に伴って起こるけいれん発作であり、乳幼児期に多く発症するため、平均年齢は2.08歳と低くなっています。
4番目に多いのは、てんかんの患者さんです。中には基礎疾患を伴う難治てんかんの患者さんも多く、複数の薬剤を併用する治療や、長時間のビデオ脳波検査によって診断を行うなど、専門的な対応が求められています。
5番目に多いのは、気管支喘息発作や小児喘息様気管支炎の患者さんです。これらの疾患では、気道、特に気管支が一時的に狭くなり、咳や呼吸困難を引き起こすため、緊急入院となるケースが大半を占めます。喘息の原因に、アレルギー反応や風邪、インフルエンザ、RSウイルスなどの気道感染が関与しています。
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇各診療科別に患者数の多いDPC14桁分類についてDPCコード、名称、患者数、自院の平均在院日数、全国の平均在院日数、転院率、平均年齢を集計しています。
◇転院数10症例未満の症例は、転院率を非公開としています。
【解説】
小児科では、先天性心疾患をはじめとして、急性期・慢性期を問わず、あらゆる疾患の患者ワンを受け入れています。新生児集中治療室(NICU)、小児循環器部、産科を統合し、特色のある二次周産期施設として「母子医療センター」を運営しており、周産期の段階から小児科医が積極的に診療に関与しています。
患者数別にみると、最も多いのは、急性気管支炎の患者さんです。その中でも、RSウイルスによる気管支炎んが約6割を占めており、乳幼児期に多く見られる疾患です。
2番目に多いのは、出生時体重2500g以上の新生児で、中心静脈注射などの処置を必要とする患者さんです。これらの新生児には、新生児黄疸、呼吸障害、哺乳不全などの症状がみられ、適切な管理と治療が行われています。
3番目に多いのは、熱性けいれんの患者さんです。熱性けいれんは、38度以上の発熱に伴って起こるけいれん発作であり、乳幼児期に多く発症するため、平均年齢は2.08歳と低くなっています。
4番目に多いのは、てんかんの患者さんです。中には基礎疾患を伴う難治てんかんの患者さんも多く、複数の薬剤を併用する治療や、長時間のビデオ脳波検査によって診断を行うなど、専門的な対応が求められています。
5番目に多いのは、気管支喘息発作や小児喘息様気管支炎の患者さんです。これらの疾患では、気道、特に気管支が一時的に狭くなり、咳や呼吸困難を引き起こすため、緊急入院となるケースが大半を占めます。喘息の原因に、アレルギー反応や風邪、インフルエンザ、RSウイルスなどの気道感染が関与しています。
産婦人科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120180xx01xxxx | 既往帝王切開後妊娠 骨盤位等 帝王切開術等あり | 154 | 7.95 | 9.40 | ー | 34.55 | |
| 120060xx01xxxx | 子宮筋腫 子宮全摘術等あり | 122 | 7.15 | 9.20 | ー | 45.49 | |
| 120260x001xxxx | 胎児機能不全等の分娩の異常 帝王切開術等あり | 88 | 8.42 | 9.34 | ー | 32.44 | |
| 120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等あり | 65 | 8.31 | 9.74 | ー | 51.85 | |
| 12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等あり | 59 | 11.17 | 9.84 | ー | 58.68 |
【集計方法と定義】
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇各診療科別に患者数の多いDPC14桁分類についてDPCコード、名称、患者数、自院の平均在院日数、全国の平均在院日数、転院率、平均年齢を集計しています。
◇転院数10症例未満の症例は、転院率を非公開としています。
【解説】
産婦人科では、母子医療センターを有し、不妊症から周産期、婦人科の悪性腫瘍に至るまで、産婦人科領域のほとんどの疾患に対応しています。また、救命救急センターを併設していることから、地域の第三次救急を担う役割も果たしており、救急搬送や他の医療機関から紹介された患者さんも多く、常に緊急対応が可能な診療体制を整えています。
不妊症に関しては、生殖医療センターを併設し、合併症を有する症例にも対応可能です。また、内視鏡手術やロボット手術にも力を入れています。
患者数別にみると、最も多いのは、既往帝王切開後(以前に帝王切開をしたことがある)の妊娠や骨盤位(逆子)に対して帝王切開術を行う患者さんです。クリニカルパスを適用しているため、平均在院日数が7.95日と短く、効率的な入院・治療が可能となっています。
2番目に多いのは、子宮筋腫に対して子宮全摘術や子宮筋腫摘出術を行う患者さんです。子宮筋腫は主に30~40歳代の女性に多く見られ、手術時の平均年齢は45.49歳となっています。
3番目に多いのは、胎児機能不全(胎児仮死)や胎児回旋異常、前期破水など、分娩時に合併が生じた場合に緊急帝王切開術を行う患者さんです。母体と胎児の安全を守るために、迅速な判断と対応を心がけています。
4番目に多いのは、卵巣の良性腫瘍に対して開腹手術を行い、卵巣の部分切除や卵巣・卵管切除を行う患者さんです。腫瘍の大きさや位置に応じて、適切な術式が選択されます。
5番目に多いのは、子宮頸癌や子宮内膜癌などの婦人科悪性腫瘍に対して、子宮悪性腫瘍手術等を行う患者さんです。これらの手術では、がんの進行度や患者さんの全身状態に応じて、根治性と安全性の両立を目指した治療が行われています。症例に応じて、開腹術、内視鏡手術、ロボット手術等の術式を選択しています。
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇各診療科別に患者数の多いDPC14桁分類についてDPCコード、名称、患者数、自院の平均在院日数、全国の平均在院日数、転院率、平均年齢を集計しています。
◇転院数10症例未満の症例は、転院率を非公開としています。
【解説】
産婦人科では、母子医療センターを有し、不妊症から周産期、婦人科の悪性腫瘍に至るまで、産婦人科領域のほとんどの疾患に対応しています。また、救命救急センターを併設していることから、地域の第三次救急を担う役割も果たしており、救急搬送や他の医療機関から紹介された患者さんも多く、常に緊急対応が可能な診療体制を整えています。
不妊症に関しては、生殖医療センターを併設し、合併症を有する症例にも対応可能です。また、内視鏡手術やロボット手術にも力を入れています。
患者数別にみると、最も多いのは、既往帝王切開後(以前に帝王切開をしたことがある)の妊娠や骨盤位(逆子)に対して帝王切開術を行う患者さんです。クリニカルパスを適用しているため、平均在院日数が7.95日と短く、効率的な入院・治療が可能となっています。
2番目に多いのは、子宮筋腫に対して子宮全摘術や子宮筋腫摘出術を行う患者さんです。子宮筋腫は主に30~40歳代の女性に多く見られ、手術時の平均年齢は45.49歳となっています。
3番目に多いのは、胎児機能不全(胎児仮死)や胎児回旋異常、前期破水など、分娩時に合併が生じた場合に緊急帝王切開術を行う患者さんです。母体と胎児の安全を守るために、迅速な判断と対応を心がけています。
4番目に多いのは、卵巣の良性腫瘍に対して開腹手術を行い、卵巣の部分切除や卵巣・卵管切除を行う患者さんです。腫瘍の大きさや位置に応じて、適切な術式が選択されます。
5番目に多いのは、子宮頸癌や子宮内膜癌などの婦人科悪性腫瘍に対して、子宮悪性腫瘍手術等を行う患者さんです。これらの手術では、がんの進行度や患者さんの全身状態に応じて、根治性と安全性の両立を目指した治療が行われています。症例に応じて、開腹術、内視鏡手術、ロボット手術等の術式を選択しています。
耳鼻咽喉科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030230xxxxxxxx | 慢性扁桃炎 扁桃摘出術あり | 75 | 6.97 | 7.35 | ー | 32.60 | |
| 030150xx97xxxx | 耳下腺・鼻腔・咽頭などの良性腫瘍 摘出術あり | 55 | 6.00 | 6.68 | ー | 60.04 | |
| 100020xx010xxx | 甲状腺癌 甲状腺悪性腫瘍手術あり | 46 | 7.04 | 7.90 | ー | 54.02 | |
| 030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 43 | 6.23 | 5.84 | ー | 54.28 | |
| 030240xx01xx0x | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等あり | 41 | 6.51 | 7.65 | ー | 44.44 |
【集計方法と定義】
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇各診療科別に患者数の多いDPC14桁分類についてDPCコード、名称、患者数、自院の平均在院日数、全国の平均在院日数、転院率、平均年齢を集計しています。
【解説】
耳鼻咽喉科は、一般には「耳鼻咽喉科・頭頸部外科」と呼ばれ、頭頸部領域(耳・鼻・口腔・咽喉頭(のど)・唾液腺・頸部・甲状腺)の病気を専門としています。当院は地域基幹病院として、精密検査や専門治療が必要な患者さん、主に手術を必要とする患者さんを中心に診療を行っています。
患者数別にみると、最も多いのは、慢性扁桃炎に対して扁桃摘出術を行う患者さんです。
2番目に多いのは、耳下腺や鼻腔、咽頭などの良性腫瘍に対して腫瘍摘出術を行う患者さんです。
3番目に多いのは、甲状腺癌に対して悪性腫瘍手術を行う患者さんです。
4番目に多いのは、慢性副鼻腔炎に対して内視鏡下鼻・副鼻腔手術を行う患者さんです。
5番目に多いのは、扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎に対して扁桃周囲膿瘍切開術を行う患者さんです。
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇各診療科別に患者数の多いDPC14桁分類についてDPCコード、名称、患者数、自院の平均在院日数、全国の平均在院日数、転院率、平均年齢を集計しています。
【解説】
耳鼻咽喉科は、一般には「耳鼻咽喉科・頭頸部外科」と呼ばれ、頭頸部領域(耳・鼻・口腔・咽喉頭(のど)・唾液腺・頸部・甲状腺)の病気を専門としています。当院は地域基幹病院として、精密検査や専門治療が必要な患者さん、主に手術を必要とする患者さんを中心に診療を行っています。
患者数別にみると、最も多いのは、慢性扁桃炎に対して扁桃摘出術を行う患者さんです。
2番目に多いのは、耳下腺や鼻腔、咽頭などの良性腫瘍に対して腫瘍摘出術を行う患者さんです。
3番目に多いのは、甲状腺癌に対して悪性腫瘍手術を行う患者さんです。
4番目に多いのは、慢性副鼻腔炎に対して内視鏡下鼻・副鼻腔手術を行う患者さんです。
5番目に多いのは、扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎に対して扁桃周囲膿瘍切開術を行う患者さんです。
眼科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020110xx97xxx0 | 白内障 水晶体再建術等あり 片眼 | 601 | 2.76 | 2.49 | ー | 75.59 | |
| 020220xx97xxx0 | 緑内障 緑内障手術あり 片眼 | 29 | 3.14 | 4.52 | ー | 74.69 | |
| 020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 硝子体茎顕微鏡下離断術等あり 片眼 | 23 | 7.04 | 5.89 | ー | 59.26 | |
| 140100xxxxxxxx | 先天性睫毛内反症 | 20 | 3.00 | 3.23 | ー | 9.60 | |
| 020200xx9710xx | 網膜前膜・黄斑円孔 硝子体茎顕微鏡下離断術+水晶体再建術あり | 12 | 6.50 | 5.47 | ー | 69.33 |
【集計方法と定義】
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇各診療科別に患者数の多いDPC14桁分類についてDPCコード、名称、患者数、自院の平均在院日数、全国の平均在院日数、転院率、平均年齢を集計しています。
◇転院数10症例未満の症例は、転院率を非公開としています。
【解説】
眼科では、幅広い分野にわたる専門知識を活かし、最先端の医療機器を導入することで、患者さんの立場に寄り添った医療の提供に努めています。
診断群類に基づく患者数を見ると、最も多いのは白内障に対して水晶体再建術を行う患者さんです。当院では、すべての患者さんに入院していただき、原則として片眼ずつ手術を行っています。クリニカルパスを活用することで、平均在院日数は2.76日となっています。
2番目に多いのは、緑内障に対して緑内障手術を行う患者さんです。
3番目に多いのは、糖尿病性増殖性網膜症に対して手術(硝子体茎顕微鏡下離断術等)を行う患者さんです。
4番目に多いのは、先天性睫毛内反症に対して眼瞼内反症手術を行う患者さんです。
5番目に多いのは、網膜前膜・黄斑円孔に対して、硝子体茎顕微鏡下離断術と水晶体再建術を併用して手術を行う患者さんです。
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇各診療科別に患者数の多いDPC14桁分類についてDPCコード、名称、患者数、自院の平均在院日数、全国の平均在院日数、転院率、平均年齢を集計しています。
◇転院数10症例未満の症例は、転院率を非公開としています。
【解説】
眼科では、幅広い分野にわたる専門知識を活かし、最先端の医療機器を導入することで、患者さんの立場に寄り添った医療の提供に努めています。
診断群類に基づく患者数を見ると、最も多いのは白内障に対して水晶体再建術を行う患者さんです。当院では、すべての患者さんに入院していただき、原則として片眼ずつ手術を行っています。クリニカルパスを活用することで、平均在院日数は2.76日となっています。
2番目に多いのは、緑内障に対して緑内障手術を行う患者さんです。
3番目に多いのは、糖尿病性増殖性網膜症に対して手術(硝子体茎顕微鏡下離断術等)を行う患者さんです。
4番目に多いのは、先天性睫毛内反症に対して眼瞼内反症手術を行う患者さんです。
5番目に多いのは、網膜前膜・黄斑円孔に対して、硝子体茎顕微鏡下離断術と水晶体再建術を併用して手術を行う患者さんです。
泌尿器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110080xx991xxx | 前立腺癌 前立腺生検法あり | 254 | 2.44 | 2.45 | ー | 70.10 | |
| 110070xx03x0xx | 膀胱癌 経尿道的膀胱悪性腫瘍手術あり | 159 | 6.62 | 6.81 | ー | 72.32 | |
| 11012xxx02xx0x | 尿管結石・腎結石 経尿道的尿路結石除去術あり | 95 | 4.76 | 5.16 | ー | 60.88 | |
| 110080xx01xxxx | 前立腺癌 前立腺悪性腫瘍手術等あり | 78 | 10.41 | 11.11 | ー | 69.09 | |
| 110070xx99x20x | 膀胱癌 化学療法あり | 58 | 7.67 | 8.64 | ー | 73.38 |
【集計方法と定義】
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇各診療科別に患者数の多いDPC14桁分類についてDPCコード、名称、患者数、自院の平均在院日数、全国の平均在院日数、転院率、平均年齢を集計しています。
◇転院数10症例未満の症例は、転院率を非公開としています。
【解説】
泌尿器科では、泌尿器科疾患全般に対して、国内でもトップクラスの症例数を誇り、最先端の知見と高い技術を持って診療にあたっています。特にがん診療においては、腹腔鏡手術やロボット支援手術などの低侵襲手術、機能温存を重視した手術、再建手術、さらには最新の薬物療法まで幅広い治療法を揃えており、患者さん一人ひとりに合わせた最適な医療を提供しています。
患者数別にみると、最も多いのは、前立腺癌や前立腺癌疑いに対して、確定診断を目的として前立腺針生検法を行う患者さんです。クリニカルパスを適用しており、基本的には入院当日に生検を実施し、翌日に退院する流れとなっています。
2番目に多いのは、膀胱癌に対して経尿道的膀胱悪性腫瘍手術を行う患者さんです。クリニカルパスを適用しているため、平均在院日数が6.62日と短く、効率的な治療が可能です。
3番目に多いのは、尿管結石や腎結石に対してレーザーを用いた経尿道的尿路結石除去術を行う患者さんです。痛みや排尿障害の原因となる結石を、身体への負担を抑えながら安全に除去する治療法です。
4番目に多いのは、前立腺癌に対して前立腺悪性腫瘍摘出術を行う患者さんです。そのうち9割以上の方が、手術支援ロボット「ダヴィンチ」(注1* )用いたロボット支援手術を行っています。開腹手術と比べて傷口が小さく、身体への負担が少ないことに加え、入院期間の短縮や尿失禁の早期改善など、多くのメリットがあります。
5番目に多いのは、膀胱癌に対して化学療法を行う患者さんです。がんの進行度や患者さんの全身状態に応じて、適切な薬剤を選択し、効果的な治療を行っています。
注1* 手術支援ロボット「ダヴィンチ」 患者さんの体に1~2cmの小さな穴を数か所開け、そこへロボットアームや内視鏡を挿入します。術者は患者さんに触れずに、離れた場所から高画質で立体的な3D画像を見ながら、ハンドルやフットペダルを操作して手術を行います。
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇各診療科別に患者数の多いDPC14桁分類についてDPCコード、名称、患者数、自院の平均在院日数、全国の平均在院日数、転院率、平均年齢を集計しています。
◇転院数10症例未満の症例は、転院率を非公開としています。
【解説】
泌尿器科では、泌尿器科疾患全般に対して、国内でもトップクラスの症例数を誇り、最先端の知見と高い技術を持って診療にあたっています。特にがん診療においては、腹腔鏡手術やロボット支援手術などの低侵襲手術、機能温存を重視した手術、再建手術、さらには最新の薬物療法まで幅広い治療法を揃えており、患者さん一人ひとりに合わせた最適な医療を提供しています。
患者数別にみると、最も多いのは、前立腺癌や前立腺癌疑いに対して、確定診断を目的として前立腺針生検法を行う患者さんです。クリニカルパスを適用しており、基本的には入院当日に生検を実施し、翌日に退院する流れとなっています。
2番目に多いのは、膀胱癌に対して経尿道的膀胱悪性腫瘍手術を行う患者さんです。クリニカルパスを適用しているため、平均在院日数が6.62日と短く、効率的な治療が可能です。
3番目に多いのは、尿管結石や腎結石に対してレーザーを用いた経尿道的尿路結石除去術を行う患者さんです。痛みや排尿障害の原因となる結石を、身体への負担を抑えながら安全に除去する治療法です。
4番目に多いのは、前立腺癌に対して前立腺悪性腫瘍摘出術を行う患者さんです。そのうち9割以上の方が、手術支援ロボット「ダヴィンチ」(注1* )用いたロボット支援手術を行っています。開腹手術と比べて傷口が小さく、身体への負担が少ないことに加え、入院期間の短縮や尿失禁の早期改善など、多くのメリットがあります。
5番目に多いのは、膀胱癌に対して化学療法を行う患者さんです。がんの進行度や患者さんの全身状態に応じて、適切な薬剤を選択し、効果的な治療を行っています。
注1* 手術支援ロボット「ダヴィンチ」 患者さんの体に1~2cmの小さな穴を数か所開け、そこへロボットアームや内視鏡を挿入します。術者は患者さんに触れずに、離れた場所から高画質で立体的な3D画像を見ながら、ハンドルやフットペダルを操作して手術を行います。
救急・集中治療科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160100xx99x00x | 急性硬膜下血腫、脳挫傷、外傷性くも膜下出血 手術なし | 33 | 5.58 | 7.99 | ー | 41.33 | |
| 161070xxxxx00x | 薬物中毒 | 30 | 4.13 | 3.58 | ー | 30.60 | |
| 161060xx99x0xx | アナフィラキシーショック 手術なし 手術・処置等2 なし | 26 | 1.77 | 2.63 | ー | 39.65 | |
| 160100xx97x00x | 急性硬膜下血腫、脳挫傷、外傷性くも膜下出血 その他の手術あり | 16 | 11.06 | 9.83 | ー | 69.56 | |
| 160450xx99x10x | 閉鎖性外傷性気胸 持続的胸腔ドレナージ等あり | ー | ー | ー | ー | ー |
【集計方法と定義】
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇各診療科別に患者数の多いDPC14桁分類についてDPCコード、名称、患者数、自院の平均在院日数、全国の平均在院日数、転院率、平均年齢を集計しています。
◇交通事故や労災などによる保険外診療については、集計から除外しています。
◇5位のDPCコードについては、患者数10症例未満のため、各項目を非公開としています。
◇転院数10症例未満の症例は、転院率を非公開としています。
【解説】
救急・集中治療科では、救急外来を受診した患者さんに対して、初期診療から緊急手術、集中治療管理まで一貫した医療を提供しています。専門的な診療が必要な場合には、各診療科と連携し、専門医がその後の治療を引き継ぐことで、効率的かつ質の高い救急医療を実現し、患者さんの救命に貢献しています。また、2020年(令和2年)10月からはドクターカーの運行を開始し、患者さんの搬送に加えて、重症外傷に対する緊急手術や心肺停止患者への人工心肺(ECMO)の導入など、病院到着前から専門的な処置や治療を迅速に開始できる体制を整えています。
患者数別にみると、最も多いのは、外傷によって急性硬膜下血腫、脳震盪、くも膜下出血などを発症した患者さんです。軽症の場合は経過観察のための入院が多く、平均在院日数は5.58日となっています。
2番目に多いのは、薬物中毒の患者さんです。睡眠薬などの意図的な大量内服や、ハチなどの有毒動物による刺傷などが含まれます。多くの患者さんが心理的な問題を抱えているため、身体的な治療に加えて精神科との連携による対応が行われています。
3番目に多いのは、造影剤や薬物、あるいは原因不明によるアナフィラキシーショックの患者さんです。多くは1泊2日の経過観察入院となる、平均在院日数が1.77日と短くなっています。
4番目に多いのは、外傷による頭蓋内損傷の患者さんで、急性硬膜下血腫、脳震盪、くも膜下出血などに加え、頭部挫創などに対して縫合処置を行うケースです。
5番目に多いのは、外傷によって気胸を発症した患者さんに対し、肺から漏れた空気をを排出するための管(胸腔ドレーン)を挿入する処置を行うケースです。これにより肺の膨張を促し、呼吸状態の改善を図ります。
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇各診療科別に患者数の多いDPC14桁分類についてDPCコード、名称、患者数、自院の平均在院日数、全国の平均在院日数、転院率、平均年齢を集計しています。
◇交通事故や労災などによる保険外診療については、集計から除外しています。
◇5位のDPCコードについては、患者数10症例未満のため、各項目を非公開としています。
◇転院数10症例未満の症例は、転院率を非公開としています。
【解説】
救急・集中治療科では、救急外来を受診した患者さんに対して、初期診療から緊急手術、集中治療管理まで一貫した医療を提供しています。専門的な診療が必要な場合には、各診療科と連携し、専門医がその後の治療を引き継ぐことで、効率的かつ質の高い救急医療を実現し、患者さんの救命に貢献しています。また、2020年(令和2年)10月からはドクターカーの運行を開始し、患者さんの搬送に加えて、重症外傷に対する緊急手術や心肺停止患者への人工心肺(ECMO)の導入など、病院到着前から専門的な処置や治療を迅速に開始できる体制を整えています。
患者数別にみると、最も多いのは、外傷によって急性硬膜下血腫、脳震盪、くも膜下出血などを発症した患者さんです。軽症の場合は経過観察のための入院が多く、平均在院日数は5.58日となっています。
2番目に多いのは、薬物中毒の患者さんです。睡眠薬などの意図的な大量内服や、ハチなどの有毒動物による刺傷などが含まれます。多くの患者さんが心理的な問題を抱えているため、身体的な治療に加えて精神科との連携による対応が行われています。
3番目に多いのは、造影剤や薬物、あるいは原因不明によるアナフィラキシーショックの患者さんです。多くは1泊2日の経過観察入院となる、平均在院日数が1.77日と短くなっています。
4番目に多いのは、外傷による頭蓋内損傷の患者さんで、急性硬膜下血腫、脳震盪、くも膜下出血などに加え、頭部挫創などに対して縫合処置を行うケースです。
5番目に多いのは、外傷によって気胸を発症した患者さんに対し、肺から漏れた空気をを排出するための管(胸腔ドレーン)を挿入する処置を行うケースです。これにより肺の膨張を促し、呼吸状態の改善を図ります。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 98 | 17 | 17 | 40 | ー | 28 | 1 | 8 |
| 大腸癌 | 85 | 49 | 63 | 43 | 12 | 29 | 1 | 8 |
| 乳癌 | 70 | 47 | 12 | ー | ー | 12 | 1 | 8 |
| 肺癌 | 202 | 56 | 142 | 119 | 38 | 221 | 1 | 8 |
| 肝癌 | ー | 16 | 11 | ー | ー | 50 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
【集計方法と定義】
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌の5大癌について、初発患者はUICCのTNMから示される病期分類別に、再発患者(再発部位によらない)は期間内の患者数を示しています。
◇患者数は延患者数です。例えば、同一患者さんが入退院を繰り返す場合は、繰り返した回数分を集計します。
◇TNM分類情報は、一連の治療を決定する際に用いた、術前所見に基づいています。
◇TNM分類が不正確等でステージが不明な場合は、「不明」として集計しています。
◇患者数10症例未満のステージについては、患者数を非公開としています。
【解説】
当院は、がん診療連携拠点病院として指定をうけており、がんに対して集学的治療(複数の治療法を組み合わせた総合的な治療)を行っております。紹介率の増加やがん検診の促進により、5大癌(胃癌、大腸癌、肺癌、肝癌、乳癌)については、ステージⅠの早期段階で発見される症例が多い傾向にあります。これは、早期発見・早期治療の体制が整っていることを示しています。
また、肺癌に関しては、再発された患者さんの割合が比較的多く、継続的な治療を受けているケースが多いことも明らかになっています。再発後も治療を継続できる体制が整っていることは、患者さんにとって重要な支えとなっています。
なお、肺癌のステージが不明とされる症例については、がんの疑いがある段階で検査目的の入院をしている場合など、診断が確定していないためにステージの判断ができないケースが含まれています。
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌の5大癌について、初発患者はUICCのTNMから示される病期分類別に、再発患者(再発部位によらない)は期間内の患者数を示しています。
◇患者数は延患者数です。例えば、同一患者さんが入退院を繰り返す場合は、繰り返した回数分を集計します。
◇TNM分類情報は、一連の治療を決定する際に用いた、術前所見に基づいています。
◇TNM分類が不正確等でステージが不明な場合は、「不明」として集計しています。
◇患者数10症例未満のステージについては、患者数を非公開としています。
【解説】
当院は、がん診療連携拠点病院として指定をうけており、がんに対して集学的治療(複数の治療法を組み合わせた総合的な治療)を行っております。紹介率の増加やがん検診の促進により、5大癌(胃癌、大腸癌、肺癌、肝癌、乳癌)については、ステージⅠの早期段階で発見される症例が多い傾向にあります。これは、早期発見・早期治療の体制が整っていることを示しています。
また、肺癌に関しては、再発された患者さんの割合が比較的多く、継続的な治療を受けているケースが多いことも明らかになっています。再発後も治療を継続できる体制が整っていることは、患者さんにとって重要な支えとなっています。
なお、肺癌のステージが不明とされる症例については、がんの疑いがある段階で検査目的の入院をしている場合など、診断が確定していないためにステージの判断ができないケースが含まれています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
| 患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | ー | ー | ー |
| 中等症 | 43 | 14.14 | 68.98 |
| 重症 | 29 | 18.76 | 81.03 |
| 超重症 | 16 | 18.06 | 80.00 |
| 不明 | ー | ー | ー |
【集計方法と定義】
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇成人(20歳以上)の市中肺炎について、重症度別に患者数、平均在院日数、平均年齢を示しています。
◇入院契機傷病名および最も医療資源を投入した傷病名に対するICD10コードがJ13~J18$で始まるものに限定しています。
◇重症度分類は、成人市中肺炎診療ガイドライン(日本呼吸器学会)による分類(A-DROP)を用いて、年齢(Age)、脱水(Dehydration)、呼吸(Respiration)、意識障害(Orientation)、収縮期血圧(Pressure)の各項目1点の5点満点により評価します。
軽症:0点の場合。
中等症:1~2点の場合。
重症:3点の場合。
超重症:4~5点の場合。ただし、ショックがあれば1項目のみでも超重症とする。
不明:重症度分類の各因子が1つでも不明な場合。
◇市中肺炎とは、基礎疾患がない、あるいは軽微な基礎疾患を有する人が普段の社会生活の中でかかる肺炎のことであり、肺炎レンサ球菌による肺炎、インフルエンザ菌による肺炎、肺炎桿菌による肺炎、ブドウ球菌による肺炎等があります。
◇患者数10症例未満の重症度については、各項目を非公開としています。
【解説】
当院では、中等症の患者さんが最も多く、次いで重症、超重症の患者さんが続いています。患者さんの平均年齢も高く、高齢が多い傾向にあります。恒例の患者さんは、慢性の呼吸器疾患を合併していることが多く、重症化した場合には人工呼吸管理を使用した管理下で治療を行っています。
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇成人(20歳以上)の市中肺炎について、重症度別に患者数、平均在院日数、平均年齢を示しています。
◇入院契機傷病名および最も医療資源を投入した傷病名に対するICD10コードがJ13~J18$で始まるものに限定しています。
◇重症度分類は、成人市中肺炎診療ガイドライン(日本呼吸器学会)による分類(A-DROP)を用いて、年齢(Age)、脱水(Dehydration)、呼吸(Respiration)、意識障害(Orientation)、収縮期血圧(Pressure)の各項目1点の5点満点により評価します。
軽症:0点の場合。
中等症:1~2点の場合。
重症:3点の場合。
超重症:4~5点の場合。ただし、ショックがあれば1項目のみでも超重症とする。
不明:重症度分類の各因子が1つでも不明な場合。
◇市中肺炎とは、基礎疾患がない、あるいは軽微な基礎疾患を有する人が普段の社会生活の中でかかる肺炎のことであり、肺炎レンサ球菌による肺炎、インフルエンザ菌による肺炎、肺炎桿菌による肺炎、ブドウ球菌による肺炎等があります。
◇患者数10症例未満の重症度については、各項目を非公開としています。
【解説】
当院では、中等症の患者さんが最も多く、次いで重症、超重症の患者さんが続いています。患者さんの平均年齢も高く、高齢が多い傾向にあります。恒例の患者さんは、慢性の呼吸器疾患を合併していることが多く、重症化した場合には人工呼吸管理を使用した管理下で治療を行っています。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 274 | 24.52 | 75.84 | 47.45% |
| その他 | ー | ー | ー | ー |
【集計方法と定義】
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇脳梗塞の患者数、平均在院日数、平均年齢、転院率を示しています。
◇最も医療資源を投入した傷病のICD10がI63$である症例を集計しています。
◇発症日から「3日以内」「その他」に分けて集計しています。
◇「その他」については、患者数10症例未満のため、各項目を非公開としています。
◇転院数10症例未満の症例は、転院率を非公開としています。
【解説】
栃木県では脳卒中(脳出血、脳梗塞、一過性脳虚血発作、くも膜下出血)の発症数が多く、当院では脳卒中センター設置し、脳卒中による後遺症を最小限に抑えるため、24時間365日体制で診療にあたっています。
脳梗塞の治療は、病型(脳梗塞の種類)や発症部位によって、点滴や内服による治療薬、再発予防薬も異なります。リハビリテーションや手術が必要となる場合もあり、初期段階での正確な病型分類が治療成績を左右するといわれています。そのため、当院では救命センター・診療部・看護部・放射線科・検査技術部が連携し、高度な院内連携システムを構築しています。これにより、超急性期の先進治療から地域と連携を通じた社会復帰まで、包括的な医療を実現しています。
脳梗塞の患者さんのうち、「発症から3日以内」に入院される方は、全体の97.16%を占めています。後遺症の予防と軽減のため、速やかに治療を開始し、症状が安定した後は、患者さんの状態に応じて自宅へ退院や回復期リハビリテーション病院へ転院を行っています。また、患者さんが安心して退院できるよう、入院初期の段階から退院支援を積極的に行っています。「発症から3日以内」に入院された患者さんにうち、転院される方の割合は47.45%となっています。
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇脳梗塞の患者数、平均在院日数、平均年齢、転院率を示しています。
◇最も医療資源を投入した傷病のICD10がI63$である症例を集計しています。
◇発症日から「3日以内」「その他」に分けて集計しています。
◇「その他」については、患者数10症例未満のため、各項目を非公開としています。
◇転院数10症例未満の症例は、転院率を非公開としています。
【解説】
栃木県では脳卒中(脳出血、脳梗塞、一過性脳虚血発作、くも膜下出血)の発症数が多く、当院では脳卒中センター設置し、脳卒中による後遺症を最小限に抑えるため、24時間365日体制で診療にあたっています。
脳梗塞の治療は、病型(脳梗塞の種類)や発症部位によって、点滴や内服による治療薬、再発予防薬も異なります。リハビリテーションや手術が必要となる場合もあり、初期段階での正確な病型分類が治療成績を左右するといわれています。そのため、当院では救命センター・診療部・看護部・放射線科・検査技術部が連携し、高度な院内連携システムを構築しています。これにより、超急性期の先進治療から地域と連携を通じた社会復帰まで、包括的な医療を実現しています。
脳梗塞の患者さんのうち、「発症から3日以内」に入院される方は、全体の97.16%を占めています。後遺症の予防と軽減のため、速やかに治療を開始し、症状が安定した後は、患者さんの状態に応じて自宅へ退院や回復期リハビリテーション病院へ転院を行っています。また、患者さんが安心して退院できるよう、入院初期の段階から退院支援を積極的に行っています。「発症から3日以内」に入院された患者さんにうち、転院される方の割合は47.45%となっています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
循環器内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 348 | 2.59 | 3.04 | ー | 71.47 | |
| K5481 | 経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル) | 146 | 2.75 | 3.54 | ー | 73.12 | |
| K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) | 90 | 0.03 | 8.62 | ー | 69.42 | |
| K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞に対するもの) | 87 | 0.02 | 19.63 | 11.49% | 67.38 | |
| K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他のもの) | 85 | 1.87 | 1.64 | ー | 72.54 |
【集計方法と定義】
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇各診療科別に患者数の多いDPC14桁分類についてDPCコード、名称、患者数、自院の平均在院日数、全国の平均在院日数、転院率、平均年齢を集計しています。
◇転院数10症例未満の症例は、転院率を非公開としています。
【解説】
循環器内科では、狭心症や心筋梗塞などの虚血性心疾患をはじめ、心不全、弁膜症、肺塞栓症、下肢動脈硬化症、不整脈、先天性心疾患など、あらゆる循環器疾患に対して質の高い医療を提供できる診療体制を整えています。とくに心臓の救急疾患に関しては、当院が宇都宮医療圏で唯一の救命救急センターであることから、常に迅速かつ高度な医療が提供できるよう、スタッフ一同が24時間体制で対応しています。
患者数別にみると、最も多いのは、狭心症に対してカテーテルを使用し、冠動脈の狭窄や閉塞部分の治療を行う患者さんです。これらの治療は予約入院による待機的なものだけでなく救急救命センターを併設していることにより、緊急のカテーテル治療にも対応しています。平均在院日数は3.99日と短く、早期の退院が可能です。
2番目に多いのは、狭心症に対して冠動脈の狭窄や閉塞部分の状態を確認するため、心臓カテーテル検査のみを行う患者さんです。
3番目に多いのは、2番目に多い狭心症の患者さんと同様ですが、心臓カテーテル検査に加えて血管内超音波検査などを併用して行うケースです。中等度の冠動脈狭窄では、薬による治療が望ましい場合もあるため、症例ごとにカテーテル治療の適応を慎重に検討しています。
4番目に多いのは、急性心筋梗塞に対し心臓カテーテルを使用し、冠動脈の狭窄や閉塞部分の治療を行う患者さんです。発症から数時間以内の「超急性期」においては、梗塞領域の縮小を目的としてカテーテル手術を行います。当院では救急外来の来院から90分以内にカテーテル手術を開始できるよう、24時間体制を整えています。
5番目に多いのは、心不全の患者さんです。平均年齢は79.93歳となっています。高齢者や心臓弁膜症などの基礎疾患を持つ重症例にも対応できるよう、集中治療室での全身管理を行っています。
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇各診療科別に患者数の多いDPC14桁分類についてDPCコード、名称、患者数、自院の平均在院日数、全国の平均在院日数、転院率、平均年齢を集計しています。
◇転院数10症例未満の症例は、転院率を非公開としています。
【解説】
循環器内科では、狭心症や心筋梗塞などの虚血性心疾患をはじめ、心不全、弁膜症、肺塞栓症、下肢動脈硬化症、不整脈、先天性心疾患など、あらゆる循環器疾患に対して質の高い医療を提供できる診療体制を整えています。とくに心臓の救急疾患に関しては、当院が宇都宮医療圏で唯一の救命救急センターであることから、常に迅速かつ高度な医療が提供できるよう、スタッフ一同が24時間体制で対応しています。
患者数別にみると、最も多いのは、狭心症に対してカテーテルを使用し、冠動脈の狭窄や閉塞部分の治療を行う患者さんです。これらの治療は予約入院による待機的なものだけでなく救急救命センターを併設していることにより、緊急のカテーテル治療にも対応しています。平均在院日数は3.99日と短く、早期の退院が可能です。
2番目に多いのは、狭心症に対して冠動脈の狭窄や閉塞部分の状態を確認するため、心臓カテーテル検査のみを行う患者さんです。
3番目に多いのは、2番目に多い狭心症の患者さんと同様ですが、心臓カテーテル検査に加えて血管内超音波検査などを併用して行うケースです。中等度の冠動脈狭窄では、薬による治療が望ましい場合もあるため、症例ごとにカテーテル治療の適応を慎重に検討しています。
4番目に多いのは、急性心筋梗塞に対し心臓カテーテルを使用し、冠動脈の狭窄や閉塞部分の治療を行う患者さんです。発症から数時間以内の「超急性期」においては、梗塞領域の縮小を目的としてカテーテル手術を行います。当院では救急外来の来院から90分以内にカテーテル手術を開始できるよう、24時間体制を整えています。
5番目に多いのは、心不全の患者さんです。平均年齢は79.93歳となっています。高齢者や心臓弁膜症などの基礎疾患を持つ重症例にも対応できるよう、集中治療室での全身管理を行っています。
消化器内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 81 | 0.52 | 1.43 | ー | 67.95 | |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 56 | 2.64 | 14.86 | ー | 73.36 | |
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 48 | 3.94 | 12.00 | ー | 76.08 | |
| K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | 36 | 3.03 | 10.22 | ー | 74.47 | |
| K533-2 | 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 | 33 | 2.06 | 9.33 | ー | 69.45 |
【集計方法と定義】
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇診療科別に手術件数の多い順に5術式について、患者数、術前日数、術後日数、転院率、平均年齢を示しています。
◇手術術式の点数コード(Kコード)により集計していますが、輸血関連(K920$)、創傷処理、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術、軽微な手術およびすべての加算は除外しています。
◇術前日数は入院日から主たる手術の手術日まで(手術日当日は含まない)の日数、術後日数は主たる手術の手術日から(手術日当日は含まない)退院日まで日数としています。
【解説】
消化器内科において最も多い手術は、長径2cm未満のポリープに対する「内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術」です。これは、内視鏡を用いて大腸ポリープを切除する治療であり、入院当日に手術を実施するケースが多く、平均術後日数は1.43日と短期間での退院が可能です。
2番目に多い手術は、内視鏡的消化管止血術です。胃や十二指腸などの出血部位を内視鏡で確認し、クリップやレーザーにより止血を行います。対象となる疾患は、出血性胃潰瘍や出血性十二指腸潰瘍などで、救急患者さんが多く、緊急対応として入院当日または翌日に手術を行うことが一般的です。そのため、平均術前日数が2.64日となっています。
3番目に多い手術は、内視鏡的胆道ステント留置術です。内視鏡にり十二指腸乳頭を切開し、胆管の狭窄部にステントを留置する治療です。
4番目に多い手術は、内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの)です。内視鏡により十二指腸乳頭を切開し、総胆管結石などを摘出する治療です。
5番目に多い手術は、内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術です。再発しやすい食道・胃静脈瘤に対して、一定期間をおいて繰り返し治療を行うことがあります。
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇診療科別に手術件数の多い順に5術式について、患者数、術前日数、術後日数、転院率、平均年齢を示しています。
◇手術術式の点数コード(Kコード)により集計していますが、輸血関連(K920$)、創傷処理、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術、軽微な手術およびすべての加算は除外しています。
◇術前日数は入院日から主たる手術の手術日まで(手術日当日は含まない)の日数、術後日数は主たる手術の手術日から(手術日当日は含まない)退院日まで日数としています。
【解説】
消化器内科において最も多い手術は、長径2cm未満のポリープに対する「内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術」です。これは、内視鏡を用いて大腸ポリープを切除する治療であり、入院当日に手術を実施するケースが多く、平均術後日数は1.43日と短期間での退院が可能です。
2番目に多い手術は、内視鏡的消化管止血術です。胃や十二指腸などの出血部位を内視鏡で確認し、クリップやレーザーにより止血を行います。対象となる疾患は、出血性胃潰瘍や出血性十二指腸潰瘍などで、救急患者さんが多く、緊急対応として入院当日または翌日に手術を行うことが一般的です。そのため、平均術前日数が2.64日となっています。
3番目に多い手術は、内視鏡的胆道ステント留置術です。内視鏡にり十二指腸乳頭を切開し、胆管の狭窄部にステントを留置する治療です。
4番目に多い手術は、内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの)です。内視鏡により十二指腸乳頭を切開し、総胆管結石などを摘出する治療です。
5番目に多い手術は、内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術です。再発しやすい食道・胃静脈瘤に対して、一定期間をおいて繰り返し治療を行うことがあります。
呼吸器内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K510-3 | 気管支鏡下レーザー腫瘍焼灼術 | 15 | 1.87 | 12.80 | ー | 76.67 | |
| K496-4 | 胸腔鏡下膿胸腔掻爬術 | ー | ー | ー | ー | ー | |
| K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | ー | ー | ー | ー | ー | |
| K509-4 | 気管支瘻孔閉鎖術 | ー | ー | ー | ー | ー | |
| K601-21 | 体外式膜型人工肺(1日につき)(初日) | ー | ー | ー | ー | ー |
【集計方法と定義】
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇診療科別に手術件数の多い順に5術式について、患者数、術前日数、術後日数、転院率、平均年齢を示しています。
◇手術術式の点数コード(Kコード)により集計していますが、輸血関連(K920$)、創傷処理、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術、軽微な手術およびすべての加算は除外しています。
◇術前日数は入院日から主たる手術の手術日まで(手術日当日は含まない)の日数、術後日数は主たる手術の手術日から(手術日当日は含まない)退院日まで日数としています。
◇2位以下のKコードについては、患者数10症例未満のため、各項目を非公開としています
◇転院数10症例未満の症例は、転院率を非公開としています。
【解説】
呼吸器内科で最も多い手術は、気管支鏡下レーザー腫瘍焼灼術です。この手術は、肺癌によって気管支が高度に狭窄したり、完全に閉塞してしまった患者さんに対して、気管支鏡を用いて腫瘍をレーザーで焼灼することで、気道の通過性を改善することを目的としています。
その他にも、胸腔鏡下膿胸腔掻爬術、胃瘻造設術、気管支瘻孔閉鎖術、体外式模型人工肺(ECMO)などが実施されています。胸腔鏡下膿胸腔掻爬術では、膿胸の状態にある患者さんに対して胸腔鏡を使用し、胸腔内にたまった膿を除去する処置を行います。また、胃瘻造設術は、経口摂取が困難な患者さんに対して、胃に直接栄養を送るための管を設置する手術であり、長期的な栄養管理を可能にします。
さらに、気管支瘻孔閉鎖術では、気管支に生じた瘻孔(異常な穴)を閉鎖することで、感染や空気漏れなどの合併症を防ぎます。そして、体外式模型人工肺(ECMO)は、重症の呼吸不全に陥った患者さんに対して、血液を体外で酸素化し、肺の機能を補助する装置を用いた高度な治療法です。
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇診療科別に手術件数の多い順に5術式について、患者数、術前日数、術後日数、転院率、平均年齢を示しています。
◇手術術式の点数コード(Kコード)により集計していますが、輸血関連(K920$)、創傷処理、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術、軽微な手術およびすべての加算は除外しています。
◇術前日数は入院日から主たる手術の手術日まで(手術日当日は含まない)の日数、術後日数は主たる手術の手術日から(手術日当日は含まない)退院日まで日数としています。
◇2位以下のKコードについては、患者数10症例未満のため、各項目を非公開としています
◇転院数10症例未満の症例は、転院率を非公開としています。
【解説】
呼吸器内科で最も多い手術は、気管支鏡下レーザー腫瘍焼灼術です。この手術は、肺癌によって気管支が高度に狭窄したり、完全に閉塞してしまった患者さんに対して、気管支鏡を用いて腫瘍をレーザーで焼灼することで、気道の通過性を改善することを目的としています。
その他にも、胸腔鏡下膿胸腔掻爬術、胃瘻造設術、気管支瘻孔閉鎖術、体外式模型人工肺(ECMO)などが実施されています。胸腔鏡下膿胸腔掻爬術では、膿胸の状態にある患者さんに対して胸腔鏡を使用し、胸腔内にたまった膿を除去する処置を行います。また、胃瘻造設術は、経口摂取が困難な患者さんに対して、胃に直接栄養を送るための管を設置する手術であり、長期的な栄養管理を可能にします。
さらに、気管支瘻孔閉鎖術では、気管支に生じた瘻孔(異常な穴)を閉鎖することで、感染や空気漏れなどの合併症を防ぎます。そして、体外式模型人工肺(ECMO)は、重症の呼吸不全に陥った患者さんに対して、血液を体外で酸素化し、肺の機能を補助する装置を用いた高度な治療法です。
脳神経内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 65 | 0.37 | 25.55 | 66.15% | 77.57 | |
| K386 | 気管切開術 | 11 | 36.91 | 65.91 | ー | 70.64 | |
| K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 10 | 5.00 | 12.20 | ー | 76.10 | |
| K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術を含む。) | ー | ー | ー | ー | ー | |
| K178-2 | 経皮的脳血管形成術 | ー | ー | ー | ー | ー |
【集計方法と定義】
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇診療科別に手術件数の多い順に5術式について、患者数、術前日数、術後日数、転院率、平均年齢を示しています。
◇手術術式の点数コード(Kコード)により集計していますが、輸血関連(K920$)、創傷処理、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術、軽微な手術およびすべての加算は除外しています。
◇術前日数は入院日から主たる手術の手術日まで(手術日当日は含まない)の日数、術後日数は主たる手術の手術日から(手術日当日は含まない)退院日まで日数としています。
◇4位以下のKコードについては、患者数10症例未満のため、各項目を非公開としています。
【解説】
脳神経内科では塞栓性脳梗塞に対して脳神経外科と連携し、治療を行っています。まず、脳神経外科にて脳動脈に詰まった血栓を回収する治療を実施し、その後、速やかに脳神経内科へ転科します。脳神経内科では、急性期の薬物療法とリハビリテーションを組み合わせることで、再発予防のためのリスク低減に務めています。発症後の早期に、適切な血栓回収術、血栓溶解薬物療法、そしてリハビリテーションを行うことで、在宅復帰が可能となります。これらの治療は、患者さんのQOL(生活の質)向上にも大きく寄与しています。
その他にも、当院ではさまざまな高度医療技術を用いた処置を実施しています。具体的には、気管切開術、経皮的頸動脈ステント留置術、経皮的内視鏡下胃瘻造設術、経皮的脳血管形成術などが挙げられます。これらの処置は、患者さんの病態に応じて適切に選択され、専門医による安全かつ効果的な治療が行われています。
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇診療科別に手術件数の多い順に5術式について、患者数、術前日数、術後日数、転院率、平均年齢を示しています。
◇手術術式の点数コード(Kコード)により集計していますが、輸血関連(K920$)、創傷処理、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術、軽微な手術およびすべての加算は除外しています。
◇術前日数は入院日から主たる手術の手術日まで(手術日当日は含まない)の日数、術後日数は主たる手術の手術日から(手術日当日は含まない)退院日まで日数としています。
◇4位以下のKコードについては、患者数10症例未満のため、各項目を非公開としています。
【解説】
脳神経内科では塞栓性脳梗塞に対して脳神経外科と連携し、治療を行っています。まず、脳神経外科にて脳動脈に詰まった血栓を回収する治療を実施し、その後、速やかに脳神経内科へ転科します。脳神経内科では、急性期の薬物療法とリハビリテーションを組み合わせることで、再発予防のためのリスク低減に務めています。発症後の早期に、適切な血栓回収術、血栓溶解薬物療法、そしてリハビリテーションを行うことで、在宅復帰が可能となります。これらの治療は、患者さんのQOL(生活の質)向上にも大きく寄与しています。
その他にも、当院ではさまざまな高度医療技術を用いた処置を実施しています。具体的には、気管切開術、経皮的頸動脈ステント留置術、経皮的内視鏡下胃瘻造設術、経皮的脳血管形成術などが挙げられます。これらの処置は、患者さんの病態に応じて適切に選択され、専門医による安全かつ効果的な治療が行われています。
腎臓内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純なもの) | 22 | 23.09 | 19.50 | ー | 65.50 | |
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | ー | ー | ー | ー | ー | |
| K616-41 | 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 | ー | ー | ー | ー | ー | |
| K635-3 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | ー | ー | ー | ー | ー | |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | ー | ー | ー | ー | ー |
【集計方法と定義】
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇診療科別に手術件数の多い順に5術式について、患者数、術前日数、術後日数、転院率、平均年齢を示しています。
◇手術術式の点数コード(Kコード)により集計していますが、輸血関連(K920$)、創傷処理、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術、軽微な手術およびすべての加算は除外しています。
◇術前日数は入院日から主たる手術の手術日まで(手術日当日は含まない)の日数、術後日数は主たる手術の手術日から(手術日当日は含まない)退院日まで日数としています。
◇2位以下のKコードについては、患者数10症例未満のため、各項目を非公開としています。
◇転院数10症例未満の症例は、転院率を非公開としています。
【解説】
腎臓内科で最も多い手術は、末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純なもの)です。慢性腎不全によって体内の老廃物を排出できなくなり、腎機能の回復が見込めない場合に、血液透析を行うためのシャント(動脈と静脈をつなぎ合わせた血管)を作成します。この手術では、患者さん自身の血管を使用してシャントを作成します。通常は予約入院で対応しますが、腎機能の急激な悪化により救急搬送される患者さんの場合は、まず状態を安定させる治療を行ったうえで、シャントを作成することが多くなります。そのため、平均術前日数が23.09日と長くなります。
2番目に多い手術は、経皮的冠動脈ステント留置術です。これは、冠動脈硬化症や狭心症の治療に用いられるもので、狭くなった冠動脈にステント(金属製の網状チューブ)を留置して血管を広げ、血流を回復させる治療法です。
そのほかに、連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術、経皮的シャント拡張術・血栓除去術、内視鏡的消化管止血術を行っています。
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇診療科別に手術件数の多い順に5術式について、患者数、術前日数、術後日数、転院率、平均年齢を示しています。
◇手術術式の点数コード(Kコード)により集計していますが、輸血関連(K920$)、創傷処理、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術、軽微な手術およびすべての加算は除外しています。
◇術前日数は入院日から主たる手術の手術日まで(手術日当日は含まない)の日数、術後日数は主たる手術の手術日から(手術日当日は含まない)退院日まで日数としています。
◇2位以下のKコードについては、患者数10症例未満のため、各項目を非公開としています。
◇転院数10症例未満の症例は、転院率を非公開としています。
【解説】
腎臓内科で最も多い手術は、末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純なもの)です。慢性腎不全によって体内の老廃物を排出できなくなり、腎機能の回復が見込めない場合に、血液透析を行うためのシャント(動脈と静脈をつなぎ合わせた血管)を作成します。この手術では、患者さん自身の血管を使用してシャントを作成します。通常は予約入院で対応しますが、腎機能の急激な悪化により救急搬送される患者さんの場合は、まず状態を安定させる治療を行ったうえで、シャントを作成することが多くなります。そのため、平均術前日数が23.09日と長くなります。
2番目に多い手術は、経皮的冠動脈ステント留置術です。これは、冠動脈硬化症や狭心症の治療に用いられるもので、狭くなった冠動脈にステント(金属製の網状チューブ)を留置して血管を広げ、血流を回復させる治療法です。
そのほかに、連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術、経皮的シャント拡張術・血栓除去術、内視鏡的消化管止血術を行っています。
外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K672-2 | 腹腔鏡下胆のう摘出術 | 166 | 1.37 | 3.43 | ー | 61.10 | |
| K6335 | ヘルニア手術(鼠経ヘルニア) | 108 | 0.90 | 2.32 | ー | 74.32 | |
| K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 89 | 1.00 | 2.13 | ー | 65.99 | |
| K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 70 | 2.47 | 8.26 | ー | 71.84 | |
| K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)) | 63 | 1.21 | 3.49 | ー | 62.84 |
【集計方法と定義】
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇診療科別に手術件数の多い順に5術式について、患者数、術前日数、術後日数、転院率、平均年齢を示しています。
◇手術術式の点数コード(Kコード)により集計していますが、輸血関連(K920$)、創傷処理、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術、軽微な手術およびすべての加算は除外しています。
◇術前日数は入院日から主たる手術の手術日まで(手術日当日は含まない)の日数、術後日数は主たる手術の手術日から(手術日当日は含まない)退院日まで日数としています。
◇転院数10症例未満のため、転院率を非公開としています。
【解説】
外科で最も多い手術は、腹腔鏡下による胆のう摘出術です。この手術は、胆のう炎や胆のう結石症に対して行われ、腹腔鏡を使って腹腔内を観察しながら、腹壁に開けた小さい穴から鉗子などの器具を挿入して胆のうを摘出します。腹壁への損傷が少ないため、術後の痛みが軽く、入院期間や回復までの時間も短縮されます。また、傷が小さく目立ちにくいため、美容面でも優れているという利点があります。術後は早期に歩行や食事を開始できるため、平均術後日数は3.34日と短くなっています。
2番目に多い手術は、前方アプローチ法による鼠径ヘルニアの手術です。腹腔鏡下手術に比べると平均術後日数はやや長くなりますが、それでも2.32日と短期間での退院が可能です。
3番目に多い手術は、腹腔鏡下で行う鼠径ヘルニア手術です。こちらはさらに術後の回復が早く、平均術後日数は2.13日となっています。
4番目に多い手術は、腹腔鏡下による結腸の悪性腫瘍切除術です。腹腔鏡を用いた低侵襲手術であるため、平均術後日数は8.26日となっています。
5番目に多い手術は、腋窩部の郭清を伴わない乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術)です。この手術では、腫瘍を含む乳腺組織を扇型または円状に部分的に切除し、乳房を温存します。乳房の温存が可能な症例が対象となり、美容面や心理的負担の軽減にも配慮されています。平均術後日数は3.49日です。
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇診療科別に手術件数の多い順に5術式について、患者数、術前日数、術後日数、転院率、平均年齢を示しています。
◇手術術式の点数コード(Kコード)により集計していますが、輸血関連(K920$)、創傷処理、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術、軽微な手術およびすべての加算は除外しています。
◇術前日数は入院日から主たる手術の手術日まで(手術日当日は含まない)の日数、術後日数は主たる手術の手術日から(手術日当日は含まない)退院日まで日数としています。
◇転院数10症例未満のため、転院率を非公開としています。
【解説】
外科で最も多い手術は、腹腔鏡下による胆のう摘出術です。この手術は、胆のう炎や胆のう結石症に対して行われ、腹腔鏡を使って腹腔内を観察しながら、腹壁に開けた小さい穴から鉗子などの器具を挿入して胆のうを摘出します。腹壁への損傷が少ないため、術後の痛みが軽く、入院期間や回復までの時間も短縮されます。また、傷が小さく目立ちにくいため、美容面でも優れているという利点があります。術後は早期に歩行や食事を開始できるため、平均術後日数は3.34日と短くなっています。
2番目に多い手術は、前方アプローチ法による鼠径ヘルニアの手術です。腹腔鏡下手術に比べると平均術後日数はやや長くなりますが、それでも2.32日と短期間での退院が可能です。
3番目に多い手術は、腹腔鏡下で行う鼠径ヘルニア手術です。こちらはさらに術後の回復が早く、平均術後日数は2.13日となっています。
4番目に多い手術は、腹腔鏡下による結腸の悪性腫瘍切除術です。腹腔鏡を用いた低侵襲手術であるため、平均術後日数は8.26日となっています。
5番目に多い手術は、腋窩部の郭清を伴わない乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術)です。この手術では、腫瘍を含む乳腺組織を扇型または円状に部分的に切除し、乳房を温存します。乳房の温存が可能な症例が対象となり、美容面や心理的負担の軽減にも配慮されています。平均術後日数は3.49日です。
呼吸器外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの)(ダヴィンチ手術を含む) | 57 | 1.19 | 7.70 | ー | 68.42 | |
| K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 19 | 1.68 | 3.95 | ー | 69.89 | |
| K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除)(ダヴィンチ手術を含む) | 15 | 1.40 | 7.20 | ー | 68.53 | |
| K504-2 | 胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術(ダヴィンチ手術を含む) | 10 | 1.00 | 4.90 | ー | 57.60 | |
| K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの)) | ー | ー | ー | ー | ー |
【集計方法と定義】
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇診療科別に手術件数の多い順に5術式について、患者数、術前日数、術後日数、転院率、平均年齢を示しています。
◇手術術式の点数コード(Kコード)により集計していますが、輸血関連(K920$)、創傷処理、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術、軽微な手術およびすべての加算は除外しています。
◇術前日数は入院日から主たる手術の手術日まで(手術日当日は含まない)の日数、術後日数は主たる手術の手術日から(手術日当日は含まない)退院日までの日数としています。
◇5位のKコードについては、患者数10症例未満のため、各項目を非公開としています。
◇転院数10症例未満の症例は、転院率を非公開としています。
【解説】
呼吸器外科で最も多い手術は、肺癌に対して行う胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの)です。当科では、2020年(令和2年)11月より、手術支援ロボット「ダヴィンチ」(注1* )を導入し、胸腔鏡下での手術を積極的に行っています。この術式は、身体への負担が少ない低侵襲手術であるため、呼吸機能を温存ができる点が大きな利点となっており、高齢の患者さんや合併症を抱える患者さんにとっても安全性の高い選択しとなっています。一方で、胸腔鏡下手術は視野が限られる中で行われるため、突発的な出血などに対して迅速かつ柔軟な対応が求められ、高度な技術が必要となります。クリニカルパスを適用しており、平均術後日数は7.70日と比較的短く、効率的な入院・治療が可能です。
2番目に多い手術は、肺癌に対して行う胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除)です。これは腫瘍の大きさや位置に応じて、肺の一部のみを切除する術式で、より呼吸機能を温存しやすい点が特徴です。
3番目に多い手術は、肺癌に対して行う胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除)です。区域切除は、肺の機能単位である区域ごとに腫瘍を取り除く方法で、部分切除よりも広範囲ながら、肺葉切除よりは機能温存が可能です。
4番目に多い手術は、縦隔・胸膜・胸腺に発生した悪性腫瘍に対して行う胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術です。これらの腫瘍に対しても、胸腔鏡を用いた低侵襲手術が主流となっており、患者さんの回復を早める効果が期待されています。
5番目に多い手術は、気胸、良性肺腫瘍、肺の炎症性疾患などに対して行う胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの))です。この手術は、肺の一部をくさび状に切除することで病変を取り除く方法で、再発や空気漏れなどの症状に対して有効な治療手段となっています。
注1* 手術支援ロボット「ダヴィンチ」 高度なロボット工学技術を駆使した最先端の手術支援ロボット。患者さんの体に1~2cmの小さな穴を数か所開け、そこへロボットアームや内視鏡を挿入します。術者は患者さんに触れずに、離れた場所から高画質で立体的な3D画像を見ながら、ハンドルやフットペダルを操作して手術を行います。
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇診療科別に手術件数の多い順に5術式について、患者数、術前日数、術後日数、転院率、平均年齢を示しています。
◇手術術式の点数コード(Kコード)により集計していますが、輸血関連(K920$)、創傷処理、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術、軽微な手術およびすべての加算は除外しています。
◇術前日数は入院日から主たる手術の手術日まで(手術日当日は含まない)の日数、術後日数は主たる手術の手術日から(手術日当日は含まない)退院日までの日数としています。
◇5位のKコードについては、患者数10症例未満のため、各項目を非公開としています。
◇転院数10症例未満の症例は、転院率を非公開としています。
【解説】
呼吸器外科で最も多い手術は、肺癌に対して行う胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの)です。当科では、2020年(令和2年)11月より、手術支援ロボット「ダヴィンチ」(注1* )を導入し、胸腔鏡下での手術を積極的に行っています。この術式は、身体への負担が少ない低侵襲手術であるため、呼吸機能を温存ができる点が大きな利点となっており、高齢の患者さんや合併症を抱える患者さんにとっても安全性の高い選択しとなっています。一方で、胸腔鏡下手術は視野が限られる中で行われるため、突発的な出血などに対して迅速かつ柔軟な対応が求められ、高度な技術が必要となります。クリニカルパスを適用しており、平均術後日数は7.70日と比較的短く、効率的な入院・治療が可能です。
2番目に多い手術は、肺癌に対して行う胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除)です。これは腫瘍の大きさや位置に応じて、肺の一部のみを切除する術式で、より呼吸機能を温存しやすい点が特徴です。
3番目に多い手術は、肺癌に対して行う胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除)です。区域切除は、肺の機能単位である区域ごとに腫瘍を取り除く方法で、部分切除よりも広範囲ながら、肺葉切除よりは機能温存が可能です。
4番目に多い手術は、縦隔・胸膜・胸腺に発生した悪性腫瘍に対して行う胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術です。これらの腫瘍に対しても、胸腔鏡を用いた低侵襲手術が主流となっており、患者さんの回復を早める効果が期待されています。
5番目に多い手術は、気胸、良性肺腫瘍、肺の炎症性疾患などに対して行う胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの))です。この手術は、肺の一部をくさび状に切除することで病変を取り除く方法で、再発や空気漏れなどの症状に対して有効な治療手段となっています。
注1* 手術支援ロボット「ダヴィンチ」 高度なロボット工学技術を駆使した最先端の手術支援ロボット。患者さんの体に1~2cmの小さな穴を数か所開け、そこへロボットアームや内視鏡を挿入します。術者は患者さんに触れずに、離れた場所から高画質で立体的な3D画像を見ながら、ハンドルやフットペダルを操作して手術を行います。
整形外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0821 | 人工関節置換術(股、膝) | 191 | 2.18 | 14.53 | 51.83% | 69.49 | |
| K0461 | 骨折観血的手術(上腕、大腿) | 85 | 1.40 | 11.96 | 37.65% | 61.56 | |
| K0462 | 骨折観血的手術(前腕、下腿) | 70 | 2.46 | 6.99 | ー | 50.41 | |
| K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(椎弓切除) | 49 | 2.92 | 14.33 | ー | 70.51 | |
| K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(椎弓形成) | 44 | 4.59 | 17.05 | 29.55% | 71.50 |
【集計方法と定義】
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇診療科別に手術件数の多い順に5術式について、患者数、術前日数、術後日数、転院率、平均年齢を示しています。
◇手術術式の点数コード(Kコード)により集計していますが、輸血関連(K920$)、創傷処理、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術、軽微な手術およびすべての加算は除外しています。
◇術前日数は入院日から主たる手術の手術日まで(手術日当日は含まない)の日数、術後日数は主たる手術の手術日から(手術日当日は含まない)退院日まで日数としています。
◇交通事故や労災などによる保険外診療については、集計から除外しています。
◇転院数10症例未満の症例は、転院率を非公開としています。
【解説】
整形外科で最も多い手術は、人工関節置換術(肩、股、膝)です。当院は人工関節センターを設置しているため、人工関節置換術を積極的に実施しています。中でも、変形性股関節症や変形性膝関節症に対して行う、関節の置換術が最も多くなっています。
2番目に多い手術は、骨折観血的手術(上腕、大腿)です。救命救急センターを併設しているため、交通事故や転倒による骨折の患者さんが多く、専門の医師が診療を担当しています。その中でも、大腿骨骨折が最も多くなっています。併存症を有する患者さんが多いため、術前には他科への依頼が必要となることがあり、手術までの平均術前日数は1.40日となっています。また、当院は地域の病院と連携しており、継続してリハビリが可能な体制を整えているため、転院率は37.65%となっています。
3番目に多い手術は、骨折観血的手術(前腕、下腿)です。前腕(橈骨、尺骨)や下腿(脛骨、腓骨)の骨折に対して、プレートやねじ、鋼線などを用いて骨折部位を固定する手術を行っています。
4番目および5番目に多い手術は、腰部脊柱管狭窄症や頚椎症性脊髄症の患者さんに対して行う椎弓切除術・椎弓形成術です。これらの疾患に対しては、脊椎・脊髄外科の専門医が診療を担当しています。
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇診療科別に手術件数の多い順に5術式について、患者数、術前日数、術後日数、転院率、平均年齢を示しています。
◇手術術式の点数コード(Kコード)により集計していますが、輸血関連(K920$)、創傷処理、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術、軽微な手術およびすべての加算は除外しています。
◇術前日数は入院日から主たる手術の手術日まで(手術日当日は含まない)の日数、術後日数は主たる手術の手術日から(手術日当日は含まない)退院日まで日数としています。
◇交通事故や労災などによる保険外診療については、集計から除外しています。
◇転院数10症例未満の症例は、転院率を非公開としています。
【解説】
整形外科で最も多い手術は、人工関節置換術(肩、股、膝)です。当院は人工関節センターを設置しているため、人工関節置換術を積極的に実施しています。中でも、変形性股関節症や変形性膝関節症に対して行う、関節の置換術が最も多くなっています。
2番目に多い手術は、骨折観血的手術(上腕、大腿)です。救命救急センターを併設しているため、交通事故や転倒による骨折の患者さんが多く、専門の医師が診療を担当しています。その中でも、大腿骨骨折が最も多くなっています。併存症を有する患者さんが多いため、術前には他科への依頼が必要となることがあり、手術までの平均術前日数は1.40日となっています。また、当院は地域の病院と連携しており、継続してリハビリが可能な体制を整えているため、転院率は37.65%となっています。
3番目に多い手術は、骨折観血的手術(前腕、下腿)です。前腕(橈骨、尺骨)や下腿(脛骨、腓骨)の骨折に対して、プレートやねじ、鋼線などを用いて骨折部位を固定する手術を行っています。
4番目および5番目に多い手術は、腰部脊柱管狭窄症や頚椎症性脊髄症の患者さんに対して行う椎弓切除術・椎弓形成術です。これらの疾患に対しては、脊椎・脊髄外科の専門医が診療を担当しています。
脳神経外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 38 | 2.00 | 15.18 | ー | 79.82 | |
| K1642 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)(硬膜下のもの) | 20 | 0.60 | 58.65 | 85.00% | 71.30 | |
| K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 19 | 0.37 | 28.16 | ー | 61.26 | |
| K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 18 | 0.61 | 36.00 | ー | 66.11 | |
| K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)(脳内のもの) | 17 | 2.18 | 48.00 | 76.47% | 62.41 |
【集計方法と定義】
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇診療科別に手術件数の多い順に5術式について、患者数、術前日数、術後日数、転院率、平均年齢を示しています。
◇手術術式の点数コード(Kコード)により集計していますが、輸血関連(K920$)、創傷処理、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術、軽微な手術およびすべての加算は除外しています。
◇術前日数は入院日から主たる手術の手術日まで(手術日当日は含まない)の日数、術後日数は主たる手術の手術日から(手術日当日は含まない)退院日まで日数としています。
◇交通事故や労災などによる保険外診療については、集計から除外しています。
【解説】
脳神経外科で最も多く行われている手術は、慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術です。これは、慢性硬膜下血腫に対して行われる手術です。運動麻痺や認知障害などの症状、あるいは頭部外傷をきっかけに発見されることがあります。脳の萎縮がみられる高齢者に多く、平均年齢は79.82歳となっています。診断後に緊急手術が必要となるケースが多く、平均術前日数は2.00日です。手術後は早期から症状の回復が見込まれるため、平均術後日数は15.18日と比較的短期間で退院となっています。
2番目に多い手術は、頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)(硬膜下のもの)です。これは、硬膜下血腫に対して血腫を除去することを目的として行われます。
3番目に多い手術は、脳血管内手術(1箇所)です。脳動脈瘤や脳動静脈奇形などの血管異常に対して、脳血管内にカテーテルを挿入し、プラチナコイルを用いて血管を閉塞させることを目的に行われます。
4番目に多い手術は、脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所)です。これは、脳動脈瘤に対して行われる最も一般的な手術で、未破裂の脳動脈瘤に対して行う場合と、破裂した脳動脈瘤に対して行う場合があります。平均在院日数は破裂の有無によって異なりますが、この手術における平均術後日数は36.00日です。
5番目に多い手術は、頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)(脳内のもの)です。これは、被殻出血や皮質下出血等の脳内出血に対して、血腫を除去することを目的に行われます。
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇診療科別に手術件数の多い順に5術式について、患者数、術前日数、術後日数、転院率、平均年齢を示しています。
◇手術術式の点数コード(Kコード)により集計していますが、輸血関連(K920$)、創傷処理、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術、軽微な手術およびすべての加算は除外しています。
◇術前日数は入院日から主たる手術の手術日まで(手術日当日は含まない)の日数、術後日数は主たる手術の手術日から(手術日当日は含まない)退院日まで日数としています。
◇交通事故や労災などによる保険外診療については、集計から除外しています。
【解説】
脳神経外科で最も多く行われている手術は、慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術です。これは、慢性硬膜下血腫に対して行われる手術です。運動麻痺や認知障害などの症状、あるいは頭部外傷をきっかけに発見されることがあります。脳の萎縮がみられる高齢者に多く、平均年齢は79.82歳となっています。診断後に緊急手術が必要となるケースが多く、平均術前日数は2.00日です。手術後は早期から症状の回復が見込まれるため、平均術後日数は15.18日と比較的短期間で退院となっています。
2番目に多い手術は、頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)(硬膜下のもの)です。これは、硬膜下血腫に対して血腫を除去することを目的として行われます。
3番目に多い手術は、脳血管内手術(1箇所)です。脳動脈瘤や脳動静脈奇形などの血管異常に対して、脳血管内にカテーテルを挿入し、プラチナコイルを用いて血管を閉塞させることを目的に行われます。
4番目に多い手術は、脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所)です。これは、脳動脈瘤に対して行われる最も一般的な手術で、未破裂の脳動脈瘤に対して行う場合と、破裂した脳動脈瘤に対して行う場合があります。平均在院日数は破裂の有無によって異なりますが、この手術における平均術後日数は36.00日です。
5番目に多い手術は、頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)(脳内のもの)です。これは、被殻出血や皮質下出血等の脳内出血に対して、血腫を除去することを目的に行われます。
形成外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹) | 22 | 0.86 | 2.73 | ー | 58.23 | |
| K0053 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4㎝以上) | 11 | 0.55 | 1.36 | ー | 47.82 | |
| K0052 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2㎝以上,4㎝未満) | 10 | 0.60 | 1.30 | ー | 35.40 | |
| K628 | リンパ管吻合術 | ー | ー | ー | ー | ー | |
| K161 | 頭蓋骨腫瘍摘出術 | ー | ー | ー | ー | ー |
【集計方法と定義】
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇診療科別に手術件数の多い順に5術式について、患者数、術前日数、術後日数、転院率、平均年齢を示しています。
◇手術術式の点数コード(Kコード)により集計していますが、輸血関連(K920$)、創傷処理、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術、軽微な手術およびすべての加算は除外しています。
◇術前日数は入院日から主たる手術の手術日まで(手術日当日は含まない)の日数、術後日数は主たる手術の手術日から(手術日当日は含まない)退院日まで日数としています。
◇4位以下のKコードについては、患者数10症例未満のため、各項目を非公開としています。
◇転院数10症例未満の症例は、転院率を非公開としています。
【解説】
形成外科で最も多い手術は、四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術です。これは肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹などにできた良性の軟部腫瘍に対して行われるもので、患者さんの生活の質向上や症状の改善を目的としています。
2番目と3番目に多い手術は、皮膚・皮下腫瘍摘出術(露出部)です。頭部や四肢などの衣服で覆われない部位(露出部)にできた腫瘍に対して行います。なお、皮膚・皮下腫瘍摘出術は、腫瘍の部位や大きさによって、術式のコード(Kコード)や名称が異なります。
4番目に多い手術は、リンパ管吻合術です。リンパ浮腫の患者さんに対して行われ、顕微鏡を用いてリンパ管と静脈をつなぎ、リンパの流れを改善するバイパスを作る高度な技術が必要とされる手術です。
5番目に多い手術は、頭蓋骨腫瘍摘出術で、頭蓋骨にできた良性腫瘍を取り除く手術です。脳や神経に影響を及ぼす可能性があるため、慎重な診断と安全な手術が求められます。
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇診療科別に手術件数の多い順に5術式について、患者数、術前日数、術後日数、転院率、平均年齢を示しています。
◇手術術式の点数コード(Kコード)により集計していますが、輸血関連(K920$)、創傷処理、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術、軽微な手術およびすべての加算は除外しています。
◇術前日数は入院日から主たる手術の手術日まで(手術日当日は含まない)の日数、術後日数は主たる手術の手術日から(手術日当日は含まない)退院日まで日数としています。
◇4位以下のKコードについては、患者数10症例未満のため、各項目を非公開としています。
◇転院数10症例未満の症例は、転院率を非公開としています。
【解説】
形成外科で最も多い手術は、四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術です。これは肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹などにできた良性の軟部腫瘍に対して行われるもので、患者さんの生活の質向上や症状の改善を目的としています。
2番目と3番目に多い手術は、皮膚・皮下腫瘍摘出術(露出部)です。頭部や四肢などの衣服で覆われない部位(露出部)にできた腫瘍に対して行います。なお、皮膚・皮下腫瘍摘出術は、腫瘍の部位や大きさによって、術式のコード(Kコード)や名称が異なります。
4番目に多い手術は、リンパ管吻合術です。リンパ浮腫の患者さんに対して行われ、顕微鏡を用いてリンパ管と静脈をつなぎ、リンパの流れを改善するバイパスを作る高度な技術が必要とされる手術です。
5番目に多い手術は、頭蓋骨腫瘍摘出術で、頭蓋骨にできた良性腫瘍を取り除く手術です。脳や神経に影響を及ぼす可能性があるため、慎重な診断と安全な手術が求められます。
心臓血管外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5612イ | ステントグラフト内挿術(胸部大動脈) | 85 | 3.01 | 9.86 | 11.76% | 73.54 | |
| K5612ロ | ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) | 64 | 1.72 | 8.36 | 75.84 | ||
| K560-22ニ | オープンステントグラフト内挿術(上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術)(その他のもの) | 42 | 1.69 | 31.26 | 42.86% | 67.98 | |
| K597-2 | ペースメーカー交換術 | 38 | 1.00 | 1.00 | 80.58 | ||
| K6154 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(その他のもの) | 20 | 0.90 | 2.85 | 72.70 |
【集計方法と定義】
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇診療科別に手術件数の多い順に5術式について、患者数、術前日数、術後日数、転院率、平均年齢を示しています。
◇手術術式の点数コード(Kコード)により集計していますが、輸血関連(K920$)、創傷処理、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術、軽微な手術およびすべての加算は除外しています。
◇術前日数は入院日から主たる手術の手術日まで(手術日当日は含まない)の日数、術後日数は主たる手術の手術日から(手術日当日は含まない)退院日まで日数としています。
◇転院数10症例未満の症例は、転院率を非公開としています。
【解説】
心臓血管外科で最も多い手術は、胸部大動脈瘤、解離性胸部大動脈瘤に対して行うステントグラフト内挿術です。
2番目に多い手術は、腹部大動脈瘤や腹部大動脈瘤破裂に対して行うステントグラフト内挿術です。ステントグラフト手術は、カテーテルを用いて人工血管(ステントグラフト)を血管内に留置し、血管を内側から補強することで動脈瘤の破裂を防ぎぐ治療法です。開胸や開腹を伴わない低侵襲な手術であるため、高齢者や高血圧、冠動脈疾患などの合併症を抱える患者さんにとって、身体への負担が少なく安全性の高い選択肢となっています。このような背景から、高齢の患者さんでも手術が可能となっており、胸部大動脈瘤に対する手術の平均年齢は73.54歳、腹部大動脈では75.84歳と高い傾向にあります。
3番目に多い手術は、オープンステントグラフト内挿術です。上行大動脈や弓部大動脈瘤、大動脈解離に対して行われます。この術式は、開胸を伴う大動脈の外科的治療とステントグラフトの留置を組み合わせたもので、より広範囲な病変に対応するための高度な技術が求められます。
4番目に多い手術は、ペースメーカー交換術です。バッテリーの消耗や電気回路の不具合などにより、既存のペースメーカーを新しいものに交換する手術です。患者さんの心拍を安定させるために欠かせない処置であり、定期的な管理が重要です。
5番目に多い手術は、血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(その他のもの)です。主に、腸骨動脈瘤や腹部大動脈瘤などに対して行います。血管内に塞栓物質を注入することで血流を遮断し、病変の進行や破裂を防ぐことを目的としています。
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇診療科別に手術件数の多い順に5術式について、患者数、術前日数、術後日数、転院率、平均年齢を示しています。
◇手術術式の点数コード(Kコード)により集計していますが、輸血関連(K920$)、創傷処理、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術、軽微な手術およびすべての加算は除外しています。
◇術前日数は入院日から主たる手術の手術日まで(手術日当日は含まない)の日数、術後日数は主たる手術の手術日から(手術日当日は含まない)退院日まで日数としています。
◇転院数10症例未満の症例は、転院率を非公開としています。
【解説】
心臓血管外科で最も多い手術は、胸部大動脈瘤、解離性胸部大動脈瘤に対して行うステントグラフト内挿術です。
2番目に多い手術は、腹部大動脈瘤や腹部大動脈瘤破裂に対して行うステントグラフト内挿術です。ステントグラフト手術は、カテーテルを用いて人工血管(ステントグラフト)を血管内に留置し、血管を内側から補強することで動脈瘤の破裂を防ぎぐ治療法です。開胸や開腹を伴わない低侵襲な手術であるため、高齢者や高血圧、冠動脈疾患などの合併症を抱える患者さんにとって、身体への負担が少なく安全性の高い選択肢となっています。このような背景から、高齢の患者さんでも手術が可能となっており、胸部大動脈瘤に対する手術の平均年齢は73.54歳、腹部大動脈では75.84歳と高い傾向にあります。
3番目に多い手術は、オープンステントグラフト内挿術です。上行大動脈や弓部大動脈瘤、大動脈解離に対して行われます。この術式は、開胸を伴う大動脈の外科的治療とステントグラフトの留置を組み合わせたもので、より広範囲な病変に対応するための高度な技術が求められます。
4番目に多い手術は、ペースメーカー交換術です。バッテリーの消耗や電気回路の不具合などにより、既存のペースメーカーを新しいものに交換する手術です。患者さんの心拍を安定させるために欠かせない処置であり、定期的な管理が重要です。
5番目に多い手術は、血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(その他のもの)です。主に、腸骨動脈瘤や腹部大動脈瘤などに対して行います。血管内に塞栓物質を注入することで血流を遮断し、病変の進行や破裂を防ぐことを目的としています。
小児科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9131 | 新生児仮死蘇生術(仮死第1度のもの) | 101 | 0.00 | 15.67 | ー | 0.00 | |
| K9132 | 新生児仮死蘇生術(仮死第2度のもの) | 14 | 0.00 | 26.43 | ー | 0.00 | |
| K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他のもの) | ー | ー | ー | ー | ー | |
| K7151 | 腸重積症整復術(非観血的なもの) | ー | ー | ー | ー | ー | |
| K386 | 気管切開術 | ー | ー | ー | ー | ー |
【集計方法と定義】
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています
◇診療科別に手術件数の多い順に5術式について、患者数、術前日数、術後日数、転院率、平均年齢を示しています。
◇手術術式の点数コード(Kコード)により集計していますが、輸血関連(K920$)、創傷処理、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術、軽微な手術およびすべての加算は除外しています。
◇術前日数は入院日から主たる手術の手術日まで(手術日当日は含まない)の日数、術後日数は主たる手術の手術日から(手術日当日は含まない)退院日まで日数としています。
◇3位以下のKコードについては、患者数10症例未満のため、各項目を非公開としています。
◇転院数10症例未満の症例は、転院率を非公開としています。
【解説】
小児科における手術件数の集計では、コード上の分類により「手術」として扱われているものの、実際には処置に近い内容も含まれています。
小児科で最も多い手術は、新生児仮死蘇生術(仮死第1度のもの)です。生まれて間もない新生児は、呼吸や循環の状態が不安定になることがあり、新生児仮死はその代表的な重要原因の1つです。蘇生術は、こうした状態に対して呼吸と循環を補助するために行われるもので、口や鼻からの分泌物の吸引、啼泣を促すための皮膚刺激、酸素の投与、さらには気管内挿管が含まれます。新生児仮死の重症度は、Apgar Score(注1*)により評価します。
2番目に多い手術は、新生児仮死蘇生術(仮死第2度のもの)です。こちらは第1度よりも状態が重く、治療後の経過観察も長期にわたるため、平均術後日数も26.43日と長くなっています。
注1* Apgar Score(アプガースコア)は心拍数、呼吸、筋緊張、反射、皮膚の色について、それぞれ0~2点をつけ、生後1分と5分で判定します。0~10点となり、点数が低い程、悪い状態といえます。第1度仮死は4~6点、第2度仮死は3点以下に相当します。状態に応じて、呼吸と循環の補助のための蘇生術が必要になり、口や鼻からの分泌物の吸引、啼泣のための皮膚刺激、酸素投与、気管内挿管などを行います。
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています
◇診療科別に手術件数の多い順に5術式について、患者数、術前日数、術後日数、転院率、平均年齢を示しています。
◇手術術式の点数コード(Kコード)により集計していますが、輸血関連(K920$)、創傷処理、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術、軽微な手術およびすべての加算は除外しています。
◇術前日数は入院日から主たる手術の手術日まで(手術日当日は含まない)の日数、術後日数は主たる手術の手術日から(手術日当日は含まない)退院日まで日数としています。
◇3位以下のKコードについては、患者数10症例未満のため、各項目を非公開としています。
◇転院数10症例未満の症例は、転院率を非公開としています。
【解説】
小児科における手術件数の集計では、コード上の分類により「手術」として扱われているものの、実際には処置に近い内容も含まれています。
小児科で最も多い手術は、新生児仮死蘇生術(仮死第1度のもの)です。生まれて間もない新生児は、呼吸や循環の状態が不安定になることがあり、新生児仮死はその代表的な重要原因の1つです。蘇生術は、こうした状態に対して呼吸と循環を補助するために行われるもので、口や鼻からの分泌物の吸引、啼泣を促すための皮膚刺激、酸素の投与、さらには気管内挿管が含まれます。新生児仮死の重症度は、Apgar Score(注1*)により評価します。
2番目に多い手術は、新生児仮死蘇生術(仮死第2度のもの)です。こちらは第1度よりも状態が重く、治療後の経過観察も長期にわたるため、平均術後日数も26.43日と長くなっています。
注1* Apgar Score(アプガースコア)は心拍数、呼吸、筋緊張、反射、皮膚の色について、それぞれ0~2点をつけ、生後1分と5分で判定します。0~10点となり、点数が低い程、悪い状態といえます。第1度仮死は4~6点、第2度仮死は3点以下に相当します。状態に応じて、呼吸と循環の補助のための蘇生術が必要になり、口や鼻からの分泌物の吸引、啼泣のための皮膚刺激、酸素投与、気管内挿管などを行います。
産婦人科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 176 | 2.04 | 6.01 | ー | 34.51 | |
| K877 | 子宮全摘術 | 134 | 1.40 | 5.74 | ー | 50.07 | |
| K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 127 | 1.80 | 6.36 | ー | 32.71 | |
| K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) | 63 | 0.89 | 4.05 | ー | 42.75 | |
| K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術(ダヴィンチ手術を含む) | 61 | 1.00 | 4.28 | ー | 47.69 |
【集計方法と定義】
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇診療科別に手術件数の多い順に5術式について、患者数、術前日数、術後日数、転院率、平均年齢を示しています。
◇手術術式の点数コード(Kコード)により集計していますが、輸血関連(K920$)、創傷処理、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術、軽微な手術およびすべての加算は除外しています。
◇術前日数は入院日から主たる手術の手術日まで(手術日当日は含まない)の日数、術後日数は主たる手術の手術日から(手術日当日は含まない)退院日まで日数としています。
◇転院数10症例未満の症例は、転院率を非公開としています。
【解説】
産婦人科で最も多い手術は、選択的帝王切開術です。帝王切開術は、子宮を切開して胎児を娩出させる手術であり、骨盤位(逆子)や既往帝王切開後妊娠(以前に帝王切開をしたことがある)など、事前にリスクが予測される症例に対して、あらかじめ手術日を決めて計画的に行います。
2番目に多い手術は、子宮全摘術です。子宮筋腫や子宮癌、子宮頸部異形成などに対して行う手術です。これらの疾患は主に30?50代の女性に多く見られ、症状の改善や根治を目的として実施されます。
3番目に多い手術は、緊急帝王切開術です。胎児機能不全(胎児仮死)や胎児回旋異常、前期破水など分娩時に予期せぬ合併症が発生した場合に、母体と胎児の安全を確保するため緊急的に行います。最近では、ハイリスク妊娠の増加や児の安全性への意識の高まり、さらには医療訴訟の増加などを背景に、緊急帝王切開の件数も増加傾向にあります。
4番目に多い手術は、子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの)です。これは主に卵巣のう腫や卵巣子宮内膜症のう胞に対して行う手術です。腹腔鏡を用いることで傷が小さく、術後の回復も早いという利点があります。
5番目に多い手術は、腹腔鏡下腟式子宮全摘術(ダヴィンチ手術を含む)です。当科では2021年(令和3年)11月より、手術支援ロボット「ダヴィンチ」(注1* )を導入し、内視鏡下での手術を積極的に行っています。この術式は、傷が小さく術後の痛みが少ないため、早期離床や社会復帰が可能であり、患者さんの生活の質向上にもつながっています。
注1* 手術支援ロボット「ダヴィンチ」 高度なロボット工学技術を駆使した最先端の手術支援ロボット。患者さんの体に1~2cmの小さな穴を数か所開け、そこへロボットアームや内視鏡を挿入します。術者は患者さんに触れずに、離れた場所から高画質で立体的な3D画像を見ながら、ハンドルやフットペダルを操作して手術を行います。
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇診療科別に手術件数の多い順に5術式について、患者数、術前日数、術後日数、転院率、平均年齢を示しています。
◇手術術式の点数コード(Kコード)により集計していますが、輸血関連(K920$)、創傷処理、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術、軽微な手術およびすべての加算は除外しています。
◇術前日数は入院日から主たる手術の手術日まで(手術日当日は含まない)の日数、術後日数は主たる手術の手術日から(手術日当日は含まない)退院日まで日数としています。
◇転院数10症例未満の症例は、転院率を非公開としています。
【解説】
産婦人科で最も多い手術は、選択的帝王切開術です。帝王切開術は、子宮を切開して胎児を娩出させる手術であり、骨盤位(逆子)や既往帝王切開後妊娠(以前に帝王切開をしたことがある)など、事前にリスクが予測される症例に対して、あらかじめ手術日を決めて計画的に行います。
2番目に多い手術は、子宮全摘術です。子宮筋腫や子宮癌、子宮頸部異形成などに対して行う手術です。これらの疾患は主に30?50代の女性に多く見られ、症状の改善や根治を目的として実施されます。
3番目に多い手術は、緊急帝王切開術です。胎児機能不全(胎児仮死)や胎児回旋異常、前期破水など分娩時に予期せぬ合併症が発生した場合に、母体と胎児の安全を確保するため緊急的に行います。最近では、ハイリスク妊娠の増加や児の安全性への意識の高まり、さらには医療訴訟の増加などを背景に、緊急帝王切開の件数も増加傾向にあります。
4番目に多い手術は、子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの)です。これは主に卵巣のう腫や卵巣子宮内膜症のう胞に対して行う手術です。腹腔鏡を用いることで傷が小さく、術後の回復も早いという利点があります。
5番目に多い手術は、腹腔鏡下腟式子宮全摘術(ダヴィンチ手術を含む)です。当科では2021年(令和3年)11月より、手術支援ロボット「ダヴィンチ」(注1* )を導入し、内視鏡下での手術を積極的に行っています。この術式は、傷が小さく術後の痛みが少ないため、早期離床や社会復帰が可能であり、患者さんの生活の質向上にもつながっています。
注1* 手術支援ロボット「ダヴィンチ」 高度なロボット工学技術を駆使した最先端の手術支援ロボット。患者さんの体に1~2cmの小さな穴を数か所開け、そこへロボットアームや内視鏡を挿入します。術者は患者さんに触れずに、離れた場所から高画質で立体的な3D画像を見ながら、ハンドルやフットペダルを操作して手術を行います。
耳鼻咽喉科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 84 | 1.00 | 5.05 | 29.74 | ||
| K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 40 | 0.23 | 5.05 | 43.38 | ||
| K4631 | 甲状腺悪性腫瘍手術(切除)(頸部外側区域郭清を伴わないもの) | 38 | 1.11 | 4.92 | 52.89 | ||
| K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 33 | 1.24 | 4.18 | 54.55 | ||
| K4611 | 甲状腺部分切除術,甲状腺腫摘出術(片葉のみの場合) | 24 | 1.00 | 4.58 | 63.17 |
【集計方法と定義】
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇診療科別に手術件数の多い順に5術式について、患者数、術前日数、術後日数、転院率、平均年齢を示しています。
◇手術術式の点数コード(Kコード)により集計していますが、輸血関連(K920$)、創傷処理、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術、軽微な手術およびすべての加算は除外しています。
◇術前日数は入院日から主たる手術の手術日まで(手術日当日は含まない)の日数、術後日数は主たる手術の手術日から(手術日当日は含まない)退院日まで日数としています。
【解説】
耳鼻咽喉科で最も多い手術は、口蓋扁桃手術(摘出)です。この手術は、慢性扁桃炎(扁桃炎を繰り返す状態)や、扁桃肥大によって嚥下障害や呼吸障害(睡眠時無呼吸症候群など)に対して行う手術です。比較的に若い年齢層の患者さんが多く、平均年齢は28.87歳です。また、クリニカルパスを適用しているため、術後の平均在院数は5.12日と短くなっています。
2番目に多い手術は、扁桃周囲膿瘍切開術です。
3番目に多い手術は、甲状腺悪性腫瘍手術(切除)(頸部外側区域郭清を伴わないもの)です。これは甲状腺癌に対して行われる手術で、腫瘍を含む甲状腺の周囲を切除する場合や、片のみを切除する場合があります。
4番目に多い手術は、内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型です。慢性副鼻腔炎に対して行われます。
5番目に多い手術は、甲状腺部分切除術です。主に甲状腺の良性腫瘍に対して行われています。
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇診療科別に手術件数の多い順に5術式について、患者数、術前日数、術後日数、転院率、平均年齢を示しています。
◇手術術式の点数コード(Kコード)により集計していますが、輸血関連(K920$)、創傷処理、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術、軽微な手術およびすべての加算は除外しています。
◇術前日数は入院日から主たる手術の手術日まで(手術日当日は含まない)の日数、術後日数は主たる手術の手術日から(手術日当日は含まない)退院日まで日数としています。
【解説】
耳鼻咽喉科で最も多い手術は、口蓋扁桃手術(摘出)です。この手術は、慢性扁桃炎(扁桃炎を繰り返す状態)や、扁桃肥大によって嚥下障害や呼吸障害(睡眠時無呼吸症候群など)に対して行う手術です。比較的に若い年齢層の患者さんが多く、平均年齢は28.87歳です。また、クリニカルパスを適用しているため、術後の平均在院数は5.12日と短くなっています。
2番目に多い手術は、扁桃周囲膿瘍切開術です。
3番目に多い手術は、甲状腺悪性腫瘍手術(切除)(頸部外側区域郭清を伴わないもの)です。これは甲状腺癌に対して行われる手術で、腫瘍を含む甲状腺の周囲を切除する場合や、片のみを切除する場合があります。
4番目に多い手術は、内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型です。慢性副鼻腔炎に対して行われます。
5番目に多い手術は、甲状腺部分切除術です。主に甲状腺の良性腫瘍に対して行われています。
眼科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 597 | 0.75 | 1.00 | ー | 75.43 | |
| K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含むもの) | 36 | 0.94 | 4.81 | ー | 64.06 | |
| K2682ロ | 緑内障手術(流出路再建術)(その他のもの) | 28 | 0.89 | 1.00 | ー | 74.68 | |
| K2172 | 眼瞼内反症手術(皮膚切開法) | 20 | 1.00 | 1.00 | ー | 9.60 | |
| K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他のもの) | ー | ー | ー | ー | ー |
【集計方法と定義】
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇診療科別に手術件数の多い順に5術式について、患者数、術前日数、術後日数、転院率、平均年齢を示しています。
◇手術術式の点数コード(Kコード)により集計していますが、輸血関連(K920$)、創傷処理、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術、軽微な手術およびすべての加算は除外しています。
◇術前日数は入院日から主たる手術の手術日まで(手術日当日は含まない)の日数、術後日数は主たる手術の手術日から(手術日当日は含まない)退院日まで日数としています。
◇5位のKコードについては、患者数10症例未満のため、各項目を非公開としています。
◇転院数10症例未満の症例は、転院率を非公開としています。
【解説】
主要な手術ごとの患者数を見ると、最も多いのは水晶体再建術(眼内レンズ挿入)です。これは、白内障に対して行われる一般的な手術です。
2番目と5番目に多いのは、硝子体茎顕微鏡下璃断術です。この手術は、網膜前膜、黄斑円孔、増殖性糖尿病網膜症、裂孔原性網膜剥離、硝子体出血などに対して行われます。硝子体茎を離断する際、硝子体が網膜に強く癒着している場合や、網膜に病変が合併している場合には、網膜の付着組織に対する処置を同時に行います。
3番目に多いのは、緑内障手術です。この手術は、房水の流れる道を広げることで眼圧を下げることを目的としています。
4番目に多いのは、眼瞼内反症手術です。内側に巻き込まれたり、余分な皮膚があるまぶたに対して、睫毛側の皮膚を瞼板へ縫い付けることで、正常な位置に整える手術です。
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇診療科別に手術件数の多い順に5術式について、患者数、術前日数、術後日数、転院率、平均年齢を示しています。
◇手術術式の点数コード(Kコード)により集計していますが、輸血関連(K920$)、創傷処理、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術、軽微な手術およびすべての加算は除外しています。
◇術前日数は入院日から主たる手術の手術日まで(手術日当日は含まない)の日数、術後日数は主たる手術の手術日から(手術日当日は含まない)退院日まで日数としています。
◇5位のKコードについては、患者数10症例未満のため、各項目を非公開としています。
◇転院数10症例未満の症例は、転院率を非公開としています。
【解説】
主要な手術ごとの患者数を見ると、最も多いのは水晶体再建術(眼内レンズ挿入)です。これは、白内障に対して行われる一般的な手術です。
2番目と5番目に多いのは、硝子体茎顕微鏡下璃断術です。この手術は、網膜前膜、黄斑円孔、増殖性糖尿病網膜症、裂孔原性網膜剥離、硝子体出血などに対して行われます。硝子体茎を離断する際、硝子体が網膜に強く癒着している場合や、網膜に病変が合併している場合には、網膜の付着組織に対する処置を同時に行います。
3番目に多いのは、緑内障手術です。この手術は、房水の流れる道を広げることで眼圧を下げることを目的としています。
4番目に多いのは、眼瞼内反症手術です。内側に巻き込まれたり、余分な皮膚があるまぶたに対して、睫毛側の皮膚を瞼板へ縫い付けることで、正常な位置に整える手術です。
泌尿器科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 171 | 1.52 | 4.19 | ー | 71.23 | |
| K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) | 95 | 1.29 | 2.56 | ー | 61.00 | |
| K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(ダヴィンチ手術) | 76 | 1.05 | 8.34 | ー | 69.12 | |
| K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 46 | 2.11 | 7.46 | ー | 71.33 | |
| K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの) | 34 | 1.12 | 4.00 | ー | 71.65 |
【集計方法と定義】
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇診療科別に手術件数の多い順に5術式について、患者数、術前日数、術後日数、転院率、平均年齢を示しています。
◇手術術式の点数コード(Kコード)により集計していますが、輸血関連(K920$)、創傷処理、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術、軽微な手術およびすべての加算は除外しています。
◇術前日数は入院日から主たる手術の手術日まで(手術日当日は含まない)の日数、術後日数は主たる手術の手術日から(手術日当日は含まない)退院日まで日数としています。
◇転院数10症例未満の症例は、転院率を非公開としています。
【解説】
泌尿器科で最も多い手術は、膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの)です。内視鏡によって早期に発見された、浸潤性でない膀胱癌に対して行う手術です。電気メスや切除用電極が進歩したことで、膀胱内視鏡下で使用する液体には、生体にやさしい生理食塩液が用いられています。経尿道的に内視鏡を挿入して切除術を行うため、身体への負担が少なく、平均術後日数は4.19日と短くなっています。
2番目に多い手術は、経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの)です。腎結石症や尿管結石症に対して行う手術です。経尿道的に内視鏡を挿入し、超音波やレーザーを用いて結石を破砕し、バスケットワイヤーカテーテルなどを使って摘出します。クリニカルパスを適用しているため、平均術後日数は2.56日と短く、効率的な治療が可能です。
3番目に多い手術は、腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(ダヴィンチ手術)です。前立腺癌に対して、手術支援ロボット「ダヴィンチ」(注1* )を用いて行われる低侵襲手術であり、精密な操作が可能なため、患者さんの身体的負担が軽減され、術後の回復も早くなります。
4番目に多い手術は、経尿道的尿管ステント留置術です。尿管狭窄、水腎症、急性腎盂腎炎などに対して行う手術です。経尿道的にカテーテルを留置して尿の流れを改善します。尿管狭窄の場合には、バルーンによる拡張も併用されます。多くが緊急入院で対応され、入院当日に手術を行うケースが多く、平均術前日数は2.11日、平均術後日数は7.46日となっています。
5番目に多い手術は、経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術です。前立腺肥大症に対してレーザーを使用し、前立腺組織を蒸散または切除する手術です。クリニカルパスを適用しているため、平均術前日数は1.12日、平均術後日数は4.00日と、短期間での治療が可能です。
注1* 手術支援ロボット「ダヴィンチ」 患者さんの体に1~2cmの小さな穴を数か所開け、そこへロボットアームや内視鏡を挿入します。術者は患者さんに触れずに、離れた場所から高画質で立体的な3D画像を見ながら、ハンドルやフットペダルを操作して手術を行います。
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇診療科別に手術件数の多い順に5術式について、患者数、術前日数、術後日数、転院率、平均年齢を示しています。
◇手術術式の点数コード(Kコード)により集計していますが、輸血関連(K920$)、創傷処理、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術、軽微な手術およびすべての加算は除外しています。
◇術前日数は入院日から主たる手術の手術日まで(手術日当日は含まない)の日数、術後日数は主たる手術の手術日から(手術日当日は含まない)退院日まで日数としています。
◇転院数10症例未満の症例は、転院率を非公開としています。
【解説】
泌尿器科で最も多い手術は、膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの)です。内視鏡によって早期に発見された、浸潤性でない膀胱癌に対して行う手術です。電気メスや切除用電極が進歩したことで、膀胱内視鏡下で使用する液体には、生体にやさしい生理食塩液が用いられています。経尿道的に内視鏡を挿入して切除術を行うため、身体への負担が少なく、平均術後日数は4.19日と短くなっています。
2番目に多い手術は、経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの)です。腎結石症や尿管結石症に対して行う手術です。経尿道的に内視鏡を挿入し、超音波やレーザーを用いて結石を破砕し、バスケットワイヤーカテーテルなどを使って摘出します。クリニカルパスを適用しているため、平均術後日数は2.56日と短く、効率的な治療が可能です。
3番目に多い手術は、腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(ダヴィンチ手術)です。前立腺癌に対して、手術支援ロボット「ダヴィンチ」(注1* )を用いて行われる低侵襲手術であり、精密な操作が可能なため、患者さんの身体的負担が軽減され、術後の回復も早くなります。
4番目に多い手術は、経尿道的尿管ステント留置術です。尿管狭窄、水腎症、急性腎盂腎炎などに対して行う手術です。経尿道的にカテーテルを留置して尿の流れを改善します。尿管狭窄の場合には、バルーンによる拡張も併用されます。多くが緊急入院で対応され、入院当日に手術を行うケースが多く、平均術前日数は2.11日、平均術後日数は7.46日となっています。
5番目に多い手術は、経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術です。前立腺肥大症に対してレーザーを使用し、前立腺組織を蒸散または切除する手術です。クリニカルパスを適用しているため、平均術前日数は1.12日、平均術後日数は4.00日と、短期間での治療が可能です。
注1* 手術支援ロボット「ダヴィンチ」 患者さんの体に1~2cmの小さな穴を数か所開け、そこへロボットアームや内視鏡を挿入します。術者は患者さんに触れずに、離れた場所から高画質で立体的な3D画像を見ながら、ハンドルやフットペダルを操作して手術を行います。
救急・集中治療科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K386 | 気管切開術 | 13 | 10.62 | 36.15 | ー | 66.23 | |
| K6151 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(止血術) | 11 | 0.36 | 15.55 | ー | 67.27 | |
| K601-21 | 体外式膜型人工肺(ECMO) | ー | ー | ー | ー | ー | |
| K6021 | 経皮的心肺補助法(1日につき)(初日) | ー | ー | ー | ー | ー | |
| K046-3 | 一時的創外固定骨折治療術 | ー | ー | ー | ー | ー |
【集計方法と定義】
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇診療科別に手術件数の多い順に5術式について、患者数、術前日数、術後日数、転院率、平均年齢を示しています。
◇手術術式の点数コード(Kコード)により集計していますが、輸血関連(K920$)、創傷処理、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術、軽微な手術およびすべての加算は除外しています。
◇術前日数は入院日から主たる手術の手術日まで(手術日当日は含まない)の日数、術後日数は主たる手術の手術日から(手術日当日は含まない)退院日まで日数としています。
◇3位以下のKコードについては、患者数10症例未満のため、各項目を非公開としています。
◇転院数10症例未満の症例は、転院率を非公開としています。
【解説】
当院では救命救急センター内に「ECMOセンター」を設置し、複数名のECMOスペシャリストが在籍しています。重症患者への対応に加え、ECMOに精通した医療人材の育成にも力を入れており、日本各地の医療機関から研修生を受け入れながら、国内のECMO診療の質向上を目指して活動しています。ECMO導入は院内に限らず、ドクターカーによる他院への出張導入も可能です。2024年度には98件の入院症例に対しECMOを導入し、延べ約927日にもわたる治療を24時間体制で行っています。これにより、院外からの重症患者にも迅速かつ専門的な治療を提供できる体制が整っています。
救急・集中治療科で最も多い手術は、気管切開術です。呼吸困難や喀痰排出困難な患者さんに対し、前頚部を切開し気管カニューレを挿入することで気道を確保する手術であり、呼吸管理の安定化を図るために重要な処置です。
2番目に多い手術は、血管塞栓術で、頭部・胸腔・腹腔内の血管に対して行われます。外傷によって肝臓や脾臓などの腹腔内臓器が損傷した場合や、骨盤骨折による骨盤内血管からの出血に対して、緊急で止血処置を行います。多くの場合、入院当日に実施されます。
3番目に多い手術は、体外式膜型人工肺(ECMO)です。急性呼吸不全や慢性呼吸不全の急性増悪等など、人工呼吸器では対応が困難な症例に対して行われ、呼吸機能を補助をします。特に重症のCOVID-肺炎などで多く使用されており、命をつなぐ重要な治療法です。
4番目に多い手術は、経皮的心肺補助法です。心肺蘇生や重症心不全の患者さんに対して行われる生命維持法のための治療です。心臓と呼吸の両方を補助することで、救命の可能性を高めます。
5番目に多い手術は、一時的創外固定骨折治療術で、骨盤骨折や大腿骨、下腿骨などの重度の骨折に対して行われます。骨折部位を安定させるために、体外から金属器具で固定する処置であり、特に多発外傷の初期対応として重要な役割を果たします。
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇診療科別に手術件数の多い順に5術式について、患者数、術前日数、術後日数、転院率、平均年齢を示しています。
◇手術術式の点数コード(Kコード)により集計していますが、輸血関連(K920$)、創傷処理、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術、軽微な手術およびすべての加算は除外しています。
◇術前日数は入院日から主たる手術の手術日まで(手術日当日は含まない)の日数、術後日数は主たる手術の手術日から(手術日当日は含まない)退院日まで日数としています。
◇3位以下のKコードについては、患者数10症例未満のため、各項目を非公開としています。
◇転院数10症例未満の症例は、転院率を非公開としています。
【解説】
当院では救命救急センター内に「ECMOセンター」を設置し、複数名のECMOスペシャリストが在籍しています。重症患者への対応に加え、ECMOに精通した医療人材の育成にも力を入れており、日本各地の医療機関から研修生を受け入れながら、国内のECMO診療の質向上を目指して活動しています。ECMO導入は院内に限らず、ドクターカーによる他院への出張導入も可能です。2024年度には98件の入院症例に対しECMOを導入し、延べ約927日にもわたる治療を24時間体制で行っています。これにより、院外からの重症患者にも迅速かつ専門的な治療を提供できる体制が整っています。
救急・集中治療科で最も多い手術は、気管切開術です。呼吸困難や喀痰排出困難な患者さんに対し、前頚部を切開し気管カニューレを挿入することで気道を確保する手術であり、呼吸管理の安定化を図るために重要な処置です。
2番目に多い手術は、血管塞栓術で、頭部・胸腔・腹腔内の血管に対して行われます。外傷によって肝臓や脾臓などの腹腔内臓器が損傷した場合や、骨盤骨折による骨盤内血管からの出血に対して、緊急で止血処置を行います。多くの場合、入院当日に実施されます。
3番目に多い手術は、体外式膜型人工肺(ECMO)です。急性呼吸不全や慢性呼吸不全の急性増悪等など、人工呼吸器では対応が困難な症例に対して行われ、呼吸機能を補助をします。特に重症のCOVID-肺炎などで多く使用されており、命をつなぐ重要な治療法です。
4番目に多い手術は、経皮的心肺補助法です。心肺蘇生や重症心不全の患者さんに対して行われる生命維持法のための治療です。心臓と呼吸の両方を補助することで、救命の可能性を高めます。
5番目に多い手術は、一時的創外固定骨折治療術で、骨盤骨折や大腿骨、下腿骨などの重度の骨折に対して行われます。骨折部位を安定させるために、体外から金属器具で固定する処置であり、特に多発外傷の初期対応として重要な役割を果たします。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | ー | ー |
| 異なる | ー | ー | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | 70 | 0.41% |
| 異なる | 41 | 0.24% | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | ー | ー |
| 異なる | ー | ー | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 19 | 0.11% |
| 異なる | ー | ー |
【集計方法】
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇医療資源最傷病名が播種性血管内凝固(DIC)、敗血症、その他の真菌症、手術・術後の合併症について、入院契機病名(DPC6桁レベル)の同一性の有無を区別して症例数を集計しています。
◇発生率は各症例数の全退院患者数に対する割合を示しています。
◇「同一性の有無」とは、各医療資源最傷病の症例(DPC6桁レベル)について、入院契機傷病名に対するICD10コードが、医療資源最傷病名に対応するICDコードに該当している場合は「同一」となります。
◇患者数が10症例未満については、各項目を非公開としています。
【解説】
敗血症は、感染に起因する全身性炎症反応症候群(SIRS)であり、診断には血液培養を含む各種培養検査を実施し、原因菌および原発感染巣の特定が必要です。主な原因菌としては、肺炎球菌、溶連菌、MRSAなどが挙げられます。重症化すると多臓器不全を伴う敗血症性ショックを引き起こすことがあり、厳密な循環管理や必要に応じた昇圧剤の投与が求められます。敗血症性ショックを呈する患者さんには、人工呼吸器による呼吸管理や循環動態の維持が不可欠です。
当院における敗血症の発生状況は、入院時より発症している「入院契機と同一」の患者さんの発生率が0.41%であり、重症例も多く、集中治療が必要となるケースが見られます。
一方、入院後に発症した「入院契機と異なる」患者さんの発生率は0.24%で、手術後の合併症などが原因となることがあります。複数の傷病を抱える患者さんでは重症化すること可能性があり、発症時には各専門科と連携し、集中的な治療を行っています。また、当院は救命救急センターを併設しているため、他院から重症患者さんを紹介を受けるケースも多く、高度な医療体制を整えています。
手術・処置等の合併症では、CT撮影時の造影剤によりショック、抗がん剤など薬剤によるアレルギー症状、CVポート留置後にカテーテル感染、予防接種後の発熱などです。これらの症例はすべて、「入院契機と同一」の患者さんに該当し、発生率は0.11%です。
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇医療資源最傷病名が播種性血管内凝固(DIC)、敗血症、その他の真菌症、手術・術後の合併症について、入院契機病名(DPC6桁レベル)の同一性の有無を区別して症例数を集計しています。
◇発生率は各症例数の全退院患者数に対する割合を示しています。
◇「同一性の有無」とは、各医療資源最傷病の症例(DPC6桁レベル)について、入院契機傷病名に対するICD10コードが、医療資源最傷病名に対応するICDコードに該当している場合は「同一」となります。
◇患者数が10症例未満については、各項目を非公開としています。
【解説】
敗血症は、感染に起因する全身性炎症反応症候群(SIRS)であり、診断には血液培養を含む各種培養検査を実施し、原因菌および原発感染巣の特定が必要です。主な原因菌としては、肺炎球菌、溶連菌、MRSAなどが挙げられます。重症化すると多臓器不全を伴う敗血症性ショックを引き起こすことがあり、厳密な循環管理や必要に応じた昇圧剤の投与が求められます。敗血症性ショックを呈する患者さんには、人工呼吸器による呼吸管理や循環動態の維持が不可欠です。
当院における敗血症の発生状況は、入院時より発症している「入院契機と同一」の患者さんの発生率が0.41%であり、重症例も多く、集中治療が必要となるケースが見られます。
一方、入院後に発症した「入院契機と異なる」患者さんの発生率は0.24%で、手術後の合併症などが原因となることがあります。複数の傷病を抱える患者さんでは重症化すること可能性があり、発症時には各専門科と連携し、集中的な治療を行っています。また、当院は救命救急センターを併設しているため、他院から重症患者さんを紹介を受けるケースも多く、高度な医療体制を整えています。
手術・処置等の合併症では、CT撮影時の造影剤によりショック、抗がん剤など薬剤によるアレルギー症状、CVポート留置後にカテーテル感染、予防接種後の発熱などです。これらの症例はすべて、「入院契機と同一」の患者さんに該当し、発生率は0.11%です。
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率ファイルをダウンロード
| 肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) | 分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) | リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
|---|---|---|
| 3,043 | 2,379 | 78.18% |
【集計方法】
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院された患者さんのうち、15歳以上を集計対象としています。
ただし、入院後 24 時間以内に死亡した患者、臓器移植は集計対象外。
◇自費、自賠責、労災等の保険証を使用しない患者さんは対象外。
◇対象期間(2024年6月1日から2025年5月31日)内に、リスクレベルが「中」以上の手術を実施した患者さんを分母としています。
◇リスクレベルが「中」以上の手術は、「肺血栓塞栓症および深部静脈血栓症の診断,治療,予防に関するガイドライン(2017 年改訂版)」(日本循環器学会等)に準じて抽出。
◇分母のうち、対象期間内に、肺血栓塞栓症予防管理料または抗凝固療を投与した患者さんを分子としています。
◇集計値は次の式で算出した値としています。
(分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者数 / 肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数) ×100
【解説】
肺血栓塞栓症とは、主に足の深い静脈にできた血のかたまり(血栓)が、血液の流れによって肺の血管まで運ばれ、そこで詰まってしまう病気です。この状態になると、肺に血液が届かなくなり、呼吸が苦しくなったり、命に関わる重い症状を引き起こすことがあります。
この病気は、手術後に長時間ベッドで安静にしていることが原因のひとつと考えられています。特に、動かずに横になっている時間が長くなると、足の静脈の血液の流れが滞り、血栓ができやすくなります。そのため、肺血栓塞栓症を予防するには、適切な対策を行うことが重要です。
予防の方法としては、日本循環器学会などが作成した「肺血栓塞栓症および深部静脈血栓症の診断・治療・予防に関するガイドライン(2017年改訂版)」に基づいて、いくつかの手段が推奨されています。まず、弾性ストッキング(着圧ソックス)を着用することで、足に適度な圧力をかけて血液の流れを促し、血栓ができにくくなります。次に、間歇的空気圧迫装置(フットポンプ)を使用することで、足に空気の圧力を断続的にかけて血液循環を助けます。さらに、ヘパリンやワルファリンなどの抗凝固薬を使うことで、血液が固まりにくくなり、血栓の予防につながります。
これらの対策を組み合わせることで、手術後の肺血栓塞栓症のリスクを減らすことができます。当院では、患者さんの状態に応じて、最適な予防方法が選ばれています。
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院された患者さんのうち、15歳以上を集計対象としています。
ただし、入院後 24 時間以内に死亡した患者、臓器移植は集計対象外。
◇自費、自賠責、労災等の保険証を使用しない患者さんは対象外。
◇対象期間(2024年6月1日から2025年5月31日)内に、リスクレベルが「中」以上の手術を実施した患者さんを分母としています。
◇リスクレベルが「中」以上の手術は、「肺血栓塞栓症および深部静脈血栓症の診断,治療,予防に関するガイドライン(2017 年改訂版)」(日本循環器学会等)に準じて抽出。
◇分母のうち、対象期間内に、肺血栓塞栓症予防管理料または抗凝固療を投与した患者さんを分子としています。
◇集計値は次の式で算出した値としています。
(分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者数 / 肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数) ×100
【解説】
肺血栓塞栓症とは、主に足の深い静脈にできた血のかたまり(血栓)が、血液の流れによって肺の血管まで運ばれ、そこで詰まってしまう病気です。この状態になると、肺に血液が届かなくなり、呼吸が苦しくなったり、命に関わる重い症状を引き起こすことがあります。
この病気は、手術後に長時間ベッドで安静にしていることが原因のひとつと考えられています。特に、動かずに横になっている時間が長くなると、足の静脈の血液の流れが滞り、血栓ができやすくなります。そのため、肺血栓塞栓症を予防するには、適切な対策を行うことが重要です。
予防の方法としては、日本循環器学会などが作成した「肺血栓塞栓症および深部静脈血栓症の診断・治療・予防に関するガイドライン(2017年改訂版)」に基づいて、いくつかの手段が推奨されています。まず、弾性ストッキング(着圧ソックス)を着用することで、足に適度な圧力をかけて血液の流れを促し、血栓ができにくくなります。次に、間歇的空気圧迫装置(フットポンプ)を使用することで、足に空気の圧力を断続的にかけて血液循環を助けます。さらに、ヘパリンやワルファリンなどの抗凝固薬を使うことで、血液が固まりにくくなり、血栓の予防につながります。
これらの対策を組み合わせることで、手術後の肺血栓塞栓症のリスクを減らすことができます。当院では、患者さんの状態に応じて、最適な予防方法が選ばれています。
血液培養2セット実施率ファイルをダウンロード
| 血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) | 血液培養2セット実施率 |
|---|---|---|
| 6,347 | 4,992 | 78.65% |
【集計方法】
◇2024年6月1日から2025年5月31日の期間に血液培養検査を実施した患者さん(入院、外来)を集計対象としています。
◇上記の患者さんのうち、血液培養検査が、1 患者 1日毎に実施された日数を集計し、分母としています。
◇血液培養検査の実施回数が 1 日 2 回以上の日数を合計し、分子としています。
◇集計値は次の式で算出した値としています。
(血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数 / 血液培養オーダー日数) ×100
【解説】
血液培養とは、血液の中に細菌や病原体が存在しているかどうかを調べるための検査です。この検査は、敗血症や菌血症などの感染症を診断する際に重要な役割を果たします。血液培養の結果によって、感染の原因となっている菌を特定することができるため、治療方針の決定や感染源の特定に大いに役立ちます。
検査によって病原体が検出されると、その菌に効果のある抗菌薬を選ぶことが可能になります。適切な抗菌薬を用いた治療は、患者さんの命を守るだけでなく、合併症の予防にもつながるため、非常に重要です。
血液培養は、通常2回(2セット)行うことが望ましいとされています。これは、左右の腕など別々の部位から1回ずつ採血する方法です。このように複数回採血する理由は、採血時の消毒が不十分だった場合に、血液中には存在しない菌が混入してしまうのを防ぐためです。もし混入した菌が培養で増えてしまうと、本来の原因菌の特定が難しくなり、正しい診断や治療の妨げになる可能性があります。
そのため、当院でも血液培養を行う際には、必ず2セットの採血を行うことがマニュアルで定められています。これは、より正確な検査結果を得るための大切な手順です。
なお、2024年7月および8月は検査キットの供給不足により、通常は必ず行う2セットの採血を1セットのみで対応したため、実施率が低下しました。これらの月を除くと、実施率は83.46%でした。
また、原則として2セットの採血を行うことになっていますが、患者さんの体調や状況によっては、2セットの採血が困難な場合があり、その際は1セットのみで対応することがあります。
◇2024年6月1日から2025年5月31日の期間に血液培養検査を実施した患者さん(入院、外来)を集計対象としています。
◇上記の患者さんのうち、血液培養検査が、1 患者 1日毎に実施された日数を集計し、分母としています。
◇血液培養検査の実施回数が 1 日 2 回以上の日数を合計し、分子としています。
◇集計値は次の式で算出した値としています。
(血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数 / 血液培養オーダー日数) ×100
【解説】
血液培養とは、血液の中に細菌や病原体が存在しているかどうかを調べるための検査です。この検査は、敗血症や菌血症などの感染症を診断する際に重要な役割を果たします。血液培養の結果によって、感染の原因となっている菌を特定することができるため、治療方針の決定や感染源の特定に大いに役立ちます。
検査によって病原体が検出されると、その菌に効果のある抗菌薬を選ぶことが可能になります。適切な抗菌薬を用いた治療は、患者さんの命を守るだけでなく、合併症の予防にもつながるため、非常に重要です。
血液培養は、通常2回(2セット)行うことが望ましいとされています。これは、左右の腕など別々の部位から1回ずつ採血する方法です。このように複数回採血する理由は、採血時の消毒が不十分だった場合に、血液中には存在しない菌が混入してしまうのを防ぐためです。もし混入した菌が培養で増えてしまうと、本来の原因菌の特定が難しくなり、正しい診断や治療の妨げになる可能性があります。
そのため、当院でも血液培養を行う際には、必ず2セットの採血を行うことがマニュアルで定められています。これは、より正確な検査結果を得るための大切な手順です。
なお、2024年7月および8月は検査キットの供給不足により、通常は必ず行う2セットの採血を1セットのみで対応したため、実施率が低下しました。これらの月を除くと、実施率は83.46%でした。
また、原則として2セットの採血を行うことになっていますが、患者さんの体調や状況によっては、2セットの採血が困難な場合があり、その際は1セットのみで対応することがあります。
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率ファイルをダウンロード
| 広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) | 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) | 広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
|---|---|---|
| 2,549 | 1,530 | 60.02% |
【集計方法】
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院された患者さんを集計対象としています。
ただし、入院後 24 時間以内に死亡した患者、臓器移植は集計対象外。
◇自費、自賠責、労災等の保険証を使用しない患者さんは対象外。
◇上記集計対象の患者さんのうち、対象期間(2024年6月1日から2025年5月31日)において、広域スペクトルの抗菌薬が投与された患者さんを分母としています。
◇分母のうち、当該入院日~抗菌薬投与日までの期間に細菌培養同定検査を実施した患者さんを分子としています。
◇集計値は次の式で算出した値としています。
(分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数 / 広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数) ×100
【解説】
病気の治療で使われる抗菌薬には、いろいろな種類の菌に効く「広域スペクトル抗菌薬」というものがあります。これは、どんな菌が原因かわからないときに、まず広く効く薬を使って治療を始めるためのものです。ただし、この薬を使う前に「本当に菌がいるのか」「どんな菌なのか」を調べることがとても大切です。そのために行うのが「細菌培養検査」です。これは、血液や尿などを調べて、菌がいるかどうかを確認する検査であり、広く効く抗菌薬を使った人のうち、実際にこの検査を受けた人の割合を表しています。この検査をきちんと行うことで、原因となっている菌にぴったり合った薬を選ぶことができ、より効果的な治療につながります。逆に、検査をせずに薬を使い続けると、菌が薬に強くなってしまい、将来その薬が効かなくなることもあります。だからこそ、広く効く抗菌薬を使うときには、できるだけ細菌培養検査を行うことが望ましいとされています。これは患者さんのためだけでなく、社会全体で薬を正しく使っていくためにも大切なことです。
予防的抗菌薬投与および入院日が2024年5月以前を除くと、細菌培養実施率は61.03%でした。
◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院された患者さんを集計対象としています。
ただし、入院後 24 時間以内に死亡した患者、臓器移植は集計対象外。
◇自費、自賠責、労災等の保険証を使用しない患者さんは対象外。
◇上記集計対象の患者さんのうち、対象期間(2024年6月1日から2025年5月31日)において、広域スペクトルの抗菌薬が投与された患者さんを分母としています。
◇分母のうち、当該入院日~抗菌薬投与日までの期間に細菌培養同定検査を実施した患者さんを分子としています。
◇集計値は次の式で算出した値としています。
(分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数 / 広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数) ×100
【解説】
病気の治療で使われる抗菌薬には、いろいろな種類の菌に効く「広域スペクトル抗菌薬」というものがあります。これは、どんな菌が原因かわからないときに、まず広く効く薬を使って治療を始めるためのものです。ただし、この薬を使う前に「本当に菌がいるのか」「どんな菌なのか」を調べることがとても大切です。そのために行うのが「細菌培養検査」です。これは、血液や尿などを調べて、菌がいるかどうかを確認する検査であり、広く効く抗菌薬を使った人のうち、実際にこの検査を受けた人の割合を表しています。この検査をきちんと行うことで、原因となっている菌にぴったり合った薬を選ぶことができ、より効果的な治療につながります。逆に、検査をせずに薬を使い続けると、菌が薬に強くなってしまい、将来その薬が効かなくなることもあります。だからこそ、広く効く抗菌薬を使うときには、できるだけ細菌培養検査を行うことが望ましいとされています。これは患者さんのためだけでなく、社会全体で薬を正しく使っていくためにも大切なことです。
予防的抗菌薬投与および入院日が2024年5月以前を除くと、細菌培養実施率は61.03%でした。
転倒・転落発生率ファイルをダウンロード
| 退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) | 退院患者に発生した転倒・転落件数 (分子) | 転倒・転落発生率 |
|---|---|---|
| 205,370 | 409 | 1.99‰ |
【集計方法】
◇2024年6月1日から2025年5月31日入院および退院された患者さんを集計対象としています。
ただし、入院後 24 時間以内に死亡した患者、臓器移植は集計対象外。
◇自費、自賠責、労災等の保険証を使用しない患者さんは対象外。
◇上記集計対象の患者さんのうち、対象期間(2024年6月1日から2025年5月31日)において、入院期間の総日数(入院患者のべ数)を分母としています。
◇分母のうち、入院中に発生した転倒・転落件数を分子としています。
◇集計値は次の式で算出した値としています。 (転倒・転落の発生件数 / 入院患者のべ数) ×1000 ※単位はパーミル(‰:千分率) 1‰=0.1%
【解説】
転倒・転落の発生件数とは、病院や介護施設などで患者や利用者が転んだり、段差から落ちたりする事故の件数を指します。これらの事故は、医療安全や介護の質を評価するうえで重要な指標のひとつです。
「転倒」とは、本人の意思とは関係なく、地面や床などに足以外の体の一部が接触することを指します。たとえば、つまずいて倒れる、滑って尻もちをつくなどが該当します。一方、「転落」は、ベッドや階段などの高低差のある場所から落ちることを意味します。
転倒・転落は高齢者に多く、骨折や頭部外傷などの重篤な結果を招くこともあるため、医療現場では予防対策が重視されています。たとえば、ベッドの高さ調整、床の滑り止め、歩行補助具の使用、スタッフによる見守りなどが行われています。また、事故が起きた場合には、原因分析と再発防止策の検討が義務づけられている施設もあります。
このように、転倒・転落の発生件数は、医療や介護の安全性を測るバロメーターであり、患者の安心・安全な生活を守るための重要な情報源となっています。
当院における発生率は1.99‰でした。
◇2024年6月1日から2025年5月31日入院および退院された患者さんを集計対象としています。
ただし、入院後 24 時間以内に死亡した患者、臓器移植は集計対象外。
◇自費、自賠責、労災等の保険証を使用しない患者さんは対象外。
◇上記集計対象の患者さんのうち、対象期間(2024年6月1日から2025年5月31日)において、入院期間の総日数(入院患者のべ数)を分母としています。
◇分母のうち、入院中に発生した転倒・転落件数を分子としています。
◇集計値は次の式で算出した値としています。 (転倒・転落の発生件数 / 入院患者のべ数) ×1000 ※単位はパーミル(‰:千分率) 1‰=0.1%
【解説】
転倒・転落の発生件数とは、病院や介護施設などで患者や利用者が転んだり、段差から落ちたりする事故の件数を指します。これらの事故は、医療安全や介護の質を評価するうえで重要な指標のひとつです。
「転倒」とは、本人の意思とは関係なく、地面や床などに足以外の体の一部が接触することを指します。たとえば、つまずいて倒れる、滑って尻もちをつくなどが該当します。一方、「転落」は、ベッドや階段などの高低差のある場所から落ちることを意味します。
転倒・転落は高齢者に多く、骨折や頭部外傷などの重篤な結果を招くこともあるため、医療現場では予防対策が重視されています。たとえば、ベッドの高さ調整、床の滑り止め、歩行補助具の使用、スタッフによる見守りなどが行われています。また、事故が起きた場合には、原因分析と再発防止策の検討が義務づけられている施設もあります。
このように、転倒・転落の発生件数は、医療や介護の安全性を測るバロメーターであり、患者の安心・安全な生活を守るための重要な情報源となっています。
当院における発生率は1.99‰でした。
転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率ファイルをダウンロード
| 退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) | 退院患者に発生したインシデント 影響度分類レベル3b以上の 転倒・転落の発生件数(分子) | 転倒転落によるインシデント影響度 分類レベル3b以上の発生率 |
|---|---|---|
| 205,370 | 7 | 0.03‰ |
【集計方法】
◇2024年6月1日から2025年5月31日入院および退院された患者さんを集計対象としています。
ただし、入院後 24 時間以内に死亡した患者、臓器移植は集計対象外。
◇自費、自賠責、労災等の保険証を使用しない患者さんは対象外。
◇上記集計対象の患者さんのうち、対象期間(2024年6月1日から2025年5月31日)において、入院期間の総日数(入院患者のべ数)を分母としています。
◇分母のうち、入院中に発生した転倒・転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の件数を分子としています。
◇集計値は次の式で算出した値としています。
(インシデント影響度レベル3b以上の転倒・転落の発生件数 / 入院患者のべ数) ×1000 ※単位はパーミル(‰:千分率) 1‰=0.1%
【解説】
この指標では、前指標で説明した「転倒・転落発生率」の中でも、特に患者に一定以上の健康被害を及ぼしたケース、すなわち「インシデント影響度分類レベル3b以上」に該当する事象の発生率を示しています。
インシデント影響度分類レベル3bとは、医療現場で発生した事故や過誤のうち、患者に一時的ではあるものの、治療や処置を必要とする程度の重大な影響を与えたケースを指します。具体的には、転倒によって骨折し手術や入院が必要となった場合や、薬剤の誤投与によって一時的に生命の危険が生じたが、適切な対応により回復した事例などが含まれます。
このようなインシデントが発生した際には、医療スタッフが患者およびご家族に対して説明と謝罪を行い、事故の詳細を記録します。その後、医療安全管理部門への報告がなされ、関係部署で原因分析と再発防止策の検討が行われます。これにより、同様の事象の再発を防ぐための改善が図られます。
医療機関では、インシデントの影響度を段階的に分類することで、事故の深刻度を客観的に評価し、適切な対応を講じる体制を整えています。レベル3bはその中でも、患者の安全に直結する重要な分類であり、医療の質と安全性を維持・向上させるための指標として位置づけられています。
◇2024年6月1日から2025年5月31日入院および退院された患者さんを集計対象としています。
ただし、入院後 24 時間以内に死亡した患者、臓器移植は集計対象外。
◇自費、自賠責、労災等の保険証を使用しない患者さんは対象外。
◇上記集計対象の患者さんのうち、対象期間(2024年6月1日から2025年5月31日)において、入院期間の総日数(入院患者のべ数)を分母としています。
◇分母のうち、入院中に発生した転倒・転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の件数を分子としています。
◇集計値は次の式で算出した値としています。
(インシデント影響度レベル3b以上の転倒・転落の発生件数 / 入院患者のべ数) ×1000 ※単位はパーミル(‰:千分率) 1‰=0.1%
【解説】
この指標では、前指標で説明した「転倒・転落発生率」の中でも、特に患者に一定以上の健康被害を及ぼしたケース、すなわち「インシデント影響度分類レベル3b以上」に該当する事象の発生率を示しています。
インシデント影響度分類レベル3bとは、医療現場で発生した事故や過誤のうち、患者に一時的ではあるものの、治療や処置を必要とする程度の重大な影響を与えたケースを指します。具体的には、転倒によって骨折し手術や入院が必要となった場合や、薬剤の誤投与によって一時的に生命の危険が生じたが、適切な対応により回復した事例などが含まれます。
このようなインシデントが発生した際には、医療スタッフが患者およびご家族に対して説明と謝罪を行い、事故の詳細を記録します。その後、医療安全管理部門への報告がなされ、関係部署で原因分析と再発防止策の検討が行われます。これにより、同様の事象の再発を防ぐための改善が図られます。
医療機関では、インシデントの影響度を段階的に分類することで、事故の深刻度を客観的に評価し、適切な対応を講じる体制を整えています。レベル3bはその中でも、患者の安全に直結する重要な分類であり、医療の質と安全性を維持・向上させるための指標として位置づけられています。
手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率ファイルをダウンロード
| 全身麻酔手術で、 予防的抗菌薬投与が実施された 手術件数(分母) | 分母のうち、手術開始前 1時間以内に予防的抗菌薬が 投与開始された手術件数(分子) | 手術開始前1時間以内の 予防的抗菌薬投与率 |
|---|---|---|
| 4,120 | 4,085 | 99.15% |
【集計方法】
◇2024年6月1日から2025年5月31日入院および退院された患者さんを集計対象としています。
ただし、入院後 24 時間以内に死亡した患者、臓器移植は集計対象外。
◇自費、自賠責、労災等の保険証を使用しない患者さんは対象外。
◇上記集計対象の患者さんのうち、全身麻酔または全身麻酔と硬膜外麻酔併用により手術をした患者さんを分母としています。
◇分母のうち、予防的抗菌薬投与を行った件数を分子としています。
◇集計値は次の式で算出した値としています。
(分母のうち、手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬が投与開始された手術件数/全身麻酔で、予防的抗菌薬投与が実施された手術件数) ×100
【解説】
「手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率」とは、手術を受ける患者に対して、感染を防ぐための抗菌薬(抗生物質)を手術が始まる1時間以内に投与できた割合を示す指標です。
手術では、皮膚を切開したり体の内部に器具を入れたりするため、細菌が入り込んで感染症を起こすリスクがあります。これを「術後感染」と呼びます。術後感染が起きると、傷の治りが遅くなったり、入院期間が延びたり、追加の治療が必要になることがあります。
そのため、感染を未然に防ぐ目的で、手術の直前に抗菌薬を投与することが推奨されています。特に、手術開始の1時間以内に抗菌薬を投与することで、薬の効果が最大限に発揮され、手術中から術後にかけて体内の抗菌薬濃度を適切に保つことができるとされています。
この指標は、病院がどれだけ適切なタイミングで抗菌薬を投与できているかを数値で表すもので、医療の質や安全性を評価するために使われます。高い投与率は、感染予防の体制が整っていることを示し、患者にとっても安心材料となります。
なお、この指標の対象となるのは、全身麻酔を伴うような比較的大きな手術であり、眼科などの軽微な手術は含まれません。また、すでに感染症の治療目的で抗菌薬を使っている患者は、この指標の対象外となります。
このように、「手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率」は、術後感染を防ぐための医療の取り組みがどれだけ適切に行われているかを示す、重要な指標のひとつです。
◇2024年6月1日から2025年5月31日入院および退院された患者さんを集計対象としています。
ただし、入院後 24 時間以内に死亡した患者、臓器移植は集計対象外。
◇自費、自賠責、労災等の保険証を使用しない患者さんは対象外。
◇上記集計対象の患者さんのうち、全身麻酔または全身麻酔と硬膜外麻酔併用により手術をした患者さんを分母としています。
◇分母のうち、予防的抗菌薬投与を行った件数を分子としています。
◇集計値は次の式で算出した値としています。
(分母のうち、手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬が投与開始された手術件数/全身麻酔で、予防的抗菌薬投与が実施された手術件数) ×100
【解説】
「手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率」とは、手術を受ける患者に対して、感染を防ぐための抗菌薬(抗生物質)を手術が始まる1時間以内に投与できた割合を示す指標です。
手術では、皮膚を切開したり体の内部に器具を入れたりするため、細菌が入り込んで感染症を起こすリスクがあります。これを「術後感染」と呼びます。術後感染が起きると、傷の治りが遅くなったり、入院期間が延びたり、追加の治療が必要になることがあります。
そのため、感染を未然に防ぐ目的で、手術の直前に抗菌薬を投与することが推奨されています。特に、手術開始の1時間以内に抗菌薬を投与することで、薬の効果が最大限に発揮され、手術中から術後にかけて体内の抗菌薬濃度を適切に保つことができるとされています。
この指標は、病院がどれだけ適切なタイミングで抗菌薬を投与できているかを数値で表すもので、医療の質や安全性を評価するために使われます。高い投与率は、感染予防の体制が整っていることを示し、患者にとっても安心材料となります。
なお、この指標の対象となるのは、全身麻酔を伴うような比較的大きな手術であり、眼科などの軽微な手術は含まれません。また、すでに感染症の治療目的で抗菌薬を使っている患者は、この指標の対象外となります。
このように、「手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率」は、術後感染を防ぐための医療の取り組みがどれだけ適切に行われているかを示す、重要な指標のひとつです。
d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率ファイルをダウンロード
| 退院患者の在院日数の総和もしくは 除外条件に該当する患者を除いた 入院患者延べ数(分母) | 褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上 の褥瘡)の発生患者数(分子) | d2(真皮までの損傷)以上の 褥瘡発生率 |
|---|---|---|
| 203,335 | 137 | 0.07% |
【集計方法】
◇2024年6月1日から2025年5月31日入院および退院された患者さんを集計対象としています。
ただし、入院後 24 時間以内に死亡した患者、臓器移植は集計対象外。
◇自費、自賠責、労災等の保険証を使用しない患者さんは対象外。
◇同一の日に入院および退院した患者さん、入院時すでに褥瘡をもっていた患者さんは対象外。
◇褥瘡分類は日本褥瘡学会「DESIGN-R分類 2020」(注1*)に基づいています。
◇上記集計対象の患者さんのうち、対象期間(2024年6月1日から2025年5月31日)において、退院患者さんの入院期間の総日数を分母としています。
◇分母のうち、入院中に発生した褥瘡の最大深度がd2(真皮までの損傷)以上の件数を分子としています。
◇集計値は次の式で算出した値としています。
(褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡)の発生患者数/退院患者さんの在院日数の総和) ×100
【解説】
褥瘡は、看護ケアの質評価の重要な指標の1つになっています。
褥瘡が発生すると、患者さんのQOL(生活の質)低下をきたし、結果的に在院日数の長期化や医用費の増大にもつながります。
褥瘡予防対策は重要であり、診療報酬制度にも定められています。褥瘡の治療には、発生予防が最大目標であり、知識の蓄積、予防策計画・実施が重要になります。
高齢化社会に伴い、褥瘡発生のリスクが高い患者さんが増える中、褥瘡発生を少しでも減少させるため、当院では多職種からなる褥瘡対策チームで対策を検討・実施しています。
注1* 「DESIGN-R分類 2020」日本褥瘡学会
Depth(深さ)および内容
d0:皮膚損傷・発赤なし
d1:持続する発赤
d2:真皮までの損傷
D3:皮下組織までの損傷
D4:皮下組織を超える損傷
D5:関節腔、体腔に至る損傷
DTI:深部損傷褥瘡(DTI)疑い
U:壊死組織で覆われ深さの判定が不能
(出典:2024年度 医療の質可視化プロジェクト 適用指標 計画手順書 より抜粋)
◇2024年6月1日から2025年5月31日入院および退院された患者さんを集計対象としています。
ただし、入院後 24 時間以内に死亡した患者、臓器移植は集計対象外。
◇自費、自賠責、労災等の保険証を使用しない患者さんは対象外。
◇同一の日に入院および退院した患者さん、入院時すでに褥瘡をもっていた患者さんは対象外。
◇褥瘡分類は日本褥瘡学会「DESIGN-R分類 2020」(注1*)に基づいています。
◇上記集計対象の患者さんのうち、対象期間(2024年6月1日から2025年5月31日)において、退院患者さんの入院期間の総日数を分母としています。
◇分母のうち、入院中に発生した褥瘡の最大深度がd2(真皮までの損傷)以上の件数を分子としています。
◇集計値は次の式で算出した値としています。
(褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡)の発生患者数/退院患者さんの在院日数の総和) ×100
【解説】
褥瘡は、看護ケアの質評価の重要な指標の1つになっています。
褥瘡が発生すると、患者さんのQOL(生活の質)低下をきたし、結果的に在院日数の長期化や医用費の増大にもつながります。
褥瘡予防対策は重要であり、診療報酬制度にも定められています。褥瘡の治療には、発生予防が最大目標であり、知識の蓄積、予防策計画・実施が重要になります。
高齢化社会に伴い、褥瘡発生のリスクが高い患者さんが増える中、褥瘡発生を少しでも減少させるため、当院では多職種からなる褥瘡対策チームで対策を検討・実施しています。
注1* 「DESIGN-R分類 2020」日本褥瘡学会
Depth(深さ)および内容
d0:皮膚損傷・発赤なし
d1:持続する発赤
d2:真皮までの損傷
D3:皮下組織までの損傷
D4:皮下組織を超える損傷
D5:関節腔、体腔に至る損傷
DTI:深部損傷褥瘡(DTI)疑い
U:壊死組織で覆われ深さの判定が不能
(出典:2024年度 医療の質可視化プロジェクト 適用指標 計画手順書 より抜粋)
65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合ファイルをダウンロード
| 65歳以上の退院患者数 (分母) | 分母のうち、入院後48時間以内に 栄養アセスメントが実施された 患者数(分子) | 65歳以上の患者の入院早期の 栄養アセスメント実施割合 |
|---|---|---|
| 8,737 | 8,656 | 99.07% |
【集計方法】
◇2024年6月1日から2025年5月31日入院および退院された患者さんを集計対象としています。
ただし、入院後 24 時間以内に死亡した患者、臓器移植は集計対象外。
◇自費、自賠責、労災等の保険証を使用しない患者さんは対象外。
◇上記集計対象の患者さんのうち、入院時年齢が65歳以上の患者さんの件数を分母としています。
◇分母のうち、入院後48時間いないの栄養アセスメントを実施した件数を分子としています。
◇集計値は次の式で算出した値としています。
(分母のうち、入院後48時間以内に栄養アセスメントが実施された患者数/65歳以上の退院患者数) ×100
【解説】
「65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合」とは、高齢の患者さんが入院した際に、早い段階で栄養状態の評価(アセスメント)が行われたかどうかを示す割合のことです。これは、医療機関が患者さんの栄養管理にどれだけ力を入れているかを測るための指標です。
高齢者は、加齢や病気の影響で食事量が減ったり、栄養が偏ったりしやすく、低栄養のリスクが高いとされています。低栄養になると、全身状態が低下し、傷の治りが遅くなったり、筋力低下から歩行困難や、転倒しやすくなるなど、さまざまな健康問題につながります。そのため、入院してすぐのタイミングで栄養状態をチェックし、必要に応じて食事の工夫や栄養補助を行うことがとても重要です。
この指標では、65歳以上の患者さんが入院してから、48時間以内に栄養アセスメントが実施されたかどうかを確認します。この割合が高いほど、病院が栄養管理を重視しており、患者さんの健康維持や回復に積極的に取り組んでいると評価されます。逆に、割合が低い場合は、栄養面での対応が遅れたり、見落とされている可能性があるため、改善の余地があると考えられます。
高齢患者さんの健康を守るための第一歩がきちんと踏み出されているかどうかを示す大切な指標です。
◇2024年6月1日から2025年5月31日入院および退院された患者さんを集計対象としています。
ただし、入院後 24 時間以内に死亡した患者、臓器移植は集計対象外。
◇自費、自賠責、労災等の保険証を使用しない患者さんは対象外。
◇上記集計対象の患者さんのうち、入院時年齢が65歳以上の患者さんの件数を分母としています。
◇分母のうち、入院後48時間いないの栄養アセスメントを実施した件数を分子としています。
◇集計値は次の式で算出した値としています。
(分母のうち、入院後48時間以内に栄養アセスメントが実施された患者数/65歳以上の退院患者数) ×100
【解説】
「65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合」とは、高齢の患者さんが入院した際に、早い段階で栄養状態の評価(アセスメント)が行われたかどうかを示す割合のことです。これは、医療機関が患者さんの栄養管理にどれだけ力を入れているかを測るための指標です。
高齢者は、加齢や病気の影響で食事量が減ったり、栄養が偏ったりしやすく、低栄養のリスクが高いとされています。低栄養になると、全身状態が低下し、傷の治りが遅くなったり、筋力低下から歩行困難や、転倒しやすくなるなど、さまざまな健康問題につながります。そのため、入院してすぐのタイミングで栄養状態をチェックし、必要に応じて食事の工夫や栄養補助を行うことがとても重要です。
この指標では、65歳以上の患者さんが入院してから、48時間以内に栄養アセスメントが実施されたかどうかを確認します。この割合が高いほど、病院が栄養管理を重視しており、患者さんの健康維持や回復に積極的に取り組んでいると評価されます。逆に、割合が低い場合は、栄養面での対応が遅れたり、見落とされている可能性があるため、改善の余地があると考えられます。
高齢患者さんの健康を守るための第一歩がきちんと踏み出されているかどうかを示す大切な指標です。
身体的拘束の実施率ファイルをダウンロード
| 退院患者の在院日数の総和 (分母) | 分母のうち、身体的拘束日数の総和 (分子) | 身体的拘束の実施率 |
|---|---|---|
| 176,351 | 13,823 | 7.84% |
【集計方法】
◇2024年6月1日から2025年5月31日入院および退院された患者さんを集計対象としています。
ただし、入院後 24 時間以内に死亡した患者、臓器移植は集計対象外。
◇自費、自賠責、労災等の保険証を使用しない患者さんは対象外。
◇上記集計対象の患者さんのうち、対象期間(2024年6月1日から2025年5月31日)において、退院患者さんの入院期間の総日数を分母としています。
◇分母のうち、身体的拘束を行った日数の合計を分子としています。
◇集計値は次の式で算出した値としています。
(分母のうち、身体的拘束日数の総和/退院患者の在院日数の総和) ×100
【解説】
「身体的拘束の実施率」とは、病院や介護施設などで、患者の動きを制限するために身体的な拘束が行われた割合を示す指標です。これは、医療や介護の現場で安全管理やケアの質を評価するために用いられています。
身体的拘束とは、患者さんの安全を守る目的で、患者さんの身体や衣服に触れる何らかの用具を使って一時的に動きを制限する行為を指します。たとえば、点滴やチューブを自分で抜いてしまう危険がある場合や、転倒のリスクが高い場合などに、やむを得ず行われることがあります。
ただし、身体的拘束は患者さんの自由を奪う行為であり、身体的・精神的な負担や人権の問題にもつながるため、できる限り避けるべきものとされています。現在では、厚生労働省の方針により、身体的拘束の「最小化」が強く求められており、当院では身体的拘束最小化チームを中心に、拘束を減らすための体制を整えています。
実際の調査では、多くの病棟で身体的拘束の実施率は10%未満ですが、患者さんの重症度が高い集中治療室(ICU)などでは、50%を超えるケースも報告されています。そのため、施設ごとの状況や患者さんの状態に応じて、実施率には差があります。
この指標は、医療機関がどれだけ患者の尊厳を守りながら、安全なケアを提供できているかを示す重要なものです。身体的拘束を減らすためには、スタッフの判断力やケアの工夫、環境整備などが求められます。今後は、拘束に頼らないケアの質が、医療の信頼性や患者満足度にも大きく影響していくと考えられています。
◇2024年6月1日から2025年5月31日入院および退院された患者さんを集計対象としています。
ただし、入院後 24 時間以内に死亡した患者、臓器移植は集計対象外。
◇自費、自賠責、労災等の保険証を使用しない患者さんは対象外。
◇上記集計対象の患者さんのうち、対象期間(2024年6月1日から2025年5月31日)において、退院患者さんの入院期間の総日数を分母としています。
◇分母のうち、身体的拘束を行った日数の合計を分子としています。
◇集計値は次の式で算出した値としています。
(分母のうち、身体的拘束日数の総和/退院患者の在院日数の総和) ×100
【解説】
「身体的拘束の実施率」とは、病院や介護施設などで、患者の動きを制限するために身体的な拘束が行われた割合を示す指標です。これは、医療や介護の現場で安全管理やケアの質を評価するために用いられています。
身体的拘束とは、患者さんの安全を守る目的で、患者さんの身体や衣服に触れる何らかの用具を使って一時的に動きを制限する行為を指します。たとえば、点滴やチューブを自分で抜いてしまう危険がある場合や、転倒のリスクが高い場合などに、やむを得ず行われることがあります。
ただし、身体的拘束は患者さんの自由を奪う行為であり、身体的・精神的な負担や人権の問題にもつながるため、できる限り避けるべきものとされています。現在では、厚生労働省の方針により、身体的拘束の「最小化」が強く求められており、当院では身体的拘束最小化チームを中心に、拘束を減らすための体制を整えています。
実際の調査では、多くの病棟で身体的拘束の実施率は10%未満ですが、患者さんの重症度が高い集中治療室(ICU)などでは、50%を超えるケースも報告されています。そのため、施設ごとの状況や患者さんの状態に応じて、実施率には差があります。
この指標は、医療機関がどれだけ患者の尊厳を守りながら、安全なケアを提供できているかを示す重要なものです。身体的拘束を減らすためには、スタッフの判断力やケアの工夫、環境整備などが求められます。今後は、拘束に頼らないケアの質が、医療の信頼性や患者満足度にも大きく影響していくと考えられています。
更新履歴
- 2025年9月29日
- 情報公開
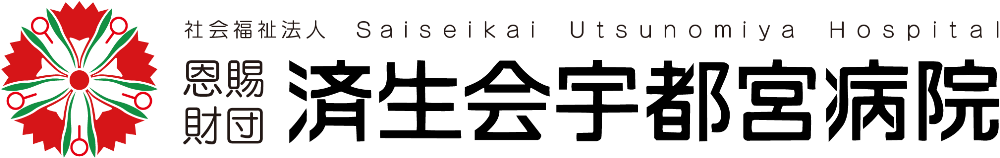

◇2024年6月1日から2025年5月31日に退院した患者さんを対象としています。
◇患者さんの年齢を、階級別(10歳刻み)に集計しています。
◇年齢は入院時の満年齢です。
◇入院後24時間以内に死亡された患者さん、交通事故等による保険外診療(自費)の患者さん、緩和ケア病棟のみ入院された患者さんは集計対象外としています。
【解説】
当院では、母子医療センターおよびバースセンターの運営をはじめ、産科・小児科の診療も行っていることから、新生児からご高齢の方まで、幅広い年齢層の患者さんにご利用いただいております。
年齢階級を10歳刻みで見ると、60歳以上の患者さんが全体の63.14%を占めており、半数を大きく超える割合となっています。さらにその中でも、比較的高齢にあたる70歳以上の患者さんが48.69%を占めており、特に高齢者の受診が多い傾向が見られます。
一方、50歳代以下の年齢層では、10歳未満の患者さんが全体の10.00%を占めており、当院が小児医療にも力を入れていることが反映されています。